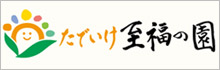セミナー等を通じて、医療・介護・健康産業事業者の未来を見つめています。
セミナー等を通じて、医療・介護・健康産業事業者の未来を見つめています。
該当するセミナーが見つかりませんでした。
| 開催日時 | 2025年9月14日 (日) 開始:12:00 | 終了:17:00 | 開場:11:30 |
|---|---|
| 開催地 | 近畿(大阪府) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 12,000円(お申込み後、クレジット決済となります) |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年2月28日 (土) まで視聴できます。 ☆動画時間:118分 ☆申込〆切:2025年2月21日 (土) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月23日(土) 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 在宅リハビリテーションケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年9月6日 土曜日 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月30日(土) 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 在宅リハビリテーションケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月27日(水) 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・鍼灸師・柔道整復師・看護師・介護福祉士・介護職 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月28日 (木) 開始:20:00| 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 あん摩マッサージ指圧師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年2月28日 (土) まで視聴できます。 ☆動画時間:125分 ☆申込〆切:2025年2月21日 (土) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 あん摩マッサージ指圧師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 合計254分の濃密講義をセットでお届け! 通常価格:2本で4,400円 → セット価格:3,300円(税込) 視聴期間:2025年12月31日まで、何度でも視聴可能! |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・鍼灸師・柔道整復師・看護師・介護福祉士・介護職 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月9日(土) 開始:20:00| 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 保険外リハビリに興味のある方 |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月2日 土曜日 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年8月7日(木) 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・鍼灸師・柔道整復師・看護師・介護福祉士・介護職 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年7月19日 (土) 開始:20:00| 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年7月25日 (金) 開始:20:00 | 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 鍼灸師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年7月30日(水) 開始:20:00 | 終了:22:00 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 機能訓練士指導員を務める方 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 鍼灸師・柔道整復師・介護職・看護師 |
| 主催 | 株式会社WorkShift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年12月31日 (水) まで視聴できます。視聴期間中は何度でも視聴できます。 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション&ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年1月31日 (土) まで視聴できます。 ☆動画時間:119分 ☆申込〆切:2026年1月24日 (土) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 トレーナー 看護師 医師 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | 2025年7月8日 (火) 開始:20:00| 終了:22:00 | 開場:19:45 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 あん摩マッサージ指圧師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年12月31日 (水) まで視聴できます。 ☆動画時間:118分 ☆申込〆切:2025年12月24日 (水) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・鍼灸師・柔道整復師・看護師・介護福祉士・介護職 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年12月31日 (水) まで視聴できます。視聴期間中は何度でも視聴できます。 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード支払いとなります) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年12月31日 (水) まで視聴できます。 ☆動画時間:130分 ☆申込〆切:2025年12月24日 (水) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・鍼灸師・柔道整復師・看護師・介護福祉士・介護職 |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年12月31日 (水) まで視聴できます。視聴期間中は何度でも視聴できます。 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 鍼灸師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年11月30日 (日) まで視聴できます。視聴期間中は何度でも視聴できます。 |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年11月30日 (日) まで視聴できます。視聴期間中は何度でも視聴できます。 ☆動画時間:123分 ☆申込〆切:2025年11月23日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・鍼灸師・柔道整復師・看護師・介護福祉士・介護職 |
| 主催 | 株式会社WorkShift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年10月31日 (金) まで視聴できます。 ☆動画時間:125分 ☆申込〆切:2025年10月24日 (金) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 鍼灸師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年11月30日 (日) まで視聴できます。 ☆動画時間:121分 ☆申込〆切:2025年11月23日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 鍼灸師 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 トレーナー |
| 主催 | 在宅リハビリテーション・ケアスクール |
| 費用 | 2,200円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年10月31日 (金) まで視聴できます。 ☆動画時間:118分 ☆申込〆切:2025年10月24日 (金) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年9月30日 (火) まで視聴できます。 ☆動画時間:121分 ☆申込〆切:2025年9月23日 (火) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
| 開催日時 | ☆配信期間: 2025年8月31日 (日) まで視聴できます。 ☆動画時間:126分 ☆申込〆切:2025年8月24日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | オンライン(オンライン) |
| 対象者 | 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 鍼灸師 柔道整復師 トレーナー |
| 主催 | 株式会社Work Shift |
| 費用 | 3,300円(クレジットカード決済のみ) 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されますので当社のインボイス番号等を記載した参加費の請求書と領収書に関するメールを送信いたします |
![]()
Copyright(c) Work Shift All Rights Reserved.