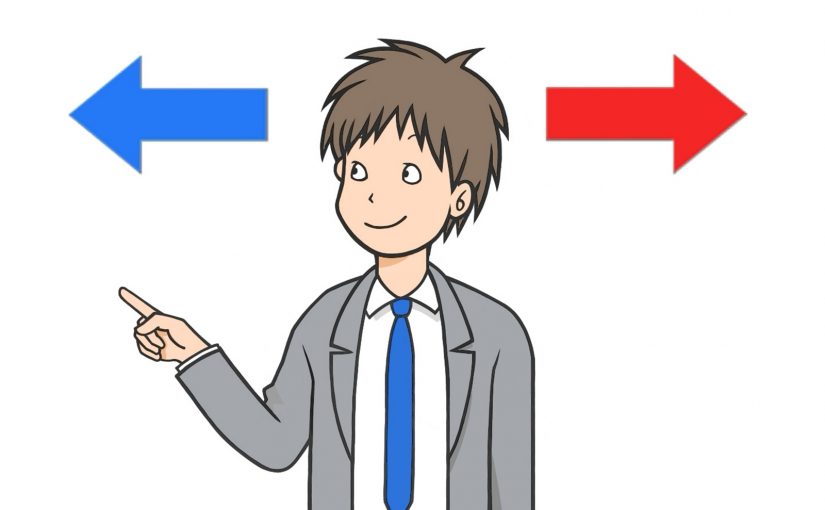「判断」とは、物事の是非や状況を見極め、自らの考えを定める行為である。
一方、「決断」とは、判断を踏まえて選択肢の中から一つを選び、責任をもって実行に移す行為である。
この二つは混同されやすいが、意味合いも役割も大きく異なる。
判断はできても、決断しない人が多い
医療・介護現場では、問題点を見極め、一定の判断は下しているものの、
・その実行を他者に委ねる
・上層部の指示を待つ
・あるいは決断自体を先送りにする
といった「決断回避」の傾向が散見される。
たとえば、「連携が不足している」「看護部門の協力が得られない」「経営陣が現場を理解していない」といった声はよく聞かれる。
しかし、これらの問題について「では、あなたは何を決断するのか?」と問うと、
「決断すべきことは特にありません。ただ、現状に不満があります」と返されることが多い。
決断を避ける者に成長はない
このような姿勢は、変化を起こす機会を自ら手放しているに等しい。
判断しかせず、決断を下さない人材には、以下の特徴がある。
-
責任を取ることを避ける
-
現状維持を好み、変化を恐れる
-
自らの意志を示さず、他者の評価に依存する
結果として、キャリアは停滞し、収入は上がらず、組織内での存在感も薄れていく。
極端に言えば、企業の“永続的労働力”として使われ続けるだけの存在となる。
チーム医療・介護の誤解
多職種連携が叫ばれる中、「チーム医療」や「チーム介護」を、単なる「情報共有の場」だと誤認しているケースは少なくない。
しかし、真に機能するチームとは、判断を持ち寄る場ではなく、決断に向けた意思を統合する場である。
単なる意見交換に終始していては、何も動かない。
チームの本質は、
-
各職種が責任ある決断を持ち寄り
-
それをぶつけ合い、
-
実行可能な方向へまとめていく
という意思決定のプロセスにある。
判断のみに長けたチームに価値はない。
価値を生むのは、決断と行動である。
決断こそが現実を変える
判断は出発点にすぎない。
決断して初めて、物事は動き出す。
判断と決断を混同している限り、仕事は「理解しているが、変わらない」ものとなる。
だが、覚悟を持って決断すれば、現場の景色は確実に変わっていく。
いま、医療・介護現場に求められているのは
判断者ではなく、決断者である。
筆者
高木綾一
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
三学会合同呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
国家資格キャリアコンサルタント
株式会社Work Shift代表取締役
関西医療大学 保健医療学部 客員准教授
医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。
医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。
著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。
経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。