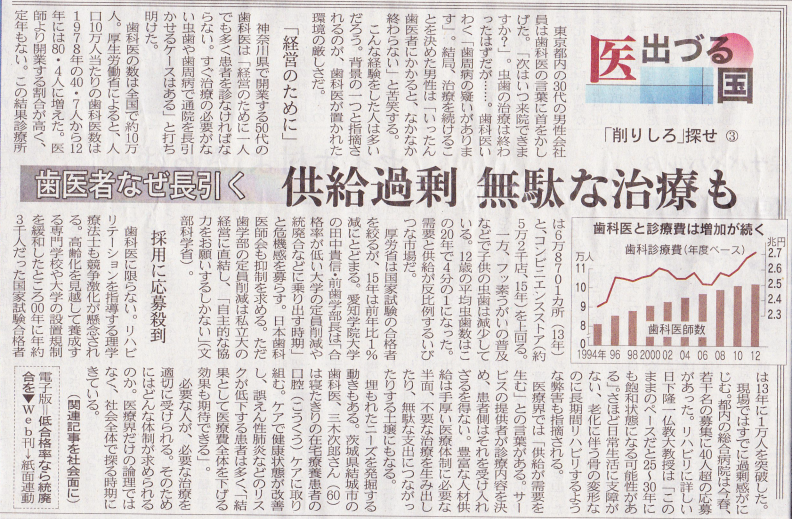地域包括ケアシステムの構築、急性期病床の削減、介護保険制度の変化、理学療法士の過剰供給に関する新聞報道・・・・。リハビリテーション職種を取り巻く環境の変化は著しい。
これらのことを受けて、本ブログだけでなく様々なセラピストが今後の療法士の働き方や生き方について言及している。数多くのセラピストが自らの働き方や生き方に大きなパラダイムシフトが生じることに気づきだしたと言える。
パラダイムシフトとは、「その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化すること 」である。まさに、リハビリテーションを取り巻く環境はパラダイムシフトの真っ只中である。
視点を変えれば、パラダイムシフトに合わせて自らの仕事や生き方を確立することができれば、相当なセラピストとしての充実感を得られる時代になったと言える。セラピストとして、仕事や生き方を確立していくための重要な要素は「理念」と「行動」のバランスである。
多くのセラピストは「理念の罠」にはまり込む。自分の働き方や行き方の「理念」ばかりを考え、素晴らしい理念や行動規範を考え、導き出す。ここまでは良いのだが、それをブログやSNSで披露したり、友人に話すことで満足してしまい、実際の行動は何一つ起こさない。
リハビリテーションやヘルスケア産業にはチャンスが渦巻いている。地域包括ケアシステムの一員として機能すること、高度急性期で活躍できるセラピストになること、高齢労働者の支援サービスを提供すること、二次予防事業に関与できる人材になること、在宅重症患者に対応できる人材になること・・・・・・・・・・など、チャンスに溢れている。
これらのチャンスは、「高承な理念」を振りかざしても、掴むことはできない。「高承な理念」を「具体的な行動」に転換することができた者だけが、チャンスをつかむ。
具体的な行動の方法は沢山ある。情報を持っている人と会う、休みの日を使ってやりたい活動を体験してみる、非常勤で働いてみる、職場で新しい企画を提案してみる、勉強会を開催してみる・・などで、チャンスの芽を掴むことはすぐにでも可能である。チャンスの芽を掴むことができなければ、芽を育てながら、働き方や生き方を確立することは不可能となる。
理念先行・行動不足型セラピストでは、このパラダイムシフトを乗り越えることはできない。