2017年1月19日の日本経済新聞にて「イオンが高齢者向けに小型の簡易フィットネスジムの多店舗展開を始める」と報道された。
記事によると、健康機器大手のタニタと提携し、同社の健康プログラムを活用するとのことである。
また、本格的な筋力トレーニング等の機器を配置するのではなく、交流を重視し、店舗の大半は飲食や休憩スペースに充てるとのことである。
セントラルスポーツ、東急スポーツオアシス、ルネサンスなどのフィットネスクラブ大手もシニア向けジムのサービスを拡充させており、フィットネス市場はシニアの取り込みに本格的に取り組んでいる。
フィットネス業界が高齢者向けサービスを拡充していることには、それ相応の理由がある。
大きな理由は、「地域包括ケアシステムにおける自助の推進」である。
現在、軽度者向けサービスとして、日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が推進されている。
現在のところ、通所介護と訪問介護を利用している要支援1.2の方は、介護保険を用いたサービスから、2017年4月以降は市町村が運営・管理する総合事業が提供するサービスに移行することになる。
この総合事業は要支援者の受け皿として考えられているが、実は厚労省はもう一段高い次元の介護予防に関する仕組みを実現したいと考えている。
厚生労働省が出した「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」には次のように記載されている(下図)。
総合事業は市場において提供されるサービスでは満たされないニーズに対応するものであることから、市場における民間サービス(総合事業の枠外のサービス)を積極的に活用していくことが重要である。
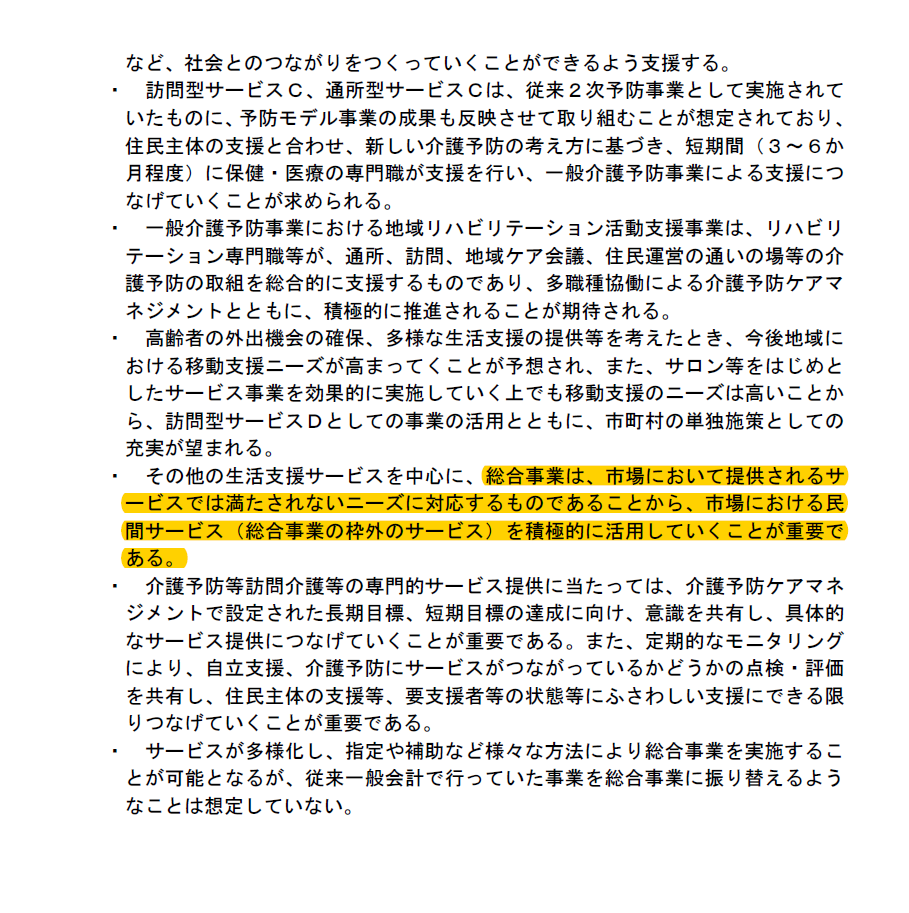 つまり、総合事業は民間サービスを補完するものであり、民間サービスを利用した自助活動が前提条件ということである。
つまり、総合事業は民間サービスを補完するものであり、民間サービスを利用した自助活動が前提条件ということである。
特に、民間サービスが潤沢な都会においては総合事業ありきではなく、民間サービスありきと厚生労働省は考えている。
総合事業は民間サービスではフォローできないサービスを受けたい人や民間サービスを購入することが出来ない人の受け皿として機能する可能性が高い。
しかし、総合事業は事業として成立することが難しい料金設定であることを考えると、質の高いサービスを成立させることが難しいかもしれない。
民間サービスが潤沢な地域と、潤沢ではない地域では、市町村の判断で総合事業の在り方も大きく変わる。
いずれにせよ、民間の高齢者向けサービスは国を挙げて推進されていく。
公的保険に頼っていた予防医学や介護予防、生活支援が民間サービスにシフトしていくのは間違いないだろう。
民間サービスの開発や提供に携わる医療・介護関係者の活躍も今後期待される。








