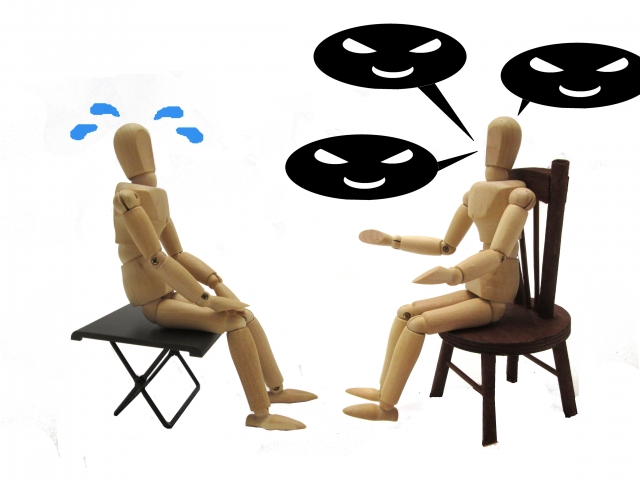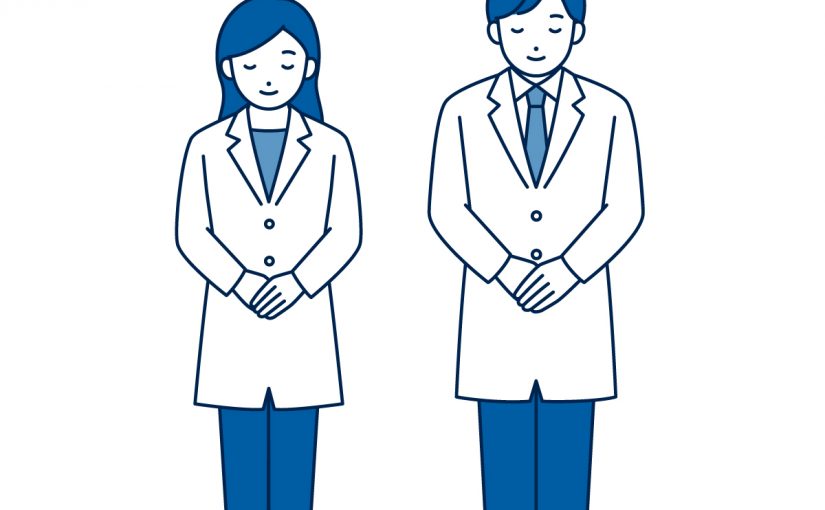リハビリ職種においていわゆる「職人肌」の人が管理職に向かない確率が100%に近い。
臨床は熱心なのに、管理業務は稚拙・無関心である。
なぜ、こんなことになるのか?
次のようなことが原因と考えられる。
1. マネジメントと専門技術の違い
職人肌の人は、自分の技術や知識を極めることに価値を見出しやすく、臨床に強いこだわりを持つ。
しかし、管理職の役割は「組織を運営し、チームをまとめ、成果を最大化すること」であり、個人の技術力とは異なるスキルが求められる。
個人からチームへ関心を向けることが難しいという根本的な問題を抱えている。
2. チームワークの軽視
職人肌の人は、自分のやり方にこだわりが強く、「自分が正しい」という意識が強い。
そのため、チームメンバーの意見を聞かず、一方的に指示を出したり、部下のやり方に不満を持ったりする。
リハビリテーションは多職種が連携して利用者にケア・リハビリテーションを提供する場なので、コミュニケーション不足や協調性の欠如は大きな問題になる。
3. 業務の属人化と育成の難しさ
「自分のやり方がベスト」と考える職人肌の人は、標準化された業務プロセスを作るのが苦手である。
標準化された業務がないため、部下が成長する機会を奪ったり、管理職本人が不在になると業務が滞ったりするリスクが生じる。
4. 視野の狭さと経営視点の欠如
職人肌の人は、臨床の細部にこだわるあまり、組織全体の利益や経営的な視点を持ちにくい。
リハビリテーション部門の管理職には、患者の満足度だけでなく、コスト管理、人材確保、業務効率化などの視点が求められるため、「良い臨床を提供すること」だけは、組織運営が困難となる。
職人肌を管理職にしないためには、専門職と管理職の複線型のキャリアパスを運用することが効果的である。
専門職コースの設置:技術や技能を極める「スペシャリスト」
管理職としてチームを率いる「マネージャー」
の2つキャリアパスを明確にすることが大切である。
管理職に向いていない職人肌の人を無理に昇進させると、本人も周囲も苦しくなる。
「管理職にならないと出世できない」という風潮をなくし、専門職として活躍できる道を整備することも重要である。
投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術・経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授