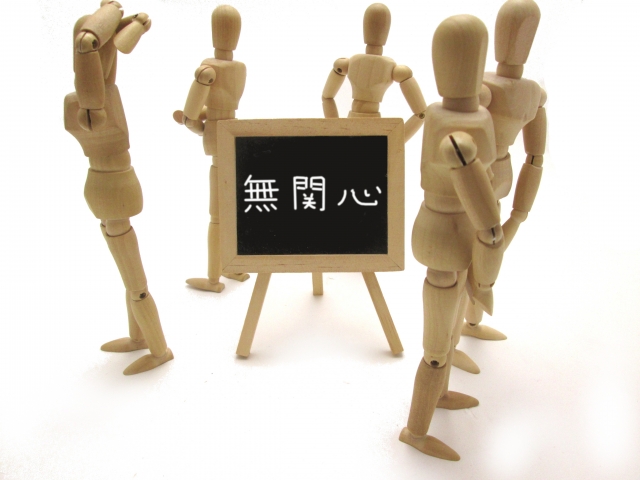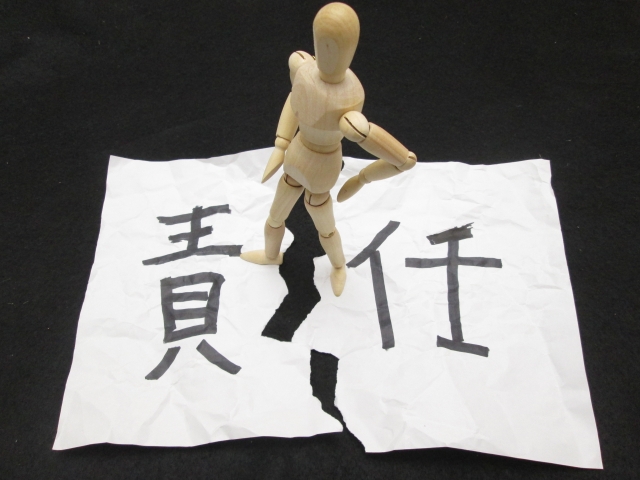急性期・回復期・生活期の全ての領域において、利用者の高齢化が進展している。
そのため、セラピストが対応しなければならない範囲が拡大している。
医療保険や介護保険においてリハビリテーション部門が必要となった原因疾患が脳卒中や大腿骨頸部骨折などの運動器疾患であっても、ほとんどの利用者が既往歴として内科系疾患を有している。
そのため、リハビリテーションの実施中に内科系疾患が原因となるトラブルが起こることがしばしばである(下図)。
関節可動域練習や筋力強化練習時の痛みの管理
立位・歩行練習時の転倒リスクの管理
などを行っている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士はいるが、平素から内科系疾患の管理を根拠をもって行っている人は少ない。
なぜならば、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は内科系疾患について学ぶ機会が圧倒的に不足しているためである。
卒前・卒後においても、主に脳血管疾患と運動器疾患に関する学びが多く、内科系疾患に関する学びは、特別講義などの機会に学ぶ程度である。
また、内科系疾患の管理は医師や看護師の仕事と考えている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も多いのも否定できない。
利用者が飲んでいる薬や受診状況なども把握していない人もいる。
しかし、高齢化が進展するリハビリテーションの現場では、内科系疾患の知識不足はセラピストの落とし穴になる。
これからのセラピストは内科系疾患の知識を高める努力を怠ってはならない。
投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)
関西医療大学保健医療学部 助教
関西学院大学大学院 経営戦略研究科
イラスト提供
福山真樹
理学療法士×イラストレーター
医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。
臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。
問い合わせ先
Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT
メール big.tree.of.truth@gmail.com
Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama
Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama