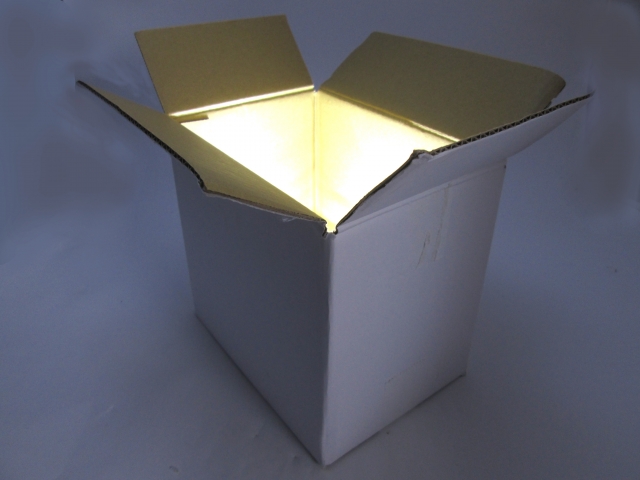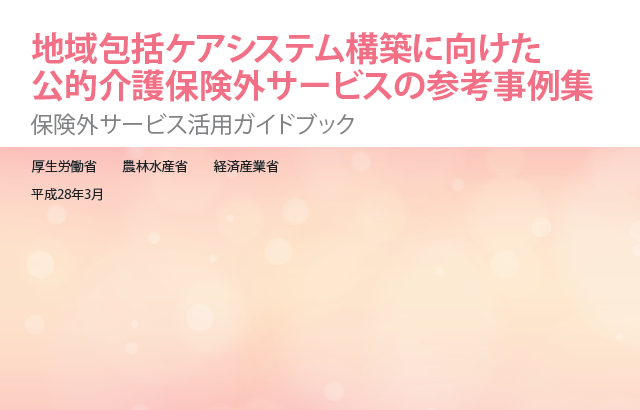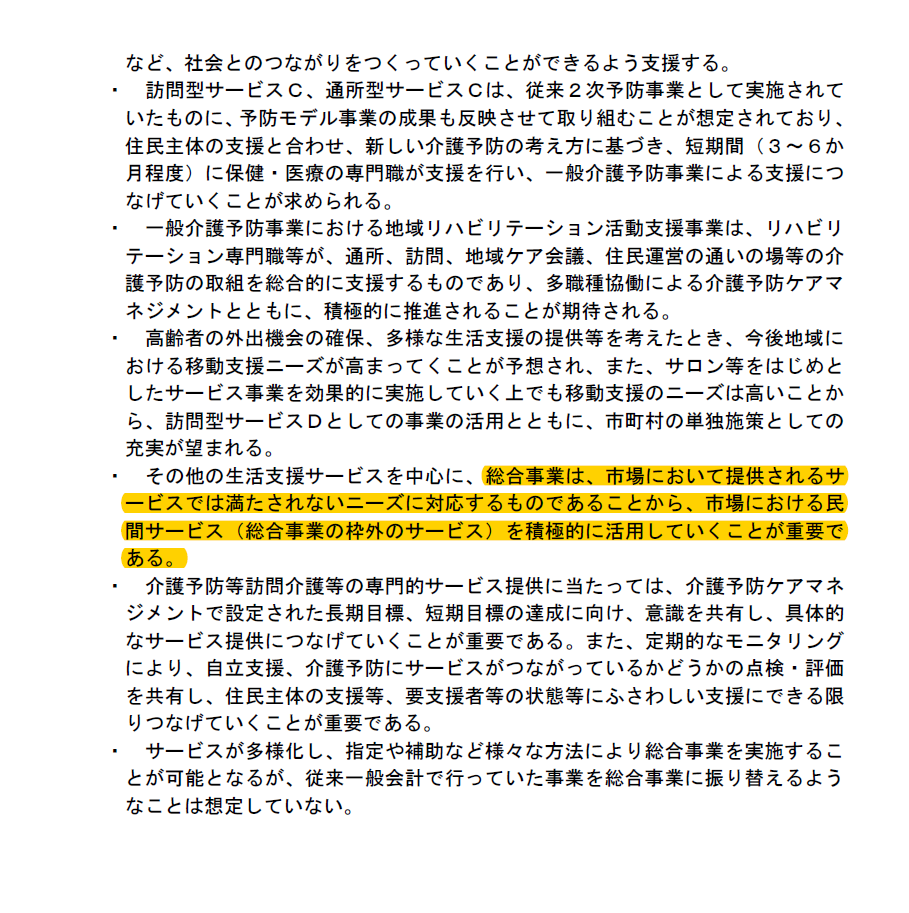理学療法士、作業療法士、看護師の働き方や生き方が多様化している。
多様化の象徴としてわかりやすいのは、異業種交流会や多職種連携会などに積極的に参加する理学療法士、作業療法士、看護師などの医療介護従事者が年々増加していることだ。
医療介護従事者が自分が働く医療や介護の現場だけでなく、外にコミュニケーションを求めるようになったのはここ10年ぐらいの出来事だろう。
異業種交流会等のイベント参加者の多くは人脈形成や仕事の依頼などを目的としている。
しかし、ほとんどの参加者は名刺ばかりが増えて、仕事の依頼ばかりか、人脈形成すらままならないのが現実だ。
実は、人脈形成や仕事の依頼にはある法則がある。
「自分のスペック以上の人脈形成や仕事の依頼は成立しない」という法則である。
簡単に言うと、職業能力や市場における価値が乏しい状況で、異業種交流会などの交流イベントに参加しても、本人が期待するような人脈形成や仕事の依頼は生じないということである。
せいぜい、自分のスペック以下の人物からのお付き合いや仕事の依頼の申し込みがあるだけである。
逆に言うと、自身のスペックが高ければ高いほど、能力の高い人と人脈を形成することができ、それが仕事につながっていく。
自分自身の自立ができていない状況で、異業種交流会などのイベントに参加すると「自立していない人」との人脈形成が進んでいくという悲惨な結果となる。
また、異業種交流会や多職連携会などは以下のデメリットのほうが多い。
①仕事を取りに来る人の集まりなので打算的な会話が多く、長期的な実利にはつながらない
②打算的な人ばかりの集まりなので、キャリア、経営、運営について学ぶことも乏しい
③ネットワーク商法の誘いが多く、対応が面倒くさい
したがって、異業種交流会や多職種連携会を長期的に実利のあるものにするためには、まずは自分自身のスペックを上げることが重要である。
むしろ、スペックを上げていれば、異業種交流会などのイベントに参加しなくても、様々な人からお付き合いや仕事の依頼が舞い込んでくる。
いずれにしても、まずは自分のスペックを上げることが最重要である。