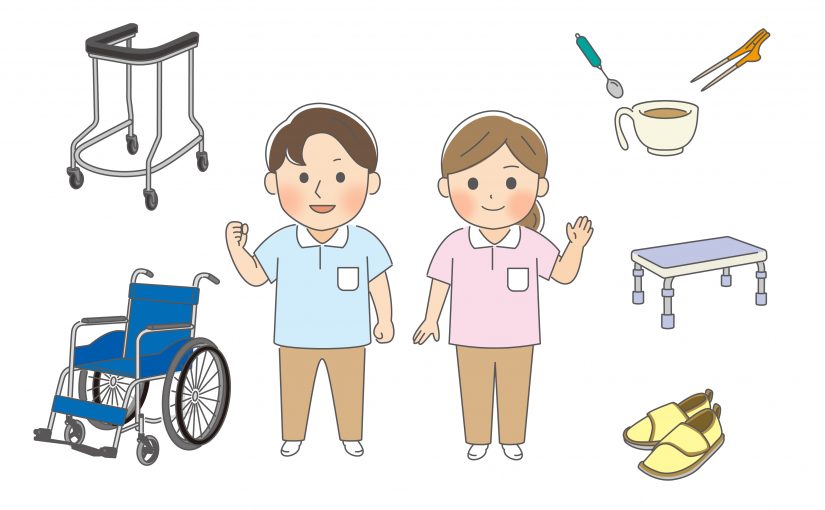2024年度の診療報酬・介護報酬のダブル改定を経て、医療・介護の政策トレンドは、より一層「在宅復帰支援」および「在宅生活継続支援」へと大きく舵を切ったといえる。
在宅生活の継続を困難にする要因は依然として明確であり、それは病状の急変やADLの低下による家族の介護負担の増加に起因する。
すなわち、在宅復帰後のフェーズにおいては、病状の安定化およびADLの維持・向上に対して、切れ目のない支援と専門的な介入が求められている。
回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟においては、医師、看護師、セラピスト、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士など多職種が一つのエリアに集い、物理的にも心理的にも距離の近い環境で業務を遂行している。
このような環境下では、情報の即時共有が可能であり、チーム内での知識・経験のナレッジシェアも容易であることから、患者ごとの個別ケアやリハビリテーションプログラムの質は総じて高くなりやすい。
一方、在宅医療・介護の現場においては、以下のような構造的な問題が依然として存在している。
-
各職種が物理的に離れており、リアルタイムの情報共有が困難である点
-
他事業所の主治医や看護師、セラピストなどが連携しながら一人の利用者に関わるため、責任と情報の分散が生じる点
-
各事業所がケアやリハビリテーションに対して共通の理念や価値観を持たない場合が多く、方針が統一されにくい点
-
そもそも急性期や回復期から十分な情報が引き継がれにくく、支援のスタート時点で不確実性が高い点
これらはすべて、質の高い個別ケアやリハビリテーションの提供を阻害する要因である。
現在、国は「地域包括ケアシステム」の進化形として、医療機関をあくまでバックアップとし、大多数の国民が住み慣れた地域・自宅で生活し続けるための仕組みづくりを急速に進めている。
しかし、在宅生活を支える在宅医療・介護のインフラに関しては、ハード面(設備や制度)に加え、ソフト面(人材や連携体制)の整備が追いついていない現状がある。
病院や施設においてもチーム医療・介護の実現には課題が多いが、在宅においては物理的・心理的な距離の広がりがこれに拍車をかけており、チーム医療・介護の実践はより一層困難となっている。
この複雑な課題に対する一つの有効なアプローチがある。
それは、「専門性を確立した上で、他職種や他領域の知識・技術を部分的にでも理解し、実践に活かせるハイブリッド型人材の育成」である。
すなわち、自己の専門性を軸にしつつ、関連領域の知識を横断的に習得することで、チーム内での連携コスト(時間的・心理的)を削減し、組織的・地域的な連携の円滑化が図れるのである。
ここで重要なのは、「まずは専門性を確立すること」が前提であるという点である。
自身の専門分野が曖昧なまま周辺知識を広げても、それらを有機的に統合することは難しく、結果としてサービスの質が上がらないリスクが高い。
たとえば、脳卒中リハビリテーションに長けたリハビリ職種が薬剤に関する基本的な知識を有していれば、向精神薬による副作用(動悸、高揚感など)と脳卒中の症状との鑑別において、早期に異常に気づき、リスクマネジメントにつなげることが可能となる。
このように、ポジティブに診療報酬・介護報酬改定を捉えるのであれば、医療・介護従事者のキャリアにはこれまで以上に多様な可能性が開かれている時代に入ったと言える。
筆者
高木綾一
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
三学会合同呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
国家資格キャリアコンサルタント
株式会社Work Shift代表取締役
関西医療大学 保健医療学部 客員准教授
医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。
医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。
著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。
経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。