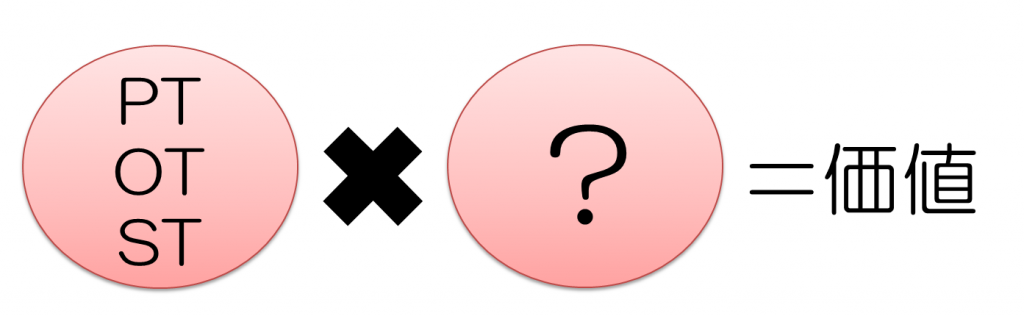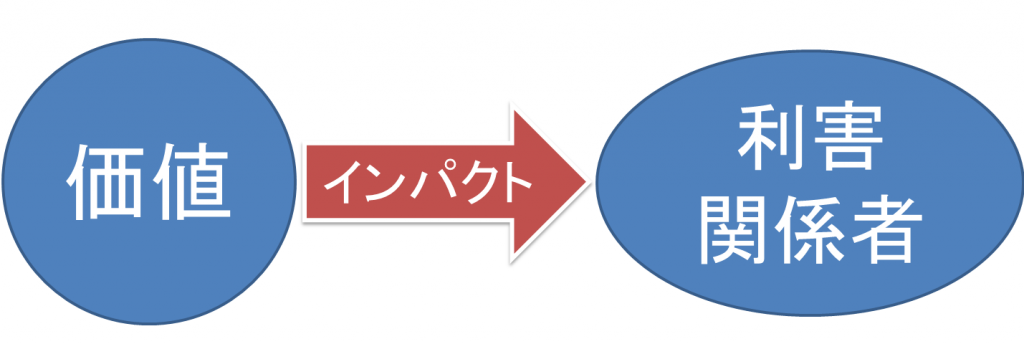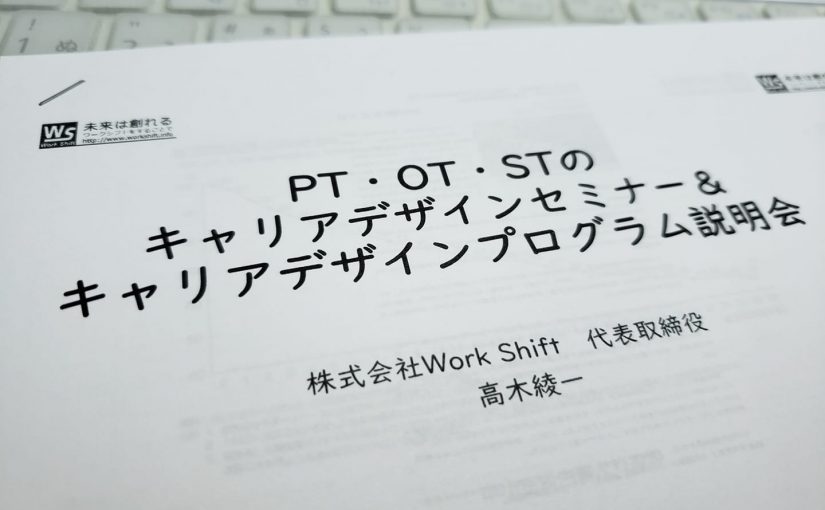今の仕事がしんどい 今の仕事を辞めたい
今の職場が嫌だ 今の上司が嫌いだ
こんなことをつぶやきながら働き続けている理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は多い。
まるで、奴隷のように働いている。
言い換えれば、やりたくもない仕事に人生を支配されているのだ。
このような状況の人は180度、仕事に対する考え方を変えたほうが良い。
仕事は自分自身を表すツールであり、あくまでも人生を豊かにする道具である。 
仕事が人生を支配するのではなく、人生が仕事を支配しなければならない。
そのためには、自分らしい人生を歩むことが最重要課題となる。
人生においては自分の興味・能力・価値観を理解することが重要であり、それらを満たす職業や職場にたどり着くことが求められる
・自分はどんな仕事をしたいのか
・自分はどんな仕事ができるのか
・自分は仕事において何を大事にしたいのか
これらのことを大切に日々の人生を歩まなければ、不満に満ち溢れた仕事をやり続けることになる。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士という資格は人生のツールでしかない。
自分自身がどのような人生を歩みたいかを決め、これらの資格を用いて人生をデザインすることが重要だ。
市場の労働環境や社会情勢の変化が激しい現代において、自分自身の人生を深く考えなければ、環境の奴隷となることは間違いない。
自分自身の気持ちや考えを抑えつけて、ひたすら働く。
こんな働き方はいつまでも続くものではない。
あなたの仕事はあなた自身の思いや考えを表現できていますか?
今一度考えてほしい。
執筆者
高木綾一  株式会社WorkShift 代表取締役
株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)(経営管理学)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授