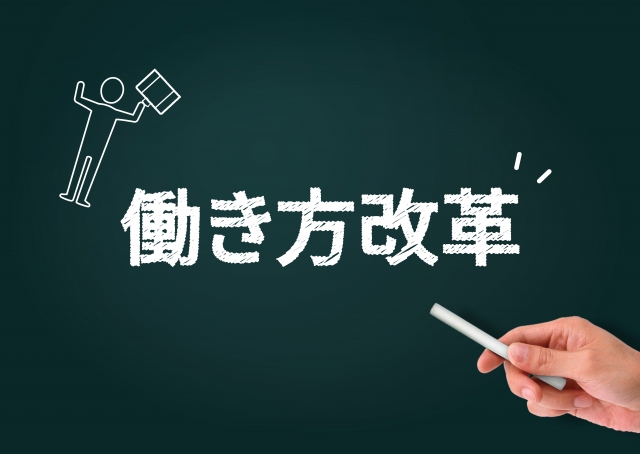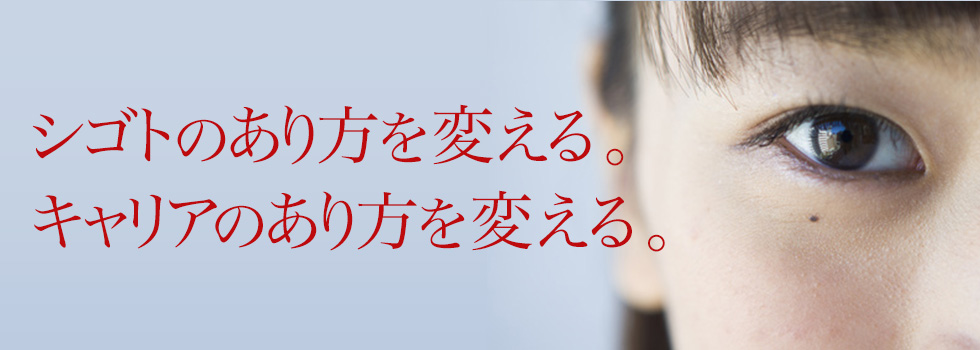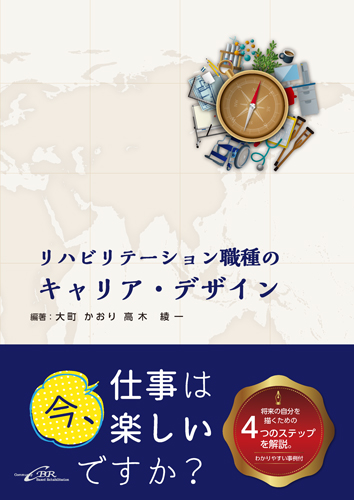全国各地の医療機関・介護事業所にて働き方改革が叫ばれている。
残業時間を短くする
ダブルワークを行う
育児や介護と仕事を両立する
ITを活用した仕事をする
などの働き方の変革を実践する組織やセラピストが増えている。
しかし、あえて言う。
働き方改革は手段であって、目的ではない。
ほとんどの組織や人が、「働き方を改革すること」だけを目的として行動している。
確かに、働き方を改革するのことはなんとなく「かっこいい」。
しかし、働き方の改革は「かっこいい」から行うのではない。
本当の目的は「あるべきキャリアの実践」である。
どんな自分になりたいのか?
どんなアイデンティティーを確立したいのか?
どんな仕事を実践したいのか?
これらを明確にした結果、「働き方改革」が生じるのである。
あるべきキャリアの実践を不明確なまま、「働き方改革」を実践しても継続した活動にならない。
なぜならば、人間は自分の心から望むこと以外のことを継続することが難しいからだ。
なぜ、ダブルワークをするのか?
なぜ、残業を少なくして早く帰宅するのか?
なぜ、新しい資格を取るために勤務時間を調整するのか?
この「なぜ」を追求しない限り、働き方改革は無意味に終わる。
あなたやあなたの所属する組織は、なぜ、働き方改革をしているのか?
今一度考えてほしい。
株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学 客員准教授