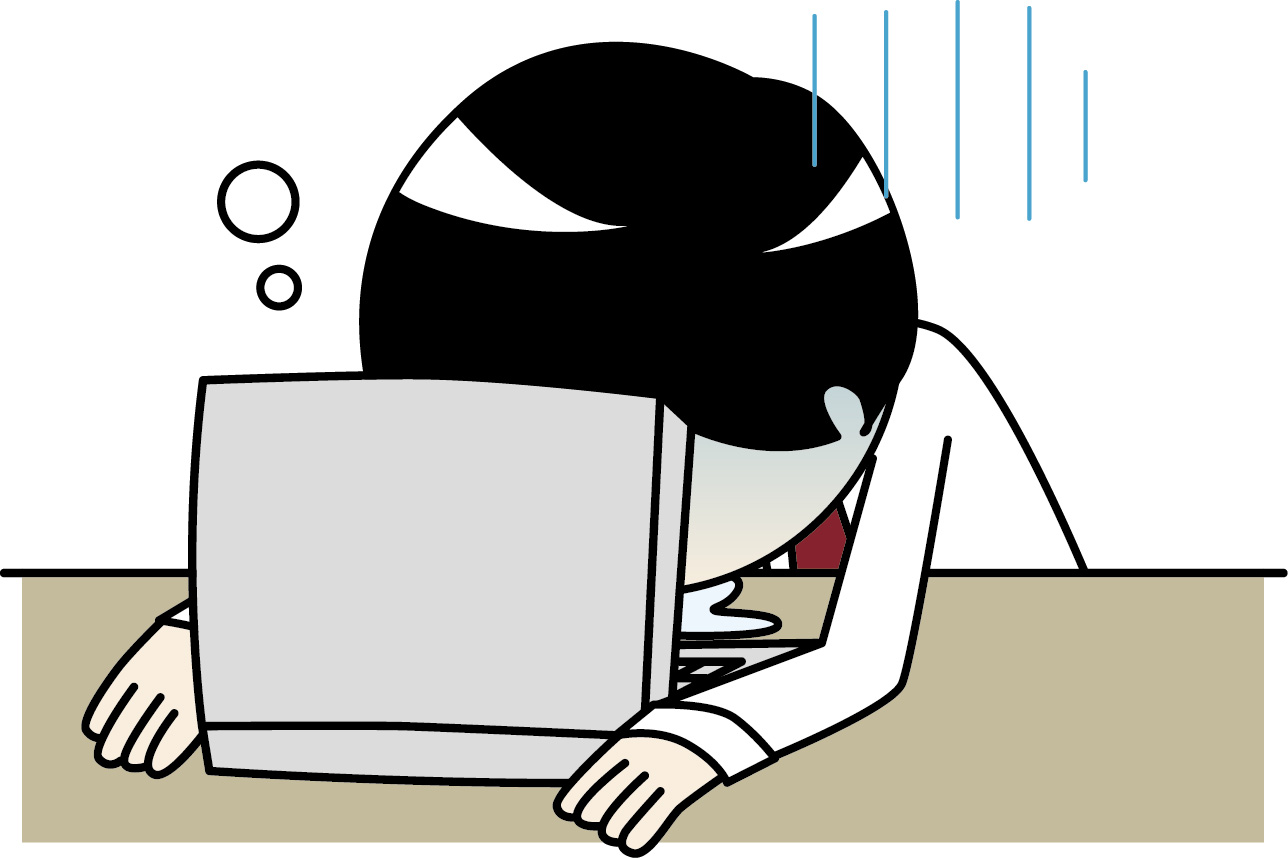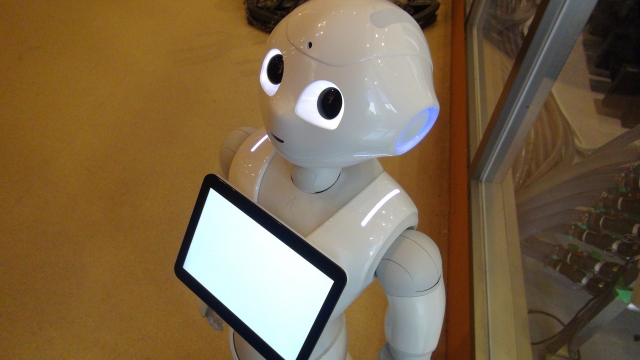現在、医療・介護分野において人工知能(AI)、ロボット、情報通信技術(ICT)の導入が進んでいる。
政府は、AI・ロボット・ICTを推進することで将来の労働者減少に対応したいと考えている。
そのため、官民一体となりAI・ロボット・ICTの開発と導入が行われている。
リハビリテーション分野でも、歩行支援ロボット、トランスファー支援ロボット、運動支援ツール、スマートフォンのアプリを用いた動作解析やリスク管理、見守り支援システムなどが導入され、徐々に市場に広がりつつある。
近い将来、リハビリテーション分野で働く大部分の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、AI・ロボット・ICTに仕事を奪われ、自らの仕事を失うのではないかとの懸念がある。
確かに今後30年や50年というスパンで考えれば、テクノロジーは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の仕事を奪う可能性はあるだろう。
特に、現在、20代前半の若いセラピストはテクノロジーがかなり進んだ未来の世界で、仕事をすることになるため、テクノロジーに食われないスキルを磨く必要があるだろう。

それではAI・ロボット・ICTに負けないセラピストのスキルはどのようなものだろうか?
筆者は以下の5つのスキル・能力に関してはAI・ロボット・ICTがセラピストを凌駕することは難しいと考えている。
1)局所アライメントの評価技術
現在、三次元動作解析機・動作分析アプリ・歩行支援ロボットなどがリハビリテーション分野で応用されている。これらは、患者や利用者の動作分析、関節運動の補助を行うものであるが、動作分析や関節運動の補助ができるのは股関節・膝関節・足関節の大関節のみで、足部、膝関節、肩関節、脊柱、手根部などの細かい骨のアライメントを捉えたり、アライメントのコントロールすることは不可能である。
例えば、足部アーチや足関節の関節可動域制限を目的とした足根骨のアライメントを調整するような非常に複雑で緻密な評価や手技はロボットには不可能だろう。
運動学や解剖学に基づくアライメントコントロールの手技に関しては、テクノロジーが追いつくことが難しいと考える。現に、マッサージチェアーがセラピストの徒手療法を凌駕することは、未だできていない。
2)患者・利用者の個別的背景を踏まえたリハビリテーションやケアの立案
患者や利用者の生活を取り巻く背景は年々複雑化している。
老々介護、貧困世帯、介護力低下、生活保護、認知症、虐待等の問題が、複雑に交錯し、高齢者の生活の自立を困難にしている。
複雑な問題を抱える患者や利用者へのリハビリテーションの介入はAIやロボットを用いても、根本的な解決はできない。
患者や利用者の生活背景は多種多様であることに加え、リハビリテーションやケアの在り方には患者、利用者、家族の価値観も強く影響する。個別的な背景を踏まえたリハビリテーションの支援は人間的な感性が非常に要求される部分であり、論理的な計算で答えを出すことはできないものである。
3)事業の立ち上げや事業を運営すること
地域包括ケアシステムが推進される社会では、自助や互助の領域における様々な事業の創出が期待されている。事業の立ち上げや運営では、コンセプトの設定、人材の確保や教育、運営手順の確率、ビジネスパートナーとの提携などが必要である。これらのことは、人間にしかできない。
事業を行うためには、情熱、熱意、感動、怒りなどのきわめて情緒な感情に基づくモチベーションが必要である。よって、事業の立ち上げ、運営は決してAIにはできない。
4)AI・ロボット・ICTを使用すること
発想を変えてAI・ロボット・ICTを完全に使いこなすことができるセラピストになれば、職を奪われることはない。例えば、歩行支援ロボットといっても様々な種類があり、これからも多くのものが発売されるだろう。それぞれのロボットには、そのロボットに適した患者や身体条件があることから、患者や利用者の適正な評価を行ったうえでロボットを選定するということもセラピストの仕事として成り立つ。
また、リハビリテーションプログラムの立案するために様々なデータとAIを用いて、プログラムを決定することもセラピストの仕事になるだろう。AIが導き出したプログラムが道義的にも患者や利用者のニーズの観点からも有用性があるかについては、セラピストにしか判断できないだろう。
5)複雑で多様な動作パータンを呈する動作のリハビリテーション
更衣動作、入浴動作、調理動作、手作業などの動作は様々なバリエーションに富んでおり、また、細かい関節運動が必要なものが多い。例えば、手作業であれば手関節や手根骨などの動きが必要である。
特に、生活関連動作バリエーションが多く、かつ、小さい関節の動きが必要な動作が多いため、ロボットを用いて治療を行うことは難しいだろう。
AI・ロボット・ICTは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と対立するものではなく、共存共栄していくものである。
その共存共栄は人間にしかできない技術領域を確立することによって、達成できるだろう。
テクノロジーの進化だけでなく、セラピストの進化が同時に求められている。