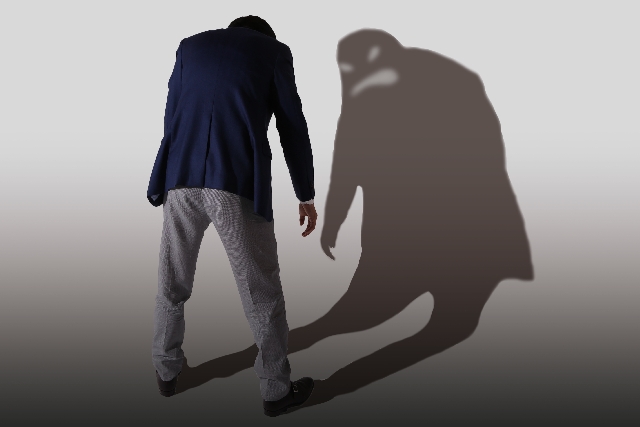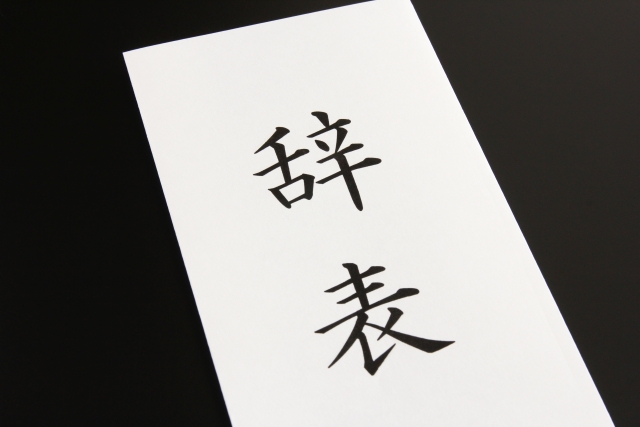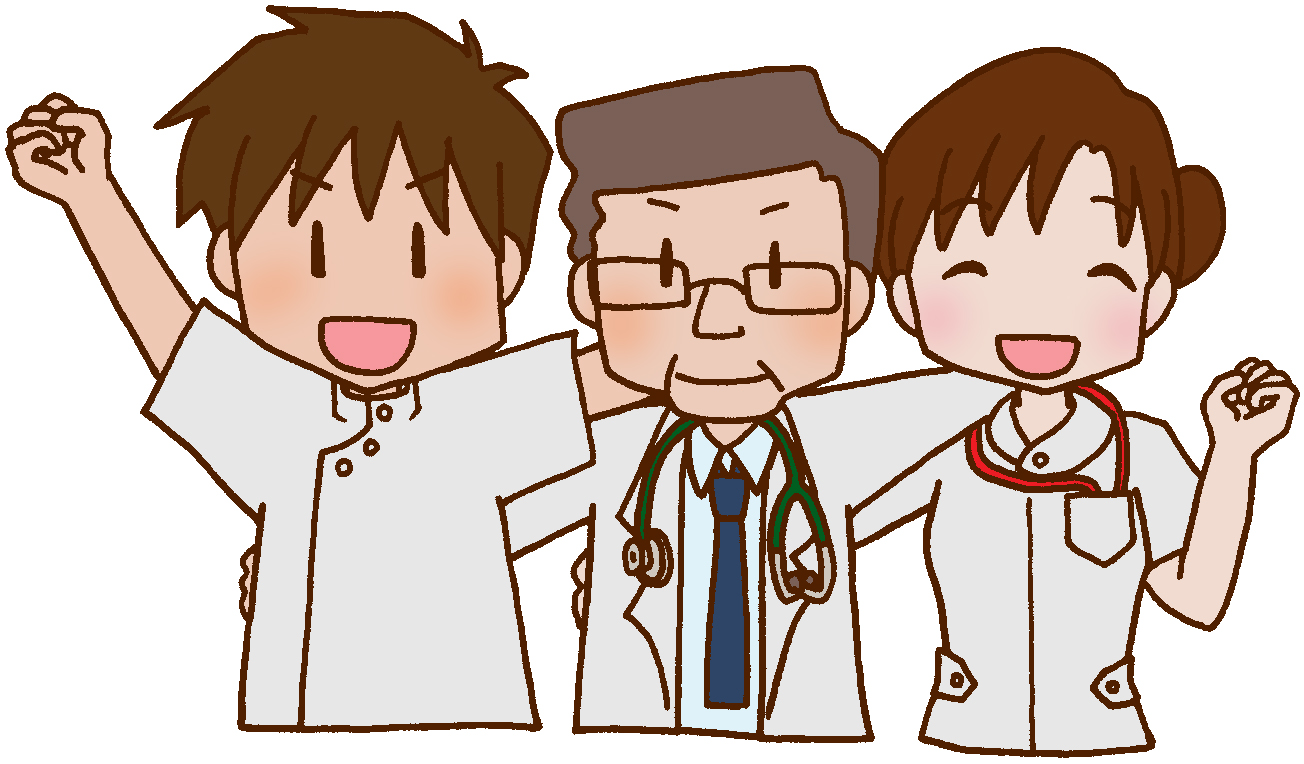フリーライダー
組織においてメンバー同士の貢献によって付加価値を産み出すとき、何も貢献せず、他のメンバーに貢献に依存し得られた付加価値の恩恵にはあずかる人、ただ乗りの人。
わかりやすく言うと、「給料泥棒」である。
ご存知の通り、診療報酬・介護報酬の体系はより厳しくなっており、生産性の高い働き方を実行できる集団でなければ、安定的な利益を確保することは難しくなっている。
生産性を高めるには
投資する時間や費用を少なくしても、成果には変化がないこと
もしくは、
投資する時間や費用は変化がないが、成果が大きく変化すること
が必要である。
すなわち、時間や給与あたりの成果が大きい人が生産性が高い人と言える。
次のような人がいる職場は、生産性の観点から考えると最悪である。
大した実力もないのに肩書だけの上司が指示ばかり出して、自分自身ではなんら仕事の成果を出していない人
職場における仕事の責任を果たさずに、外部の仕事(セミナーや副業)などの仕事を職場に持ち込んでしている人
よくわからない経営者や院長の親族の人が月に数回だけ勤めて、えらく高い給与をもらっている人
毎日残業をして、残業代も高く、しかも普通の仕事の成果しか残せていない人
1分でわかる話を5分も10分もする人
同じ失敗を何度もする人
今までの診療報酬・介護報酬の体系では、生産性の低い人がいても最低限の利益率を維持することが出来ていた。
また、生産性の低い理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護職、看護師、医師も人手不足をアドバンテージにして、雇用されていた。
しかし、地域包括ケアシステム構築の最終コーナーを回っている昨今では、もはや生産性の低いに人間は不必要となってくる。
医療・介護現場は、まだまだ生産性が低い。
マネジメントレベルの低下
個々の職員の技術力
コミュケーションの不備
生産性への意識
ITの活用
など多くの課題の解決が先送りされている。
また、生産性の低い人を排除する仕組みも乏しい。
特に、経営者の知り合い、血縁関係者や立場の高い人のフリーライダーの排除をする力は乏しい。
あなたの組織にはフリーライダーを排除する考えや仕組みはありますか?
フリーライダーが増えれば増えるほど、組織崩壊は近い。