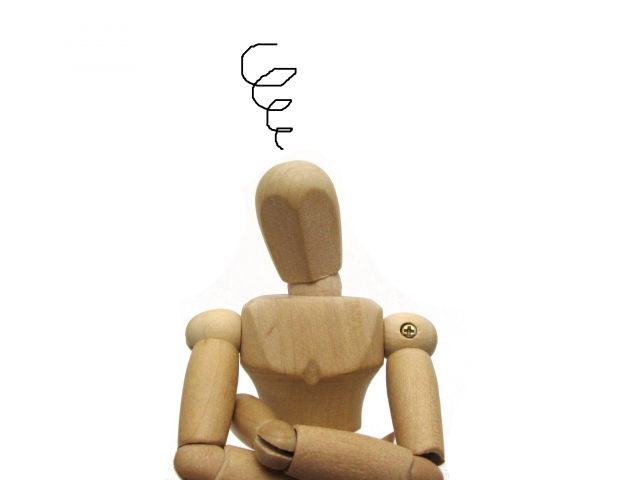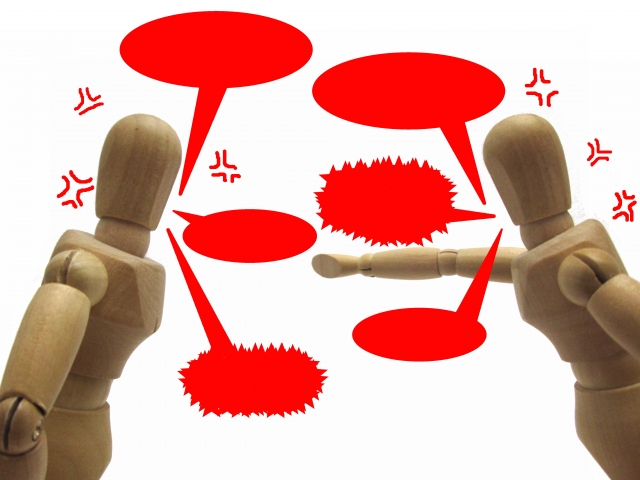リハビリテーション専門職の就業の流動性がどんどん高まっている。
回復期リハビリテーション病棟の単位数削減
地域包括ケア病棟のリハビリテーションの包括化
在宅リハビリテーションの推進
都心部ではリハビリテーション職の過剰供給
これらの問題により、以前と比較すると転職の機会がセラピストに増えており、生涯の転職が3回以上が当たり前になる時代になっている。
転職すると言うことは、自分が背負っていた勤め先の看板を入れ替えることである。
多くの人は、勤め先の看板でご飯を食べている。
セラピストが自身のマーケティングを通じて患者や利用者を増やすことはない。
医師や介護支援専門員からの依頼で仕事をいただいているだけである。

したがって、勤め先の看板がなければ仕事を成立しにくいと言っても過言ではない。
勤め先を変わると言うことは、勤め先の看板に甘えることにもなる。
しかし、それでは勤め先が支払える給与以上の対価を得ることは不可能に近い。
勤め先の看板を入れ替える機会が多いこれからの時代では、自分自身の名前でご飯が食べられるか?という視点が必要である。
みなさんも有名な理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を思い出してほしい。
その人の所属先でそのセラピストの能力を判断していることはないだろう。
その人の名前でその人の価値を想像しているだろう。
自分の名前で、相手に何を想像させることができるか?