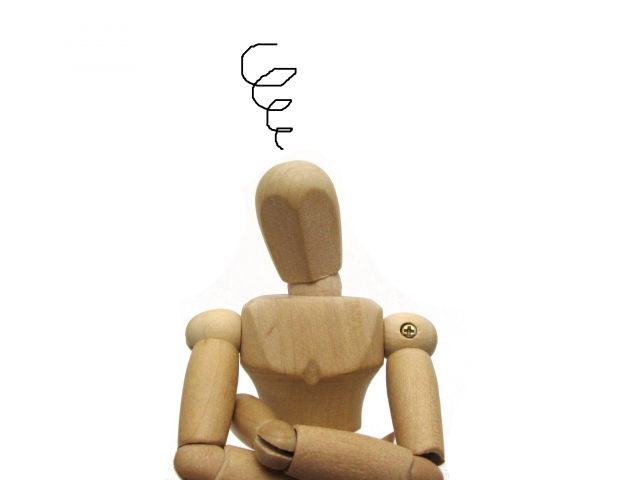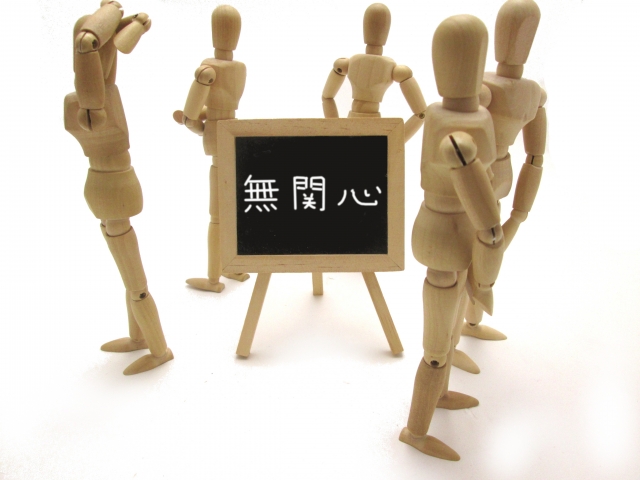リハビリテーション部門の最大の経営資源はセラピストであることは間違いない。
そのため、多くのリハビリテーション部門は人材育成に取り組んでいる。
しかし、人材育成が成功している事例を聞くことは少ない。
多くのリハビリテーション部門では、人材育成に関して次のような課題を有している。
3年目から5年目ぐらいで退職する
職場内の風紀を乱すセラピストがいる
セラピストの多くが管理職を希望しない
臨床能力が低いだけでなく、事故を良く起こす
人事異動に納得しないセラピストがいる
部下を扇動し、組織を乱すセラピストがいる
など・・・多くの人材に関する問題が散見する。
このような問題の収束や解決のために疲弊している管理職は多い。
しかしながら、このような問題の収束や解決は組織力のマイナスをゼロに戻すだけの作業であり、本来の管理職の仕事である組織力のプラスをよりプラスに変えるものではない。
したがって、人材に関する問題が極力生じないための組織マネジメントが必要となる。
そのために必要なのは、採用の入り口で徹底した人材の人選が重要である。
組織の理念、ビジョン、業務内容、役割、キャリア教育等に完全に納得、同意した人間を複数回の面接や試験などで厳選することが重要である。
人材を厳選する活動は大きなエネルギーが必要であるが、問題人材への対応に必要なエネルギーとは遥かに健全なエネルギーである。
問題社員に振り回される組織は採用活動の質が悪すぎるだけである。
あなたは、良い人材を採用するためのエネルギーと問題社員対応のエネルギーならどちらを選びますか?
執筆者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)
関西医療大学保健医療学部 助教
関西学院大学大学院 経営戦略研究科