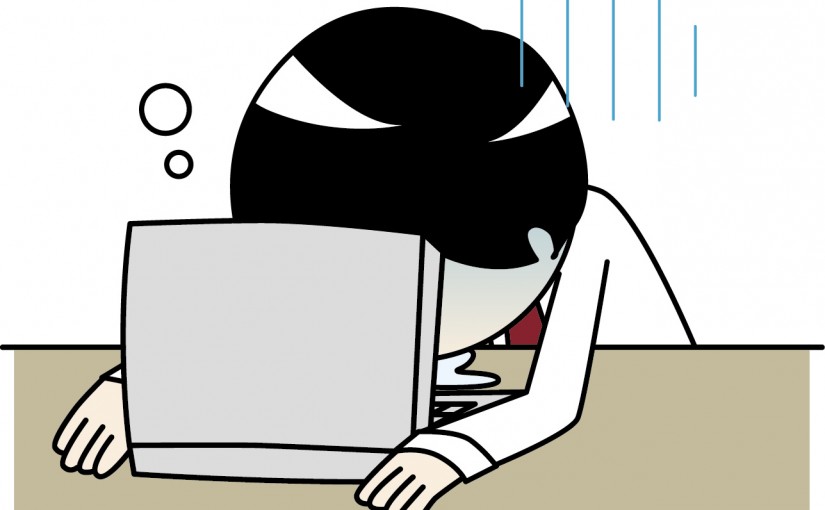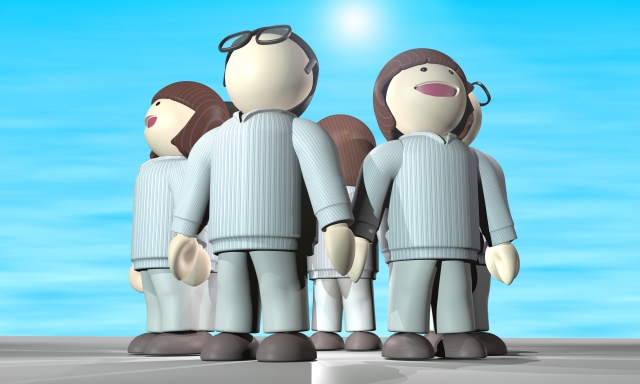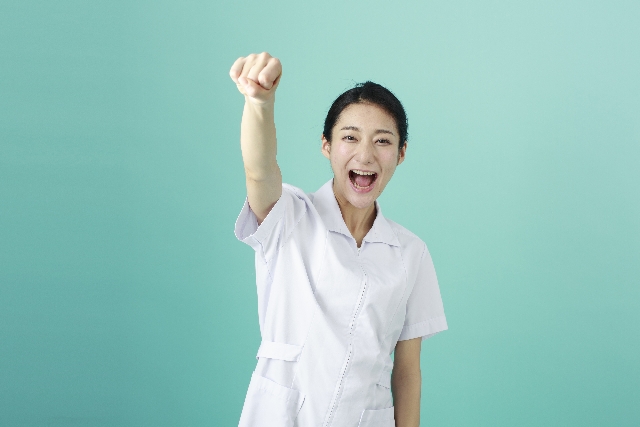診療報酬改定、介護報酬改定などの環境変化や事業所収益の低下が生じた時に、必ずと言って、取り沙汰されるものとして、「従業員への教育強化」がある。
接遇が悪いので接遇の教育をしよう
リハビリの質が悪いのでリハビリ部門の研修を強化しよう
介護職員の腰痛が多いので、移乗介助の研修をしよう
などが提案され、外部の研修に参加したり、内部より講師を選び研修が行われる。
研修にはコストがかかる。
外部研修では、参加コストや参加している時間の人件費コスト
内部研修では、会場の電気光熱コスト、講師の人件費コスト、参加者の人件費コスト、講師が研修に費やした時間コストなどが生じる
つまり、研修にコストがかかるということは、本来、研修には費用対効果、時間対効果が求められるということである。
費用対効果、時間対効果を別の表現で現すと、投資活動である。
投資とは「将来の資本を増加させるために、現在の資本を投じる活動」である。
つまり、研修を行うことで明確な資本の増加が必要である。
わかりやすく言うと、研修を行うことで、在院日数が低下する、褥瘡発生率が低下する、職員の離職が低下する、在宅復帰率が増加する、日当円が増加する、再入院率が低下する、稼働率が増加するなどの明確な効果が得られる必要がある。
果たして、多くの医療機関や介護事業所にて、行われている教育研修は資本を増加させているのだろうか?
リハビリテーション部門でよくある研修の形態は以下のものである。
1)セラピストが好きな内容の研修に自由に参加している
2)外部の先生を適当に招致して、研修会を開催している
3)セラピストが自主的に勉強会を開催している
4)研修費を支給して、外部の研修に参加させている
などである。
これらは果たして、医療機関や介護事業所の資本増加に寄与するものであるか?
筆者は多くの研修は無駄であると考えている。
投資効果を得るためには、自社の問題点を明確し、自社の理想と現実のギャップを埋める計画を立案し、その計画を実行するという極めて慎重な活動が必要である。
多くのリハビリテーション部門で行われている上記の研修形態は、計画に基づいた慎重な活動ではないし、自社の問題を中心に置いたものでもない。
多くの研修は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の個人の価値観やスキルを重視したものである。
セラピストや介護職に不足している技術や知識=自社の課題 にはならない
多くの事業所は研修を行うことが目的となっており、投資という本質的な目的を忘却している。
そのため、投資効果の低い研修ばかりを行っている。
企業がコストをかける以上、それは投資である。
研修は、あくまでも企業価値を上げるために存在しているのである。