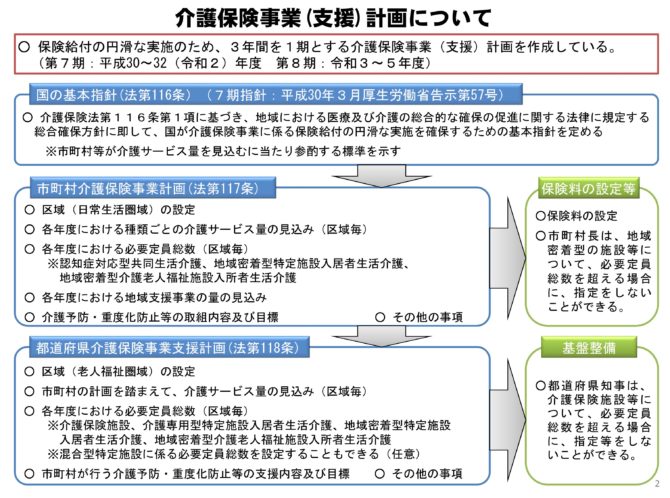変化の激しい時代では、計画したキャリアに固執することは避けたほうが良い。
なぜならば、自分のしたいことに固執をしてしまうと、時代の変化によって生じる様々な可能性を見捨てることになる。
したがって、自分のしたいことだけでなく、行動の幅を大きく持ち、様々なことにチャレンジすることにより生じる様々な可能性に出会うことが大切である。
これはスタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授は提唱したプランドハプスタンスセオリーの考え方である。
この理論の中核をなす考え方は、「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される」というものである。
自分の人生における出会いや出来事の中に自分の仕事や人生に大きな影響を与えるものを見つけて、それをキャリアに積極的に活かしていくという考え方である。
しかし、意味のある出会いや出来事は待っていても発生しない。 転機となる出会いや出来事と遭遇するためには、積極的に行動する必要がある。
例えば、研修会、交流会に参加することや、新しい資格を取得すること、新しい仕事に携わるなどの行動は、自分の人生に意味のある出会いや出来事を発生させる可能性が高い。
そこで、出会った人や生じた出来事は、偶然に発生したものであるが、自分が行動したことによって生じたものである。
そういう理由からこの理論は、プランドハプスタンス理論、すなわち、計画された偶発性理論と呼ばれる。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士として、目標が不明確なまま悶々と働いていても、キャリアの突破口は開けない。
そういった時は、とにかく、動くこと大切である。
図書館に行ってもいい
アルバイトをしてもいい
自然をみてもいい
昔の友人にあってもいい
研修会に参加してもいい  日頃の生活では、感じることが少ない感情の動きを起こす必要がある。
日頃の生活では、感じることが少ない感情の動きを起こす必要がある。
そうすることで、沸々と新しい意欲がわいてくる可能性がある。
プランドハプスタンスセオリーは、キャリアを発展させるためには「とにかく動くこと」が重要であることを示している。
今の仕事が面白くない やりたいことがみつからない 特に夢がない などと思っていても状況は少しも変わらない。
とにかく、「動く」。
これに尽きる。