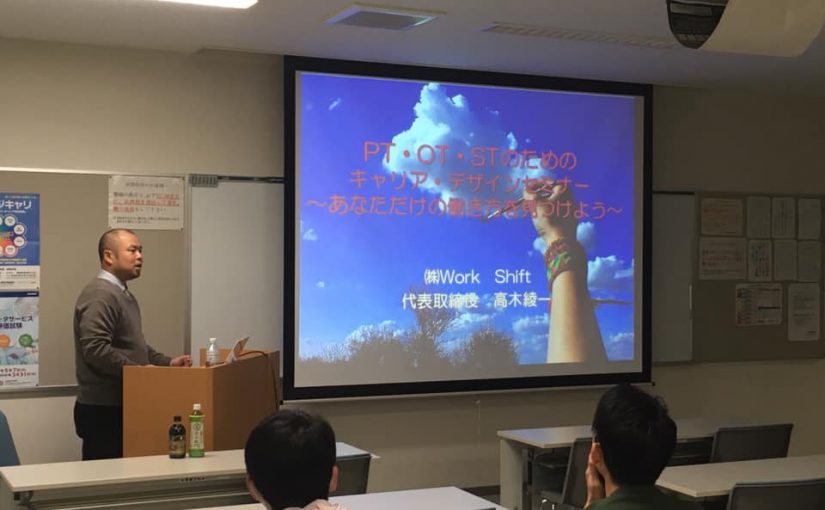BCPとは「Business continuity plan」の頭文字を取った略語である。
日本語では「事業継続計画」と呼ばれ、近年、BCPが注目されている。
ご存知の通り、新型コロナウィルスCOVID–19が世界各地で蔓延している。
日本でも、東京都や大阪府と言った大都市圏を中心に全国各地で感染が拡大している(2020年4月現在)。
そのため、政府より不要不急の外出自粛が国民になされている。
確かに、感染防止には不要不急の外出は効果的な方法であるが、一方で経済の委縮を生じさせてしまう。
外出をしてもらうことが前提である宿泊施設、タクシー、バス、飲食店、小売店、百貨店、アミューズメント関係などは軒並み大打撃を受けている。
筆者が関わるデイサービス、クリニック、病院、フィットネスクラブなども利用者減が日増しに強くなっている。
このような状況においては、平素の事業で利益をだすためのマーケティングやマネジメントではなく、事業を継続するための事業継続活動が必要となる。
簡単に言えば、生き残ることが最優先事項ということである。
BCPを策定する目的は
自然災害・大事故・不祥事・感染症・戦争等が生じた際に、被害を最小限におさえ、自社のコアビジネスを素早く再開させることで、損害の発生を最小限に留めること
である。
現在の日本では、BCPの策定は法的義務はないためBCPを策定している企業はマイノリティーである。
しかし、今回の新型コロナウィルスCOVID–19により多くの企業にBCPの策定が求められるのは明白である。
BCPの策定においては次の4点が重要と言われている。
初動対応計画
仮復旧計画
本復旧計画
保守運用
である。
この中で最も重要といわれているが初動対応計画である。
「初動対応計画」のポイントは次のとおりである。
①防衛対策
危機的状況が確認された直後に行う活動であり、被害を最小にとどめるための防衛対策である。危機的状況のリスク管理をおこない、リスクが自社に与える影響を予想し、リスク階層別の対応策を考える。
例 危機的状況を回避する手段を考える、被害が出た場合は速やかにダメージコントロールを行う、会社や従業員に実害が出た場合は速やかに救援措置を行うなどが当てはまる。
②仮復旧のための準備作業
危機的状況に対応し、復旧に向けて動き出すための一連のプロセスである。
従業員の健康状況、施設の安全性、ビジネス環境の状況などを評価し、復旧ができる箇所を模索する。場合によっては、新しいビジネス環境に応じた新規事業やビジネスモデルを検討・立案を行う。
皆さんの事業所にはBCPはあるだろうか?
また、BCPは事業所だけではなく個人事業主やフリーランスにも求められるものである。
一度、社会環境が変化すると個人事業主やフリーランスは大打撃を受けるからである。
今回の新型コロナウィルスCOVID–19のことを教訓にBCPについて考えてはいかがだろうか?
株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
茂澤メディカルクリニック
たでいけ至福の園
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学 客員准教授