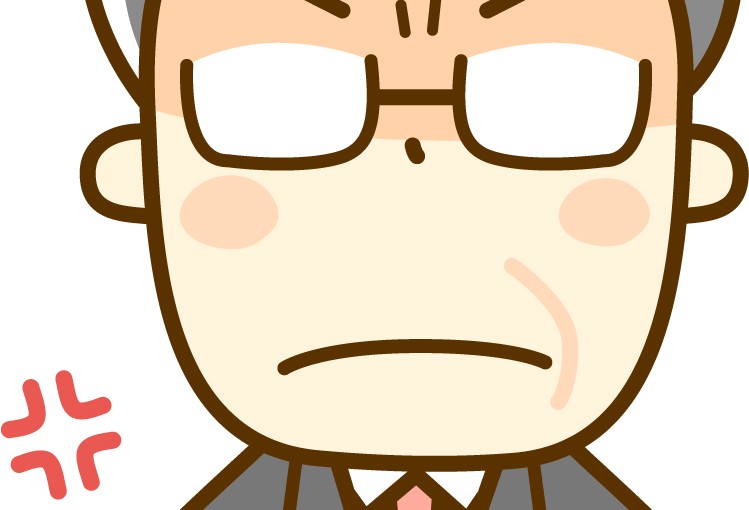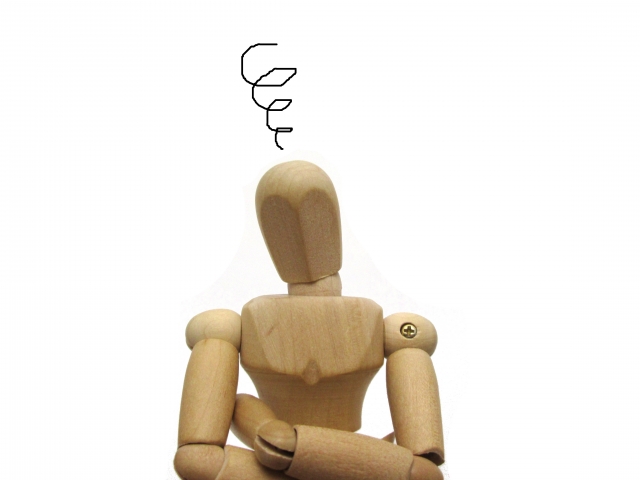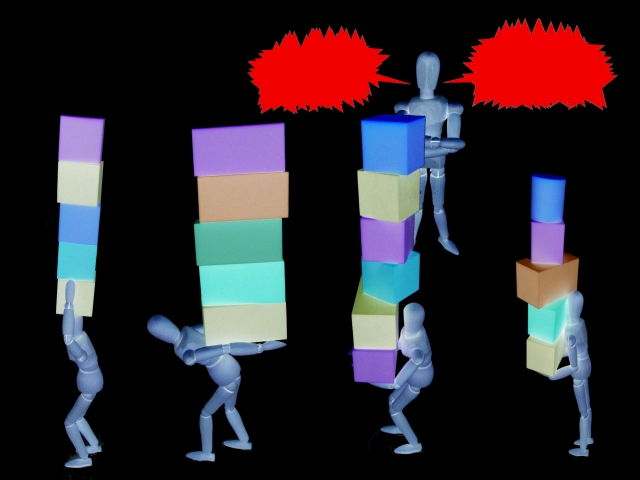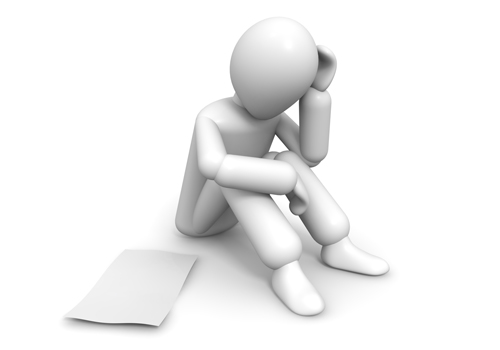訪問リハビリの利用者が増えない
病棟の稼働率が上がらない
通所介護への紹介が少ない
だから・・・・
営業に行ってこい!!!!
という経営者は多い。
しかし、残念ながら、営業に行っても利用者は増えない。
なぜか?
営業の効果が極めて限定的であるからだ。
営業が単体でできることは、せいぜい、「事業所のわずかな認知度の向上」程度である。
しかも、営業は時として諸刃の剣となる
皆さんも、色々な商品やサービスの営業担当者から営業行為を受けたときに不快な気持ちになったことはないだろうか?
実は、営業が成功するための条件として、「信頼」が存在する。
信頼できる人や事業所の営業は、不快にならない。
むしろ、もっと話を聞きたいと思う。
しかし、売り込み臭の漂う信頼のない人からの営業は、極めて不快である。
したがって、営業を行う前に、信頼関係の構築が重要である。
信頼関係は日々のサービスや情報発信により獲得されていくものである。
信頼関係構築のための地道な作業をせずに、営業さえすれば利用者が獲得できると考えている経営者は、とにかく残念な人である。
医療や介護サービスは信頼関係に基づくソーシャルキャピタルである。
ソーシャルキャピタルは信頼関係で機能する資本である。
営業に行く前に質の高いサービスの提供が重要である。
執筆者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)
関西医療大学保健医療学部 助教
関西学院大学大学院 経営戦略研究科