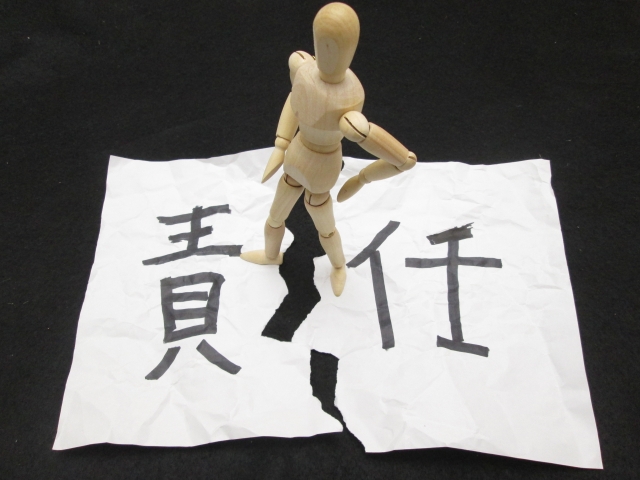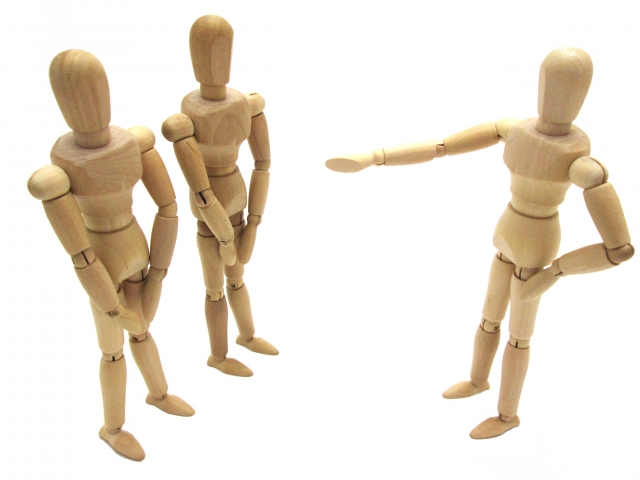孤独になるのが怖い
他人と同じ状況に安堵感を感じる
飲み会に誘われないと不安である
知り合いというレベルで仲良くなった気がする
このような心理状態になる人が周りにはいないだろうか?
このような人は、人間関係条件のハードルが低いと言える。
志や理念を共有してなくても、ただ、知り合いというだけで仲良くなった気になり、ともに食事をしたり、時間を過ごすこと出来る人たちである。
しかし、その友達がビジネスのパートナーや将来の盟友になることはなく、一瞬の知り合いで終わることが殆どである。
人と違ったことをすることに対する怖さや恐れを感じている人は、常に自己保身を前提にした行動パターンを取る。
その結果、自分の所属しているコミュニティから、異端扱いされず、受け入れられることで心理的な安定を図る。
そのため、安易な人間関係を構築することに腐心する傾向が強い。
しかし、このような特徴を持つ人は自分の人生を自分でコントロールことが難しい。
なぜならば、人間関係を広げれば広げるほど、多様な価値観が広がり、他者からの目が気になるからだ。

理念や信念を共有していない知人や友人を10000人持つよりか、理念や信念を共有し、共通の目的に向かって走れる盟友を1名持つ方が遥かに意味がある。
Facebookなどでやたらめった人脈の豊富さをアピールする人がいるが、実はその人は人間関係地獄にはまっている。
他人の目が気になり、何もできない状況を加速させているだけだ。
また、自分自身をアピールせず、人脈の豊富さをアピールしている時点で社会人としては二流である。
読者の皆さん、人間関係をどんどん整理していきましょう、どんどん人間関係を断っていきましょう!
人間関係は創るだけでなく、断つことも社会人には必要なスキルだ。