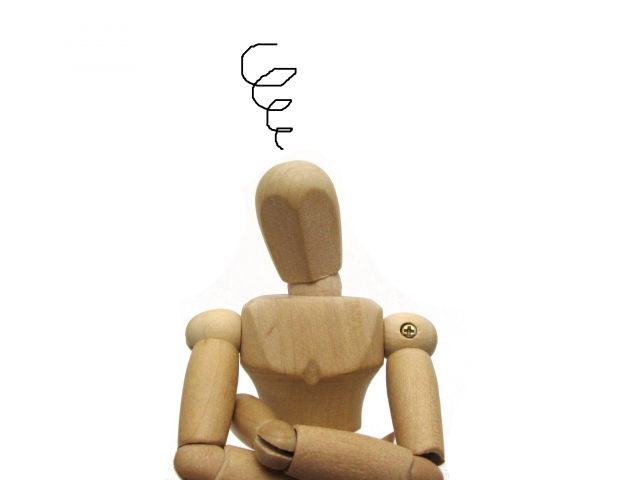筆者は2018年度診療報酬・介護報酬改定に関して全国各地でセミナー講師の依頼をいただくことが多い。
多くの参加者は、施設基準の内容や加算の算定要件に関して関心がある。
施設基準や加算が経営に直結するため、大きな関心があるのだろう。
しかし、多くの人は施設基準や加算は手段であることを忘れている。
経営理念という目的を果たすために施設基準や加算という手段を存在することを忘れているのだ。
施設基準や加算を満たすことだけが、目的となっている事業所に共通することは質の低い人材の雇用、書類だけ揃えて監査を乗り切る、人材育成に興味がないである。
このような事業所は、診療報酬・介護報酬改定のたびに10円単位の金額に一喜一憂する。
言い換えれば、厚生労働省に自社の運命を委ねていると言える。
このような事業所は遅かれ早かれ、厚生労働省と市場に抹殺される。
在宅復帰、ADL改善、活動と参加の推進、看取りの促進などは元来崇高なものであり、簡単にできるものではない。
社会保障費が厳しくなる現在、効果的な医療や介護が求められるようになっている。
理念がない事業所は向かうべき方向性が定まっていないため、見かけ倒しのサービスを行い加算等を算定しているため、決して効果的な医療や介護サービスを提供しているとは言えない。
誤解を恐れずに言えば、診療報酬・介護報酬などどうでもよく、社会に貢献することができる組織を作れば、診療報酬・介護報酬はあとからいくらでもついてくるというものである。
施設基準や加算要件だけを追いかけるから組織がおかしくなる。
あるべき姿を追いかけた結果、施設基準や加算要件を満たすことができるのだ。
診療報酬・介護報酬の10円単位に一喜一憂するのではなく、自社の理念を実践することができる組織作りに邁進することが最も効果的な生き残り政策である。
あなたの医療機関や事業所は組織作りに邁進していますか?
それとも加算算定に邁進していますか?