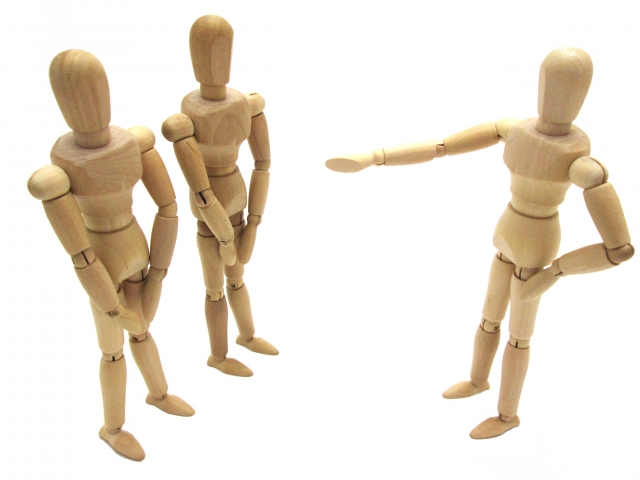キャリアデザインにお金は必要である。
これは、厳然たる事実である。
大学院への進学
資格取得のプロセス
治療技術の認定コースを受ける
自身より実力のある人の弟子になる
様々な研究に打ち込む
これらの活動はすべて時間とお金を犠牲にしている。
これらの活動に打ち込む時間に、働くことが出来れば収入が得られるし、ましてや、大学院、認定コース、研修は学費や参加費という現金を失うことになる。
キャリアを磨くためには、大変な金銭的負担を背負わなくてはならない。
しかし、世の中には金銭的な負担を理由にキャリアデザインを躊躇する人がいる。
金銭的な不安があるため、自己投資が出来ないのが理由である。
しかし、そういう人に限って、家や車のローンを組んでいる。
35年間にわたり金銭的負担を背負う家のローンは組めるのに、自分自身のキャリアを磨くためのローンは組めない。
大学院の学費は高くても200万円程度である。
一方、家のローンは利息を含めば、総額3000万円~5000万円である。
仕事で成功している人は、常に自己投資をしている。
自己に惜しみなく時間とお金をつぎ込み、キャリアを常に前進させている。
その結果、社会より高い評価を受け、金銭的な対価を得ている。
家や車のローンとキャリアデザインのローン。
あなたにとってどちらのローンが人生にとって大切だろうか。
自分のキャリアにお金をかける。
そんな発想を持っても良いのではないだろうか?
これからの時代、与えられた労働時間で作業するだけの労働者は、厳しい処遇を受けることになる。
組織や社会にとって、キラーコンテンツになるような働き方をしなければ、社会からの評価は得られない。
そのためには、自己投資が極めて重要な意味を持つ。