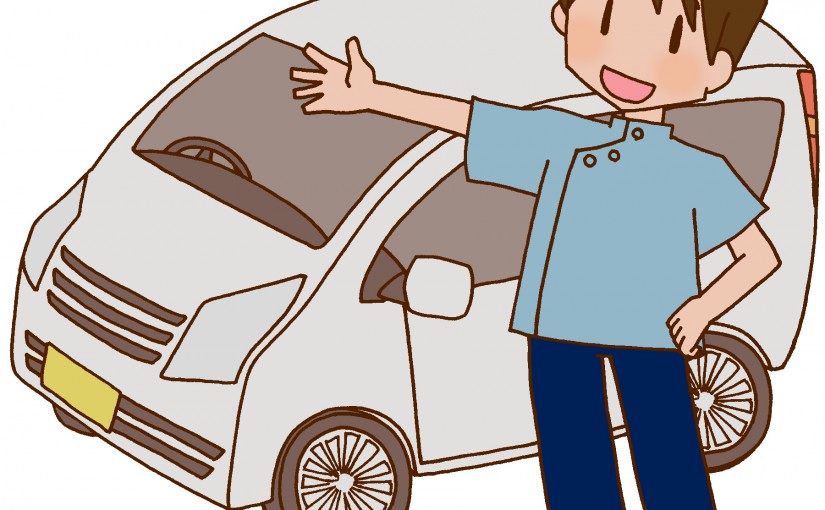2014年度診療報酬改定における地域包括ケア病棟、2015年度介護報酬改定における通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション実施加算、社会参加支援加算、そして、今後、議論されるリハビリテーションの出来高算定の在り方。
これらの話はすべて、リハビリテーション費用の包括化を示すものである。
現在の単位時間あたりの個別リハビリテーションの提供は、以下の特徴がある。
1)提供サービス時間に対する料金体系であるため、患者の理解が得られやすい
2)レセプトの請求が簡便である
3)リハビリテーションは施術行為と捉えられているため、提供時間を明確にして施術を提供することが合理的と考えられている
しかし、現在、単位時間あたりの個別リハビリテーションの提供方法が疑問視されている。
「リハビリテーションは施術ではなく、全人間的復権を支援するあらゆる活動をである。特にICFが提唱する心身機能・構造、活動、参加のすべてに介入することが、リハビリテーションを提供する上では重要である」との主張がここ数年間の医療・介護報酬改定に反映されている。
また、一部の有識者達は、「看護師は個別看護ではなく、包括的な業務や他職種連携の中で、看護を提供して、病棟の基本入院料を算定している。だから、個別リハビリテーションをなくして、セラピストも包括的な取り組みで、リハビリテーションを行い包括的なリハビリテーション料を算定すれば良い」という主張をしている。
これらの考え方には、賛否両論があるが、私の考えは以下のとおりである。
まず、リハビリテーションはICFの概念に基づけば、心身機能・構造、活動、参加に対して総合的にアプローチするものである。
つまり、心身機能・構造はリハビリテーションの重要な部分であり、心身機能・構造と活動、参加を有機的に統合させる介入が必要不可欠である。
そのため、活動と参加を円滑に進めるための心身機能・構造を獲得することは重要である。
心身機能・構造を改善させるためには、患者の個別性とエビデンスに基づく集中的な治療的介入は必要である。
生活期の患者であっても、定期的に医師の診察を受けて、投薬などの積極的治療を受けるのと、同様にリハビリテーションの介入により心身機能・構造をよりベストな状態に保つことは、活動、参加を保証する上で重要である。
したがって、単位時間あたりの個別リハビリテーションの提供方法は、必要であり報酬上も評価される必要がある。
有識者より「看護師は個別看護をせず、包括的な業務や他職種連携の中で、看護を提供して、病棟の基本入院料を算定している。」との意見があるが、個別看護というものが提供された場合、患者状態を大きく改善する可能性も高い。
実際に、訪問看護では、個別看護を提供し、患者の様態が大きく改善している。
心身機能・構造を改善させる単位時間あたりの個別リハビリテーションは、活動、参加の向上に寄与しなければならない。

従来のリハビリテーションは、活動、参加の取り組みが少なかったことから、2015年度介護報酬改定にて患者の行動変容への介入や社会活動参加機会の提供といった取り組みを評価する報酬体系が導入された。
このような報酬体系の導入は、セラピストの働き方を大きく変える。
リハビリテーションは生活支援総合業務に変わりつつある。
生活支援総合業務とは、心身機能の改善、生活上の困難な活動や参加に関する評価や介入、社会参加資源の発掘、患者を支える関係者へのコンサルテーションなどである。
心身機能・構造を変えるスペシャリストとしてのセラピスト
活動、参加をコンサルテーションできるジェネラリストとしてのセラピスト
つまり、医療や介護保険のリハビリテーションの包括化が進む中で、活躍できるセラピストはスペシャリストとジェネラリストの両面を追求し、実践できる人材である。
従来より活動、参加に対するアプローチの介入が増加すれば、単位時間あたりの個別リハビリテーションの提供時間は物理的に少なくなる。
したがって、リハビリテーションの包括化が進む時代だからこそ、短時間で結果の出せる個別リハビリテーションを提供しなければならない。
リハビリテーション費用の包括化やICFは、心身機能・構造、活動、参加のそれぞれへの高品質なリハビリテーションの介入を求めていると言える。