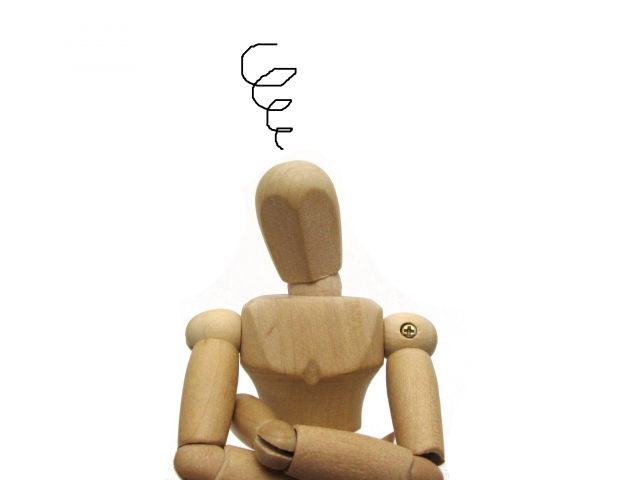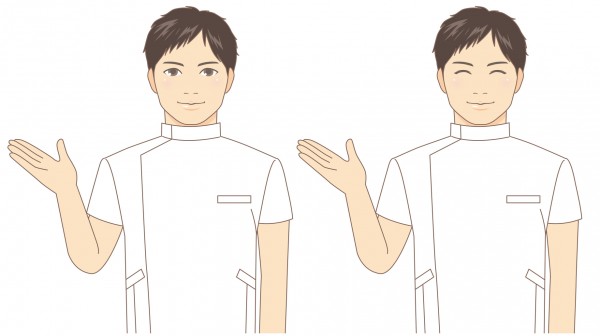お正月・ゴールデンウイーク・お盆休みなどの節目で、PT・OT・STの方が急激にモチベーションがあがり、SNSなどに突如として「これからの人生の目標」や「取得したい資格」について書き込むことがある。
「非常に高いモチベーションが生まれている」ことを感じさせる言動である。
しかし、最初にSNSに書き込んでから数日たつと普段通りの投稿内容に変化し、いつの日か「これからの人生の目標」や「取得したい資格」について語ることすらもなくなることを良く散見する(下図)。
瞬間最大風速のモチベーションが吹き荒れた後に全くモチベーションの風が吹かない・・・。
それではなぜこのような状況になってしまうのだろうか?
それは、「自分のアイデンティティから生まれたモチベーション」ではないことが原因である。
人間は他人から与えられた、促された、命令された行動や金銭などの打算的なことを目的とした行動は長続きをしない。
なぜならば、それは「自身のアイデンティティから生まれた行動」ではなく、「他者の圧力により生じた行動」だからである。
「他者の圧力により生じた行動」が上手くいかなくなると、「自分自身が心の底から手に入れたい目標ではない」ため、行動を継続することが難しくなる。
つまり、「他者の圧力により生じた行動」には執念がないのだ。
執念は「自身のアイデンティティから生まれた行動」に宿る。
したがって、「なりたい自分」「自分らしさを感じる目標」「自分の本音」についてしっかりと悩み、その先に芽生えた「目標に対する行動」を大切にすることが重要である。
「最大瞬間風速のモチベーション」を繰り返している人はぜひ参考にしてほしい。
株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授
理学療法士×イラストレーター
医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。
臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。
問い合わせ先
ホームページ https://fukunoe.com/
Facebook https://www.facebook.com/illustration.studio.fukunoe
メール studio.fukunoe@gmail.com
Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama
Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama.fukunoe/