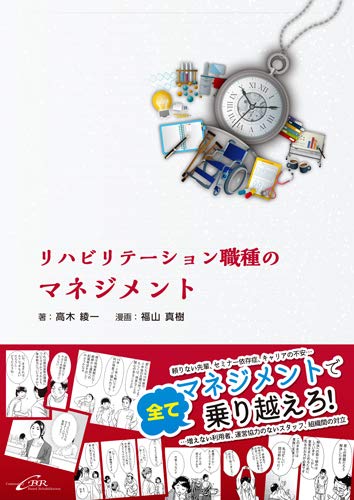2020年4月になって日本では新型コロナウィルス感染症が全国的に広がり、日本社会に大きな打撃を与えている。
特に、経済活動に与える影響は大きく、世界大恐慌レベルの不況になると予想されている。
今現在、多くの経営者や管理者は経済的な不安を強く感じている。
経済的に不安を感じると人間は極度のストレスを感じ、そのストレスはその人の本性をあぶりだす。
筆者が医療や介護の経営者や関係者より感じる「悪い本性」は以下の三通りである。
パターン① 都合の良い依頼をする人
人間関係も疎遠でかつ信頼関係が破綻している人が、自社の経営や運営が思わしくなくなり、急に不安になったことで、急に連絡をしてきて「色々と助けてほしい」と懇願する都合良すぎる依頼をしてくる人
パターン② すぐに減給・雇止めを言っちゃう人
日頃は「職員は会社の財産だ!皆さんのおかげで会社は成り立っている!」と公言しているが、経営状態に不安を覚えるとすぐに、減給やシフト調整を醸し出し、リストラの臭いがプンプンする人
パターン③ 売上低下を他人の責任に転嫁する人
日頃から経営改善の努力や従業員の教育などを放置し、いざ、経営状態が悪くなると職員の努力が足りないから経営状態が悪いと経営者としての責任を転嫁する人
これらの本性は平時においては、表面化することはないが有事においては顕著に表面化してくることが多い。
このような本性はその人の価値観や他人に対する思いを如実に表したものである。
したがって、このような本性を感じた時は、この経営者や管理者とこれからも長い間一緒に働くべきか?を考える良い機会である。
新型コロナウィルスにより職場ではいろいろな人の本性が見えているのではないだろうか?
ちなみに、私はこんな経営者か管理者とは長い間一緒に働きたいとは思わない。
株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
茂澤メディカルクリニック
たでいけ至福の園
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学 客員准教授