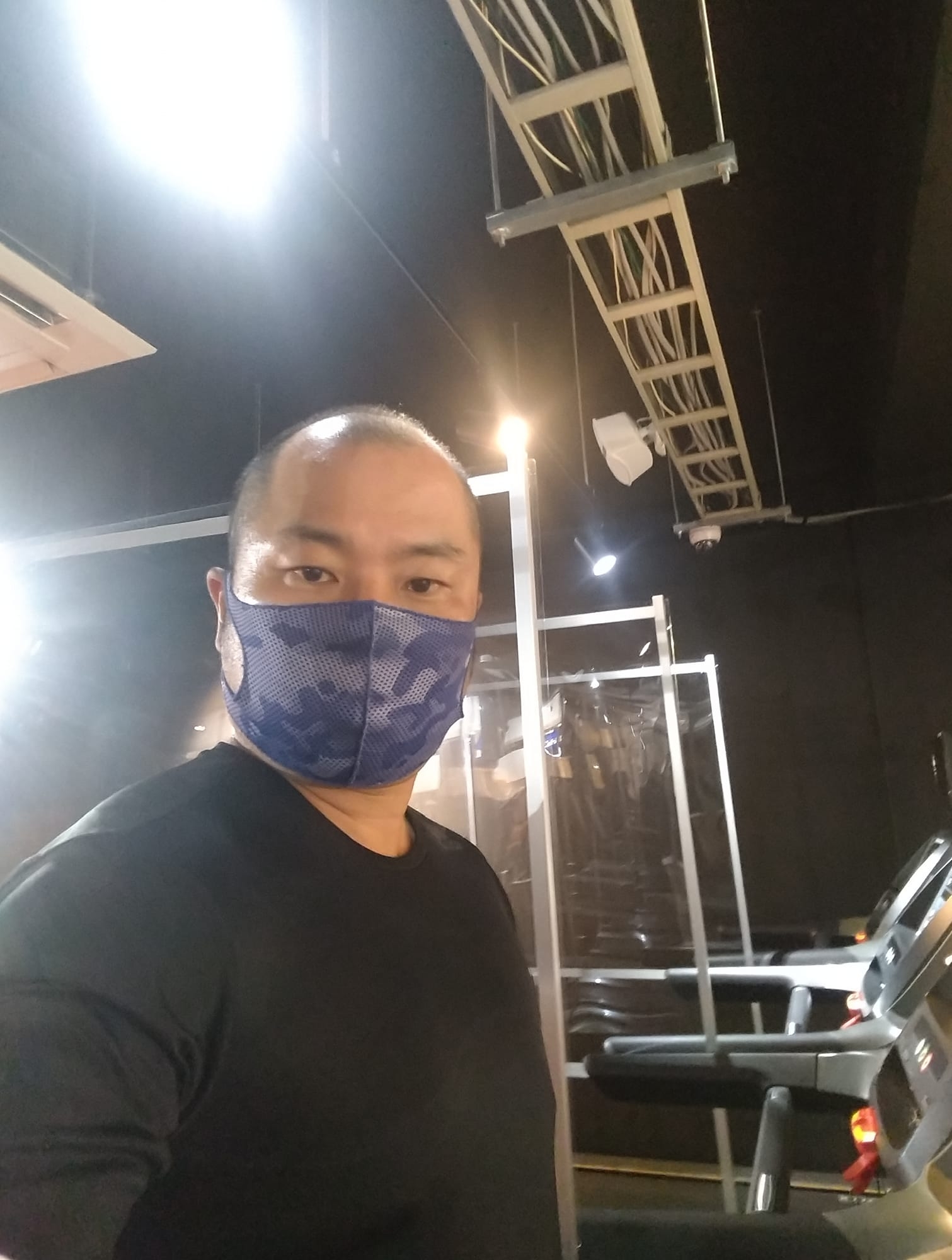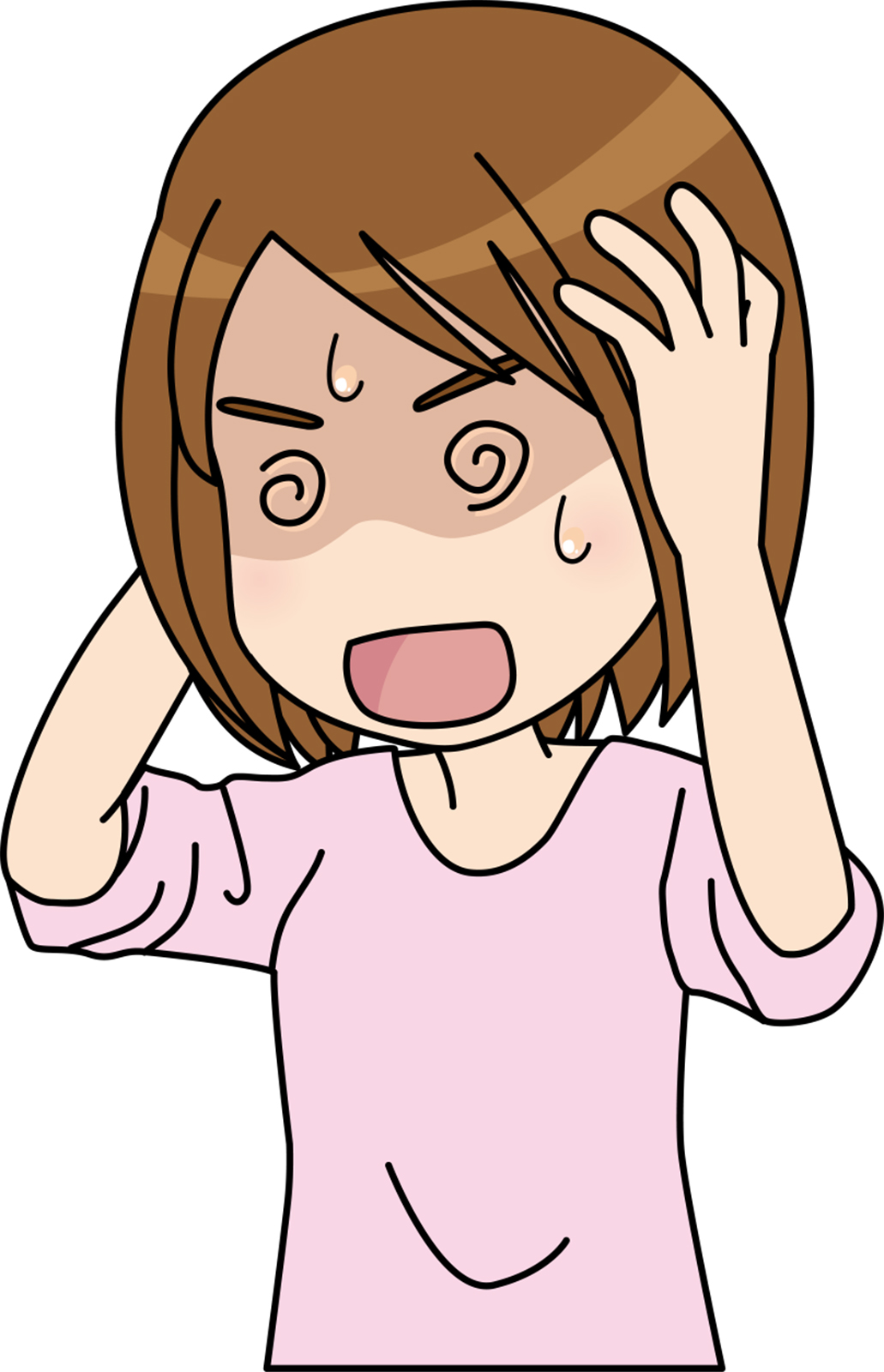2021年度介護報酬改定では通所リハビリに新たな方向性を示された。
今回のブログではリハビリテーションマネジメント加算Ⅰの基本報酬への包括化および生活行為向上リハビリテーション実施加算について解説をしたい。
【リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの基本報酬への包括化】
通所リハビリはあらゆる時間区分において基本報酬が増加したが、これはリハビリテーションマネジメント加算Ⅰが廃止され、基本報酬に包括化されたことによるものである。
リハビリテーションマネジメント加算の算定率は90%を超えていたことから、加算区分としての意味をなさなくなったため、基本報酬に含まれた。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの要件は次のようなものであった。
- リハビリテーション計画を定期的に評価し、適宜計画を見直していること
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネジャーを通じて、ご利用者が利用する他の介護サービスの職員に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等の情報を伝達すること
- 新規にリハ計画を作成したご利用者に、医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、1ヵ月以内に自宅等を訪問し、検査等を実施すること
- 医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、リハの目的とリハ実施に伴う指示があること(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)
- リハ実施に伴う指示内容がわかるように記録すること
つまりこれらの内容は通所リハビリの業務として標準化されたものとなった。
リハビリテーションマネジメント加算Ⅰの包括化の意味は、通所リハビリの本来の意味をより明確にしたと言え、医師や理学療法士等のリハビリ職種がより協業し、リハビリの質を上げることが必須となったと言える。
通所リハビリは歴史的に老健や診療所のサテライトビジネスとして運営されてきた経緯もあり、経営者や医師の関りが乏しい傾向がある。
そのため、国が求める通所リハビリの機能が向上しない状況が続いていたが2021年度改定により今後は、リハビリ職種にお任せする運営スタイルは通用しなくなった。
【生活行為リハビリテーション実施加算の要件緩和】
生活行為リハビリテーション実施加算は要件が見直された。
この加算は算定率がなんと1%台という極めて危機的な状況にあるものだった。
その理由は、6か月間の算定期間を経過した場合、基本報酬が15%減算されるという条件があったために、ほとんどの事業所が同加算の算定に消極的であったと言える。
今回はこの基本報酬15%減算の条件が撤廃された。
この加算は、ADLレベルや活動参加レベルが疾病や急性増悪等により低下し場合に早期の集中的なリハビリテーションを提供する目的で設置されたものである。
また、この加算は急性期や回復期の退院患者の受け皿となり在宅回復期を実現する切り札と言えるものであった。
しかし、あまりの算定率の低さから、大幅な要件の緩和が行われた。
この変更により算定率は大幅に向上するはずであるが、もし、算定率が上がらない場合、通所リハビリはみずから在宅回復期としての役割を放棄していると判断される。
その場合、2024年度介護報酬改定で同加算は消滅してしまう可能性が高い。
株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授