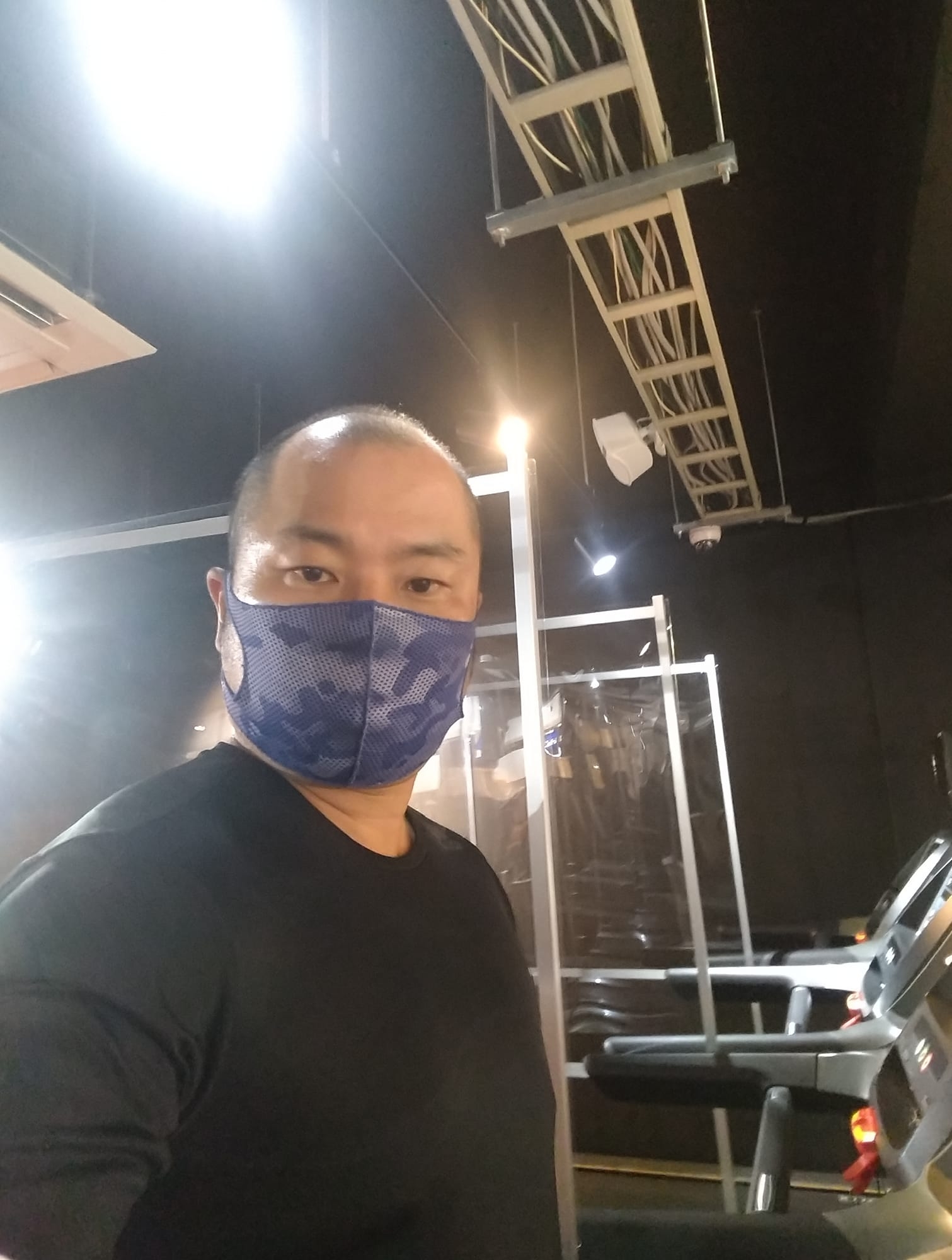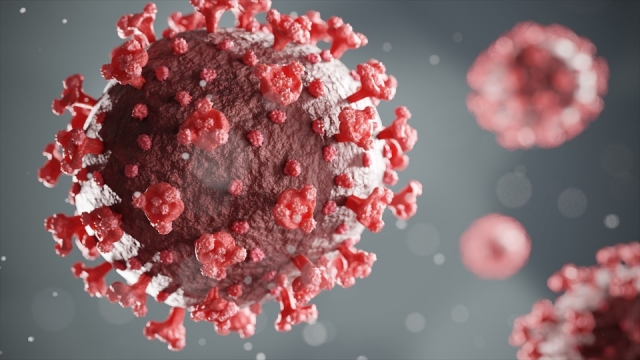採用は人材獲得のスタート時点。
このスタート時点で最も大切なことは、「人と仕事と組織」のマッチングです。
マッチングとは
「つり合うこと」、「調和すること」
です。
組織や仕事が求めている能力、資質、姿勢、共感とその人材との適合性を評価するのがマッチングとなります。
マッチングを軽視しているリハビリ部門は、
離職率が高い
売上重視の人材育成軽視
従業員満足度が低い
運営に対する非協力な態度
陰口が多い職場
になる傾向が高いです。
マッチングには次の要素が必要です。
①獲得した人材スペックの明確化
②人材募集の方法を考える
③募集してきた人材の選考方法
①獲得した人材スペックの明確化
これについては「リハビリ部門採用戦略のキーポイント 人材スペックの明確化」をご確認ください。
②人材募集の方法を考える
組織の外部から人材に応募してもらうためには、「人材募集」という機能が重要となります。
「人材募集」の機能をどこまで高められるか?は非常に重要な要素となります。
ホームページ、SNS、ブログ、人脈、ハローワーク、優良人材紹介会社、求人誌などの「人材募集」の方法があります。
その中でも、ホームページ、SNS、ブログ、人脈に関しては企業努力によって相当なレベルの差が出る部分です。
単なる求人募集の情報を提供するだけでなく、法人の理念、ビジョン、取り組み、実績をわかりやすく伝えることができるか?が重要となります。
しかし、多くのリハビリ部門では募集人数、職種等の記載にとどまっていることが多く、募集の機能は極めて低い状態です。
③募集してきた人材の選考
応募してきた人材がどのような能力や資質を持っているか?について判定が必要となります。
その判定には、求める人材スペックが必須となります。
正確に言えば、「求める人材スペック明確でなければ選考は不可能」と言えます。
選考方法には面接、試験などがありますが、人材不足や利益優先のリハビリ部門では面接や試験は形骸化しています。
株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授