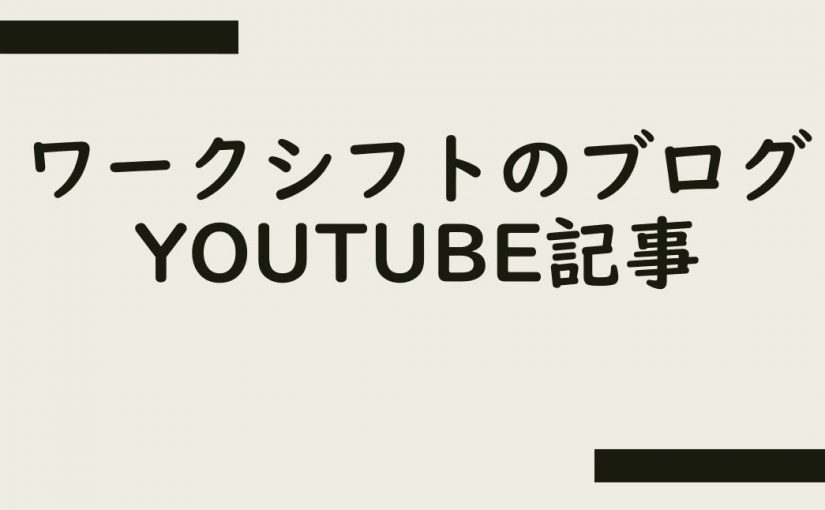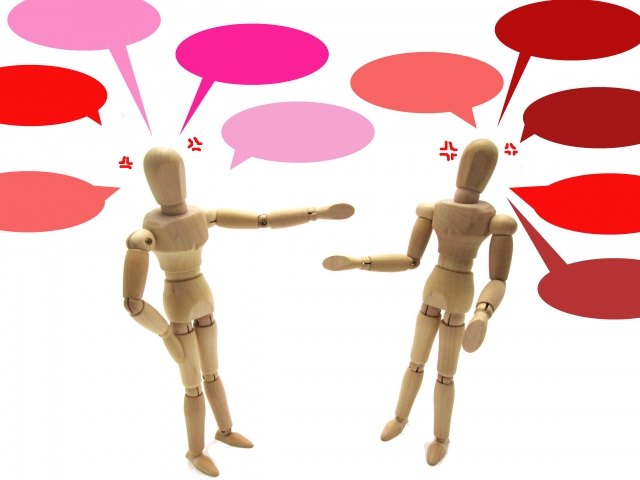セラピストの大学院進学がブームである。
また、現在は、様々な学会があり多くのセラピストが学会発表を行っている。
昔と比べて学術に取り組むセラピストの絶対数は非常に増えている。
その中で、学術をがんばっても待遇が変わらないと嘆くセラピストも多い。
特に大学病院以外の民間病院や民間事業所ではよく見られることである。
経営者の筆者に対する相談の一つに「学術活動に頑張っているセラピストの評価方法はどうしたらいいのか?」というものがある。
ようするに、「学術を頑張っているのだから組織からもっと評価されてもよいのではないか!」と訴えるセラピストがいるという事である(図)。
それでは、学術を頑張っているセラピストを組織が評価することの正当性や合理性はどこにあるのだろうか?
企業経営から考えると、企業業績や企業活動の質の向上に資するものかどうか?という判断軸が重要となる。
簡単に言えば、その学術活動は、組織にどのようなインパクトを与えたのか?が重要であるという事である。
学術活動が組織が抱える課題の解決に寄与することができればその学術活動は非常に有意義なものであり、評価の対象となる。
在院日数が短縮した
FIM利得が向上した
後方連携の質が向上した
早期離床のシステムが完成した
誤嚥性肺炎や転倒が減った
など・・・
実利に資する研究であればあるほど評価は高い。
しかし、組織の課題を決して解決することはないような学術活動・・・セラピストの極めて個人的な興味による研究、社内で議論されることない症例発表などは評価に値しないだろう。
研究だけが評価されたいのであれば、研究機関や大学病院などに就職することが望ましい。
しかし、民間病院や民間施設では実利が求められる学術活動が必要である。
投稿者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)
関西医療大学保健医療学部 助教
関西学院大学大学院 経営戦略研究科
イラスト提供
福山真樹
理学療法士×イラストレーター
医療・介護等の現場を、医療職種の胸の内まで分かりやすくイラストで伝える。
臨床で勤務する理学療法士だからこそ描ける作品を医療関係者等へ提供し、書籍・学会・福祉機器紹介PV等、様々な場面で用いられている。
問い合わせ先
Facebook https://www.facebook.com/Masaki.Fukuyama.PT
メール big.tree.of.truth@gmail.com
Twitter https://twitter.com/PT_Fukuyama
Instagram https://www.instagram.com/masaki.fukuyama