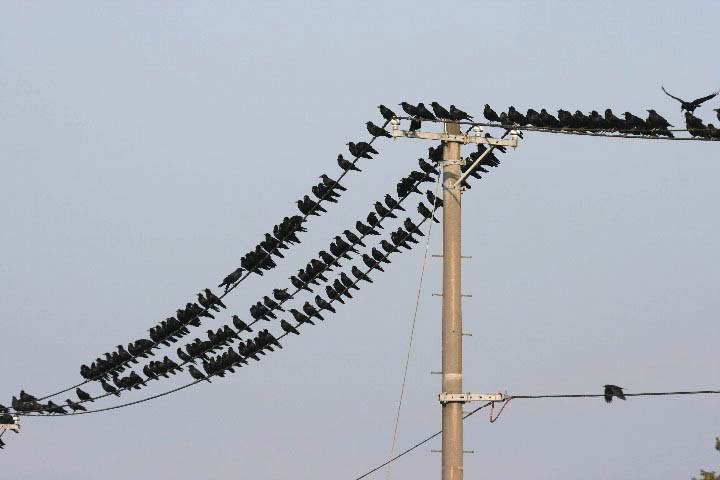医療・介護に費やす国費が高騰していることは周知の事実である。
この問題に対する介入方法は多く提案されているが、とりわけ、今後は「自助」「互助」サービスの導入が加速していく。
国は以下の4つサービスカテゴリーを医療・介護領域に導入したい考えている。
現在は、ほとんどの医療介護従事者は共助と公助に携わっている。
つまり、公的医療・介護保険や財源が国から出ている事業に関わっているのが現状である。
政府は、財源が国からではなく、国民から得られる自助と互助の導入を推進している。
例えば、金融庁はこれまで、生命保険に限らず民間保険会社の現物給付は禁止してきが、高齢者向けの商品を充実させたいと要望する保険会社の意向を受け、「保険会社が直接提供しないなら」という条件付きで認める方針である。
つまり、保険請求の条件を満たせば、お金の代わりにサービスを受け取ることができる仕組みが導入されようとしている。
脳卒中になったら、介護保険だけでなく、民間の○○リハビリ保険を利用して、月20回のリハビリテーションサービスを受けることができる という保険商品が近々、登場する可能性が高い。
また、フィットネスクラブや学習塾が高齢者向けの介護予防や健康増進サービスにどんどん参画している。
このような状況で一番取り残されているのは、医療・介護産業で働く看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士などである。
サービスの担い手でありながら、このような時代の流れを知らないのは誠に嘆かわしい状況である。
他の業種に自助・互助のサービスが占有される前に、医療・介護産業従事者はいち早く行動を起こし、事業参入を行うべきである。