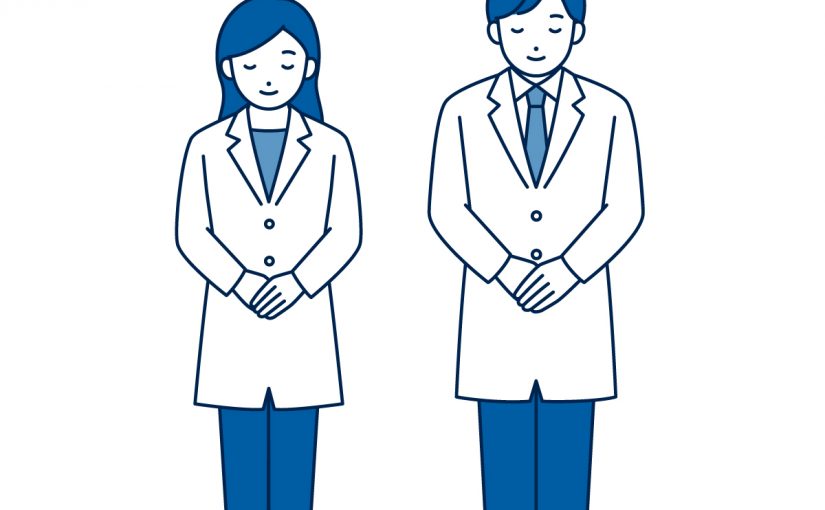高齢化の進展により、急性期病院に入院する患者の属性が変化している。
急性期病院は重症度の高い急性発症の患者が入院する「場」であったが、高齢者の延命率向上や介護保険によるケアの提供により、在宅生活と病院入院を繰り返す高齢者が増加している。
その結果、急性期病院には複数の既往歴や認知症を有する高齢者が入院するケースが増えており、急性期医療の医学的モデルが適応できない状況が進んでいる。
そのため、急性期病院では慢性期疾患を持った高齢者に対する急性期治療を行うという複雑な状況が増えている。
特に認知症高齢者今後800万人になるとも言われており、急性期病院における認知症対応も大きな課題である。
つまり、高齢化が進展し、介護保険サービスの質が良くなればなるほど、急性期の役割は多様性を増してくる。
治療を意味するキュア、全人的アプローチを意味するケア
この両方の提供が急性期病棟には求められる時代となっており、リハビリテーションにおいてもキュアとケアのバランスが課題となっている。
専門性の高い治療技術、多職種と連携し、最良のQOLを生み出す技術、これらがミックスされたハイブリッドリハビリテーションが向こう30年は加速する。
急性期だから慢性期、認知症の技術を磨く。そんな時代になっている。