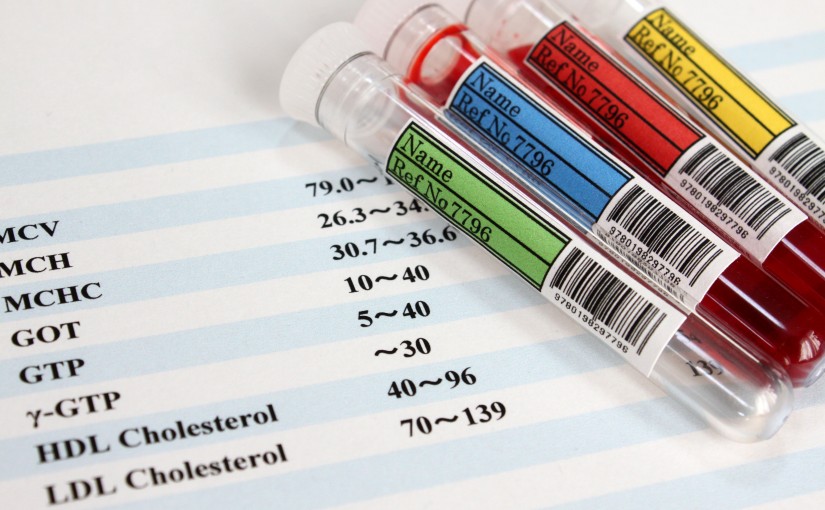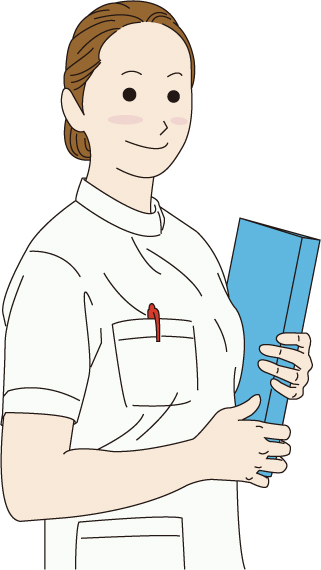2000年以降の緊縮財政により、医療・介護事業では経営環境の変化に伴い、患者や利用者獲得のための「営業活動」が活発化した。
医療の機能分化の促進、介護保険事業所の増加により、患者や利用者の争奪戦の状況が生まれ、地域連携室や事務方の職員などが地域の医療機関、介護事業所、居宅介護支援事業所に患者や利用者の獲得目的で挨拶回りに行くなどの営業行為は、もはや、ごくごく普通のことである。
しかし、そんな「営業行為」だけでは、もうどうしようもないほど現在の医療機関や介護事業所を取り巻く環境はより厳しさを増している。
地域包括ケアシステムの推進は、各医療機関や介護事業所の「実力」を白日の下にさらしている。
在院日数短縮
重度者対応
ADL改善
24時間365日対応
地域連携
自立支援
ターミナル対応
多職種連携
認知症対応
など・・様々な項目への取り組みが医療・介護事業所の必須事項になっている。
昨今ではこれらの項目に対応できない場合、患者や利用者だけでなく、連携医療機関や介護事業所から、不信に思われる。
例えば、次のような事例は「不信」を招く典型例である。
営業活動で、「〇〇の疾患であればすぐに入院対応できますので、いつでも、ご連絡ください」と言っていたが、いざ、入院の依頼をすると先方の医師の判断で入院が断られる。
自立支援を目指しているデイサービスという紹介で、デイサービスを利用したが、筋力トレーニングだけのデイサービスだった。
「365日24時間対応の訪問看護ステーションなんで、ご安心ください」と利用者に伝えていたが、実際に深夜に電話したら、オンコール担当の看護師の態度が悪かった。
「リハビリテーションを中心にしている病院です」という紹介で入院したが、土曜日、日曜日はリハビリテーションがなかった。
旧来の営業活動は、エクスターナルマーケティングといわれるもので、いわゆる、認知度を高めるための行為である。
こんな医療をしている医療機関ですよ!
こんなことに取り組んでいる介護事業所ですよ!
ということを、市場関係者に伝えることで、サービスや商品の購入を促進するものである。
エクスターナルマーケティングは
競合が少ない
市場が成熟していない
相手に知識がない
場合に有効である。
しかし、昨今の医療・介護情勢については、医療・介護分野の関係者だけでなく、多くの国民もインターネットなどのメディアを通じて知っていることが多い。
そのため、認知度を高める程度では、サービスや商品の購入が起こりにくい。
そこで、重要なのがインターナルマーケティングである。
このマーケティングは
社員に自社のサービスや商品の価値を教育し、日常的な活動において顧客の期待を裏切らないようにする
ことである。
言い換えると、「自社が謳っているサービスや商品の質を常に順守する」ということである。
よい噂を聞いたので、実際に利用したが、期待していたサービスを下回ったことはないだろうか?
このような場合、もう一度そのサービスを利用したいと思わない。
医療・介護分野では、患者・利用者の獲得目的の営業は、エクスターナルマーケティングのような活動だけでは、もう、効果を出すことはできない。
利用者や入院稼働率が低下した場合、多くの経営者や院長は「外部の事業所に営業に行ってこい!!!」と言う。
しかし、この発言は本末転倒であることが多い。
そもそも利用者や患者が減っている理由は何だろうか?
なぜ、利用者や患者が離れて行っているのだろうか?
ほとんどの人は
臨床現場が、「インターナルマーケティングというマーケティングの最前線であること」を理解していない。
今一度、臨床現場におけるマーケティングを見直すべきである。