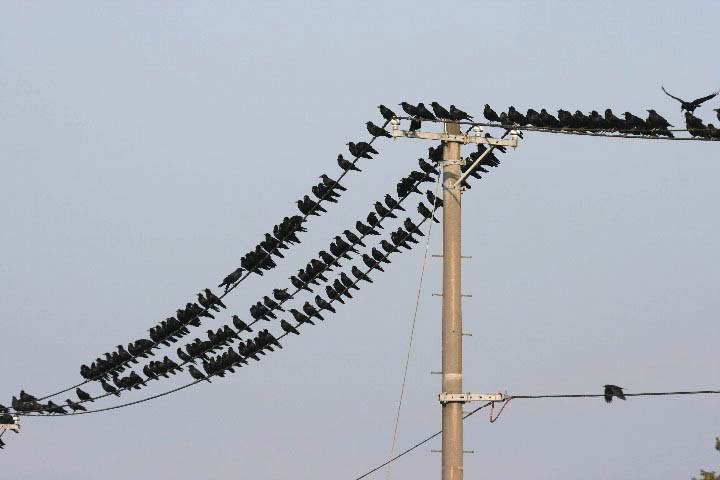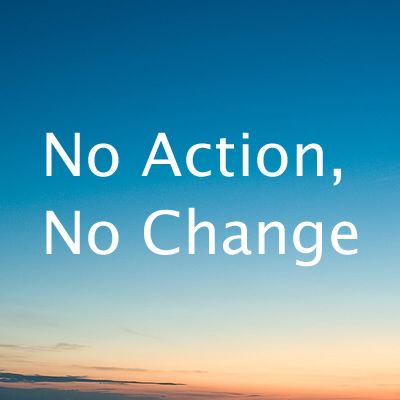2015年介護報酬改定の目玉の一つとして通所リハビリテーションにおける「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」と「生活行為向上リハビリテーション実施加算」が挙げられる。
これらの加算の単位と主な要件は、以下の通りである。
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)
・開始日から6月以内 1,020単位/月
・開始日から6月超 700単位/月
主な要件
(1)リハビリテーション会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を、会議の構成員である医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記載すること。
(2)通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
(3)通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して6ヶ月以内の場合にあっては1ヶ月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見なおしていること。
生活行為向上リハビリテーション実施加算
利用開始日から起算して3月以内の期間に行われた場合 2,000単位/月
利用開始日から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 1,000単位/月
主な要件
通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定していること。ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合は、算定しない。
生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後に継続利用する場合の減算
生活行為向上リハビリテーション実施加算の実施後の翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する。
二つの単位数は非常に高く設定されており、厚生労働省の強い政策的誘導を感じる。
今後の通所リハビリテーションのあるべき姿を、加算によって表現したと言える。
全国の通所リハビリテーション事業所は現在、この二つの加算をどのように取るべきかについて非常に頭を悩ませている。

筆者のところにも多くの相談が寄せられているが、次のような相談内容が多い。
1.医師のカンファレンスの参加、利用者、家族へのリハビリテーション計画の説明が困難
2.結局、医師の代わりにセラピストが多くのことを仕切ることになり、業務負担が増加する
3.書類上の帳尻を合わせて、おけば加算が取れると上司やオーナーが言っている
4.利用者の多くがレスパイト目的での利用であるため、生活行為向上リハビリテーションに該当する方が少ない
5.今まで、利用者と接したことがない医師が、リハビリテーションに関する主治医になれるとは思えない
と様々である。
これらの問題はなぜ生じるのか?
それはまさに、新しいビジネスモデルの転換に関して組織のケイパビリティーが著しく不足しているからである。
ケイパビリティとは、企業が全体として持つ組織的な能力を示す。
環境変化が著しいヘルスケア産業では、競争戦略による差別化が最大の課題である。
ケイパビリティを高めることで、戦略の実現性で他社に差をつける、地域や市場における持続的な競争優位を確立することができる。
おそらく、2018年度診療報酬・介護報酬ダブル改訂においては、通所リハビリテーションは二段階に分けられる。
リハビリテーションマネジメントや生活行為向上リハビリテーションを提供できるリハビリテーション施設としての通所リハビリテーション
食事、入浴、レクレーションと質の悪い個別リハビリテーションを提供する送迎付きの入浴施設的通所リハビリテーション
に分別される。
当然、後者は経営的には厳しくなる。
そして、通所介護と通所リハビリテーションの統合の議論も本格化してくる。
時代背景に合わせたビジネスモデルを導入する時は、権力闘争、組織間対立、コンプライアンス低下が起こる。
大塚家具のように成功体験があるビジネスモデルがあると、さらにビジネスモデルの新生には大きなエネルギーが必要となる。
大塚家具の問題は、単なる親子の問題ではない。
企業統治や組織のケイパビリティーに関して、手を抜いていたからあのような騒動に発展したのである。
一部上場の大企業ですら、ビジネスモデルの転換には苦労する。
ましてや、家業経営体質やワンマンオーナーの通所リハビリテーションは、ほぼガバナンスは正常に作用していないと考えても良い。
通所リハビリテーションの事業モデルの転換には2018年までの3年間の猶予が与えられた。
病院、診療所、老人保健施設の副業的な収入源として運営してた事業所には修羅場の3年間である。
医師がリハビリテーション会議に参加しない、利用者のリハビリテーション中の話しかけで同意を得たことにする、リハビリテーション会議をセラピストだけで行う、対象とする利用者をいつまでも変えられない・・・・・などのことをやっている通所リハビリテーション事業所は、2018年に、通所リハビリテーション業界から退場を命じられるだろう。