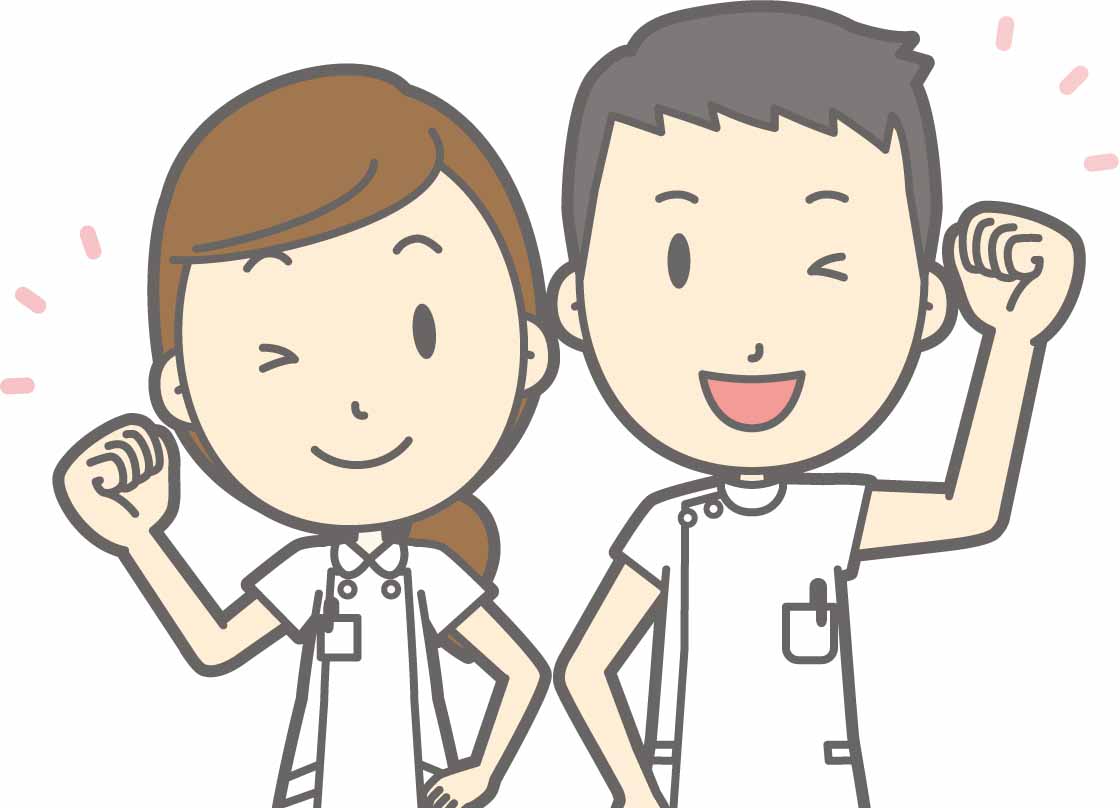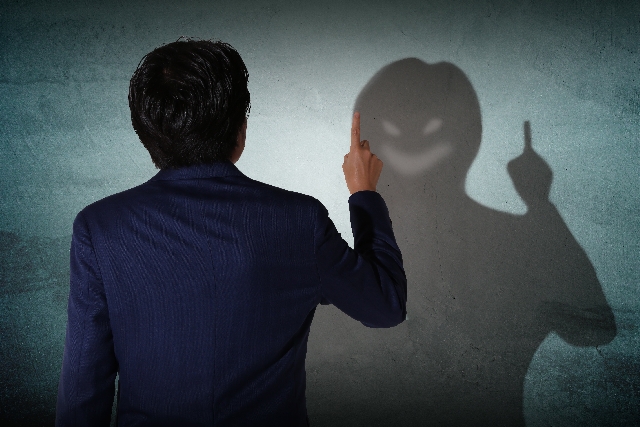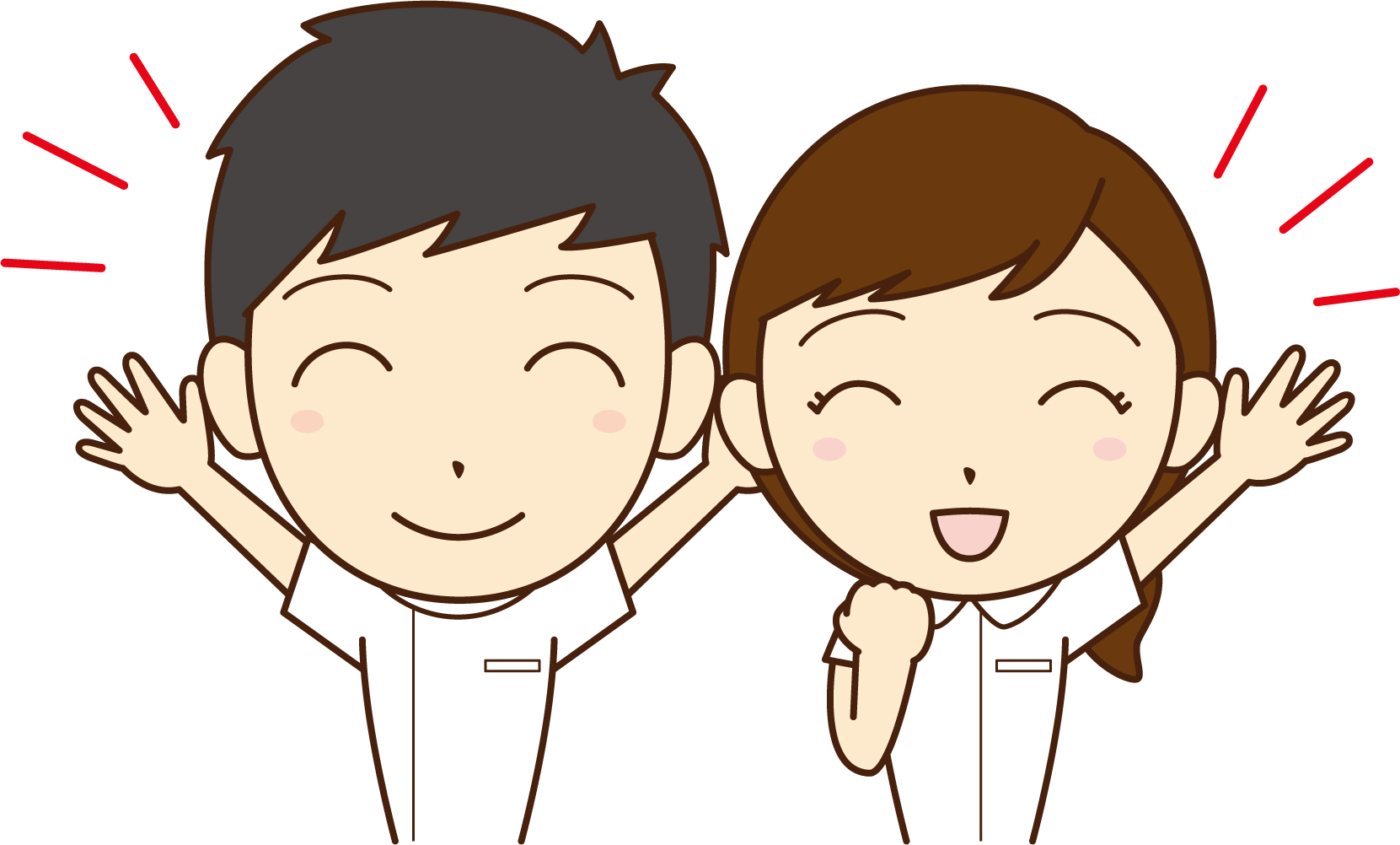2025年に向けた医療・介護制度のパラダイム転換が本格的に始まっている。
経営課題は山積しており、課題の解決なくして次期介護報酬・診療報酬改定は乗り切れない。
各分野における経営課題をあげると
病院
在宅復帰推進・在院日数短縮・病床機能報告制度への対応・介護との連携・医師や看護師の確保・電気料金増加への対策・稼働率の向上
診療所
外来患者の確保・大規模診療所への転換・基幹病院との連携・夜間対応・在宅診療報酬減額への対応・医師、看護師、セラピストの確保・介護の多角経営・
介護事業所
利用者の確保・介護報酬減額への対応・診療所、ケアマネージャー連携・在宅復帰の受け皿機能・介護施設間連携・重度者への対応・介護職の確保と教育
などが挙げられる
このような経営環境を、経営者一人で乗り越えることは不可能である。
最低、二名のブレーンが必要である。
しかし、日本の多くの病院・診療所・介護事業所は中小企業レベルのマネジメントスタイルであり、家族経営中心の家業気質が抜けていない。
今後は、この家業気質が今後の経営のボトルネックになる可能性が高い。
家業では、家族や身内の保身を背景とした経営判断が行われやすく、環境変化に対応することが難しい。
今後、生き残る医療・介護事業になるためには、経営と家業を分離する家業分離経営を実現し、優秀なブレーンを雇用する必要がある。
オーナーや創業家のマネジメントだけで、乗り切れない時代になった今日、医療介護の従事者はマネジメント能力を磨く必要がより高まっている。
医療・介護従事者が医療技術・介護技術だけを提供していれば良い時代は終焉している。
マネジメントに関する能力を高めることは、一労働者としての生き残るためにも必要である。