キャリアデザインやキャリアアップについて考える場合、「未来のこと」を一生懸命に計画する方が多いのではないかだろうか?
近い将来、〇〇な資格を取りたい。
次の職場は、〇〇ができることに行きたい。
大学院に行って、〇〇について勉強したい。
など未来について考えることがキャリアデザインであると考えている人は多い。
実は、キャリアを考える上で重要となるのは未来のことより、「過去のこと」である。
自分の価値観や自己概念をより反映したキャリアを開発できる人の特徴は 「過去のこと」に対する向き合い方が非常に上手であるということである。
「過去のこと」に向き合うことが上手という方は以下の2つについてしっかりと対応ができる。
1)過去から現在まで、人生や仕事において自分が置かれている状況を明確に把握している
2)過去から現在までの状況に対して、感情だけでなく、その状況に対して意味づけをしている
例えば、 「病院で嫌な仕事を与えられ、仕事を辞めたいと考えている。しかし、年齢も47歳で、今から転職するかどうか悩んでいる」 というキャリア上の悩みをセラピストが持っていたとする。
このような場合に、
1)今の病院で働いてきた中で、獲得してきた知識、経験、技術を整理する 2)嫌な仕事を与えられたことに対してどのような気持ちになっているのかを整理する
3)年齢が47歳が自分にとってどのような意味を持つのかを整理する
4)今から転職することで具体的にどのような不安があるのかを整理する 5)1)~4)の内容を統合した上で、自分は何に悩んでいて、そしてどの様にしたいのかを考える。
これらの一連の思考が、発展的で主体的なキャリア開発には欠かせない。  キャリアを考えるうえで重要なのは 「経験の再現」と「意味の出現」の繰り返し である。
キャリアを考えるうえで重要なのは 「経験の再現」と「意味の出現」の繰り返し である。
過去の経験をしっかりと振り返り、 それに対して、どのような感情や気持ちを持っているのか。
それを踏まえて、自分は将来どうしていきたいという気持ちを持っているのか?
この繰り返しをすることで、自己概念を反映したキャリアを選択することができるようになる。
株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授





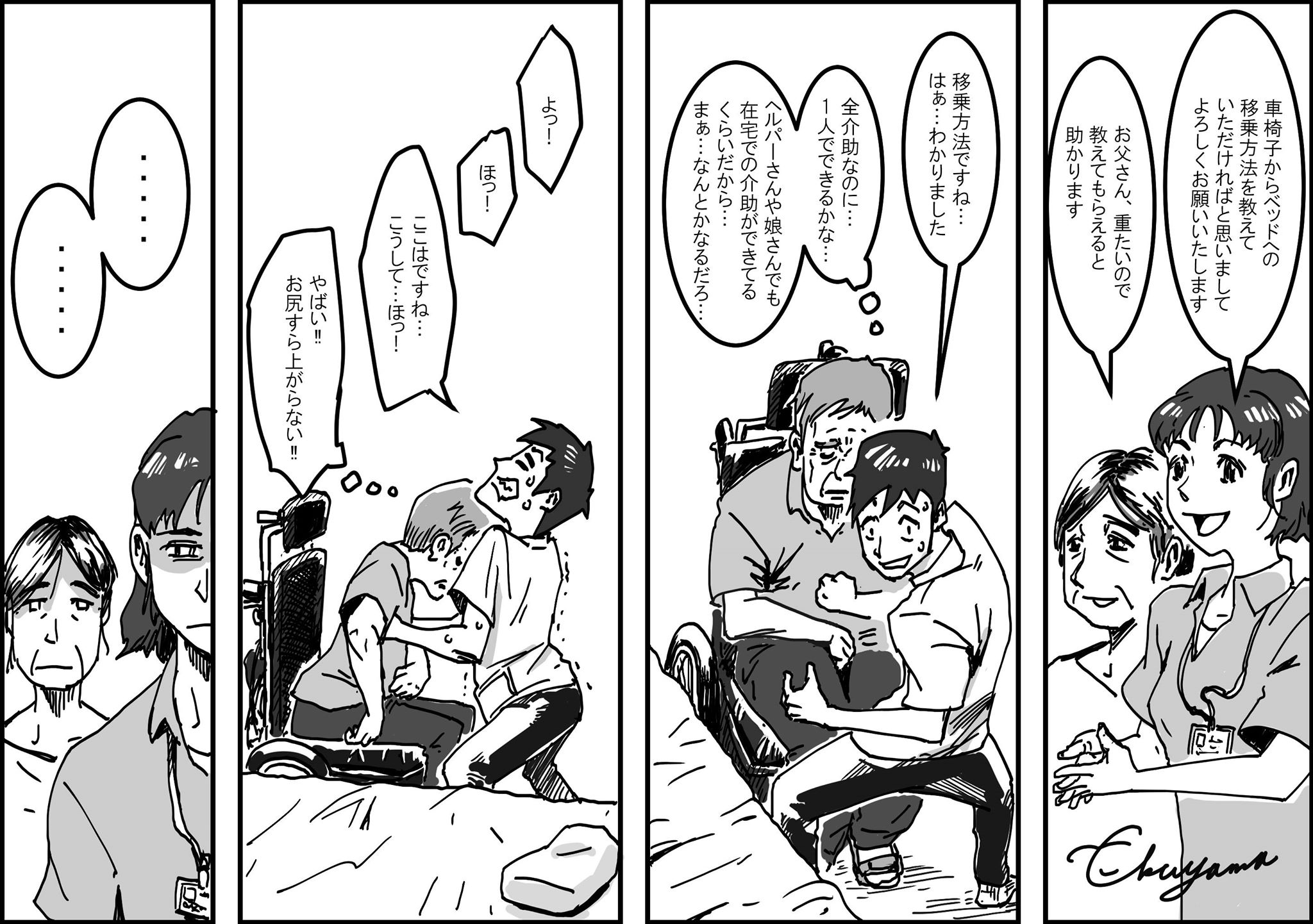 無断転載禁止
無断転載禁止


 株式会社WorkShift 代表取締役
株式会社WorkShift 代表取締役
