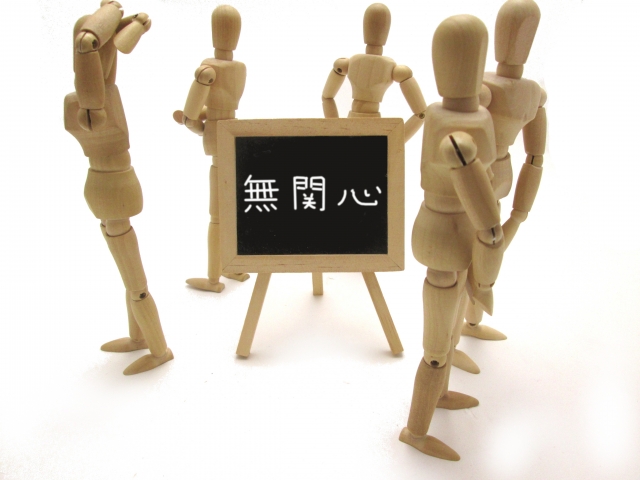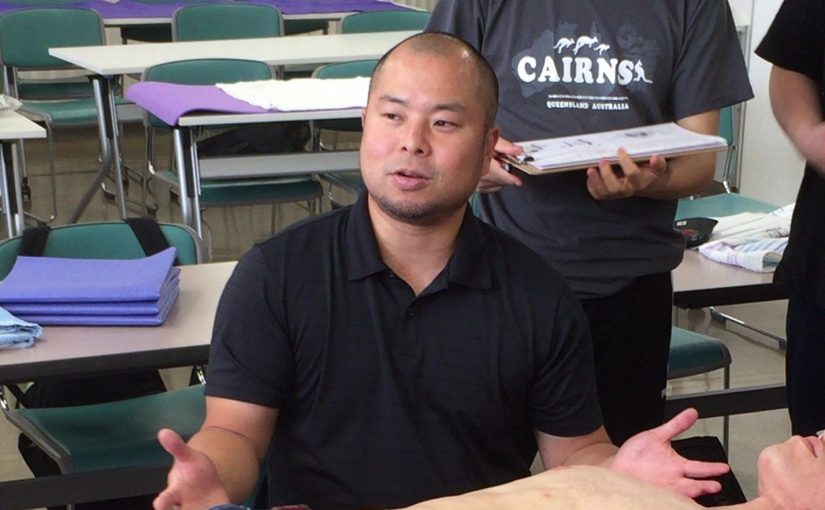企業の存在目的は利潤の最大化を通じて社会に貢献することである。
利潤の最大化には短期的な手法と長期的な手法があり、真の社会に必要とされる企業になるためには、長期的な手法を用いることが重要である。
短期的に会社の利潤を最大化しようとすると、経費を削減するいわゆるリストラクチャリングを中心とした手法が有効である。
リストラクチャリングには利益の確保や株主などへの説明責任などのメリットもある一方で、雇用や取引先への悪影響が大きいというデメリットを伴う。
リストラクチャリングでは雇用や取引先との関係を破壊することから、結果的に社会や地域にとって必要とされない企業となる可能性が高まる。
社会や地域から愛され必要とされる企業となるためには長期的な手法を用いて企業経営を行って行くことが重要である。
長期的な手法で大切なことは社会や地域から信頼を得ることができる「企業倫理」の実践を通じた経営が必要である。
つまり、「企業倫理」とは企業が成長していくための戦略と言える。
企業倫理を企業成長の武器として使うことが長期的な利潤の最大化に繋がる。
医療機関や介護事業所が短期的利益のために、サービスの品質を無視し、事業を運営すれば地域の利用者や介護支援専門員から反感を買う。
悪い評判はその医療機関や介護事業所を利用するインセンティブを消失させる。
一度生まれた悪い評判を打ち消すのはほぼ不可能に近い。
「企業倫理」を戦略的に実践することで、利用者や介護支援専門員との良好な関係を維持することができ、その結果、事業運営も発展する可能性が高い。
執筆者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)
関西医療大学保健医療学部 助教
関西学院大学大学院 経営戦略研究科