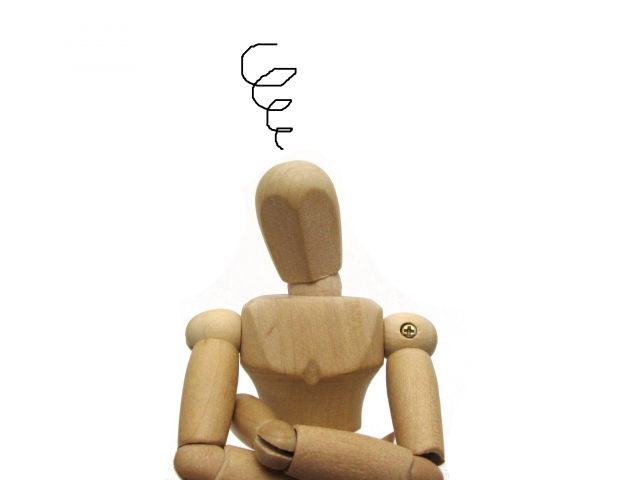リハビリテーションの現場には、知識も技術もあり若手から慕われているリーダー格のセラピストがいることが多い。
そのため、そのリーダーは若手に良くも悪くも影響を与え、組織にとって油断ならない存在となることがある。
このようなリーダーは、若手や周囲のセラピストに対して、リーダーシップを発揮し組織や業務の在り方に対して異議を唱えることもあり、まさに現場の代表者として活動する。
本人は「自分が素晴らしいことをしている」という自覚症状があり、「組織や個人に対して異議を唱えること」への活動を増長させることが多い。
しかし、ここには重要な視点が抜けている。
リーダーとして優れていても部下として優れていなければ、組織からの評価は得られないという事である。
部下として優れているという事はどういうことか?
それは、組織の一員としてチームプレイに徹し、組織の方向性を建設的な意見を述べることで調整していくことである。
リーダーシップが優れている人の組織に対する異議申し立ては、組織の弱点や上司の欠点を指摘することが多い。
しかし、組織の弱点や上司の欠点を指摘するだけでは、それはただの「クレーム」「文句」である。
優れた部下は組織の弱点や上司の欠点を補うために自分にはどのようなことができるか?を考え、建設的な意見を述べることができる。
リーダーとして優れていても部下として優れていなければ、組織からの高い評価は得られない。
あなたの職場にはいないだろうか?
クレームや文句は得意だが、チームのために行動できないリーダーの皮をかぶっているセラピストが。
執筆者
高木綾一

株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術)
関西医療大学保健医療学部 助教
関西学院大学大学院 経営戦略研究科