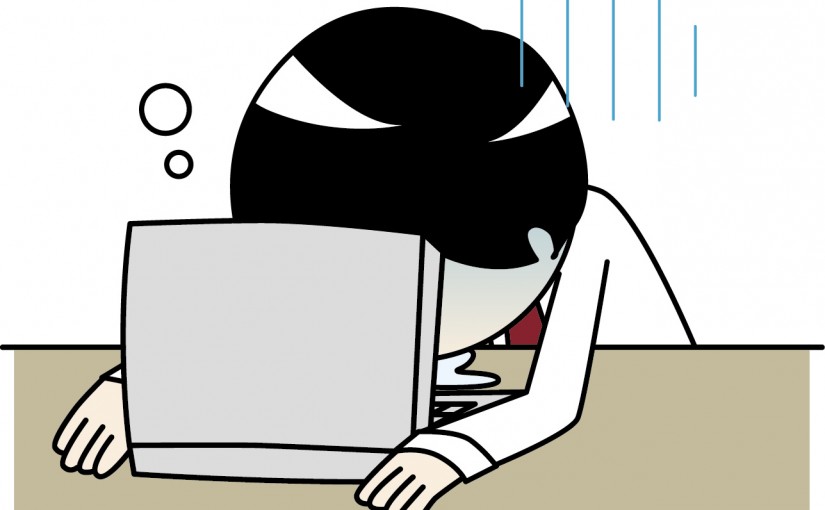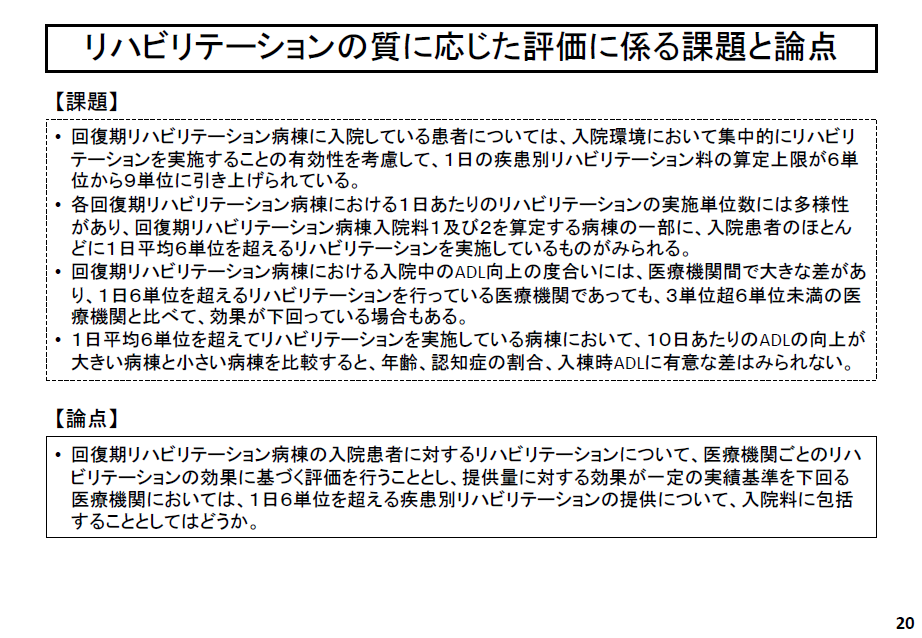世の中の95%以上のセラピストは会社に雇用されている。
つまり、自分の能力を勤めている会社に購入してもらい、会社から給与を支払ってもらっている。
では、その能力は自分の勤めている会社以外でも、認めてもらえるだろうか?
日本社会は激変しており、終身雇用の崩壊、企業存続率の低下など労働者を取り巻く環境は一層熾烈を極めている。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士も同様に厳しい環境で働く者が増えており、給与が上がらない、病院が買収された、介護事業所が倒産した、仕事のノルマが厳しいなどの話には枚挙に暇がない。
このような状況において、セラピストはどのように働いていけば良いのだろうか?
エンプロイアビリティという言葉を知っているだろうか?
エンプロイアビリティーには3つの意味がある。
1.所属する組織に雇われ続けるためのエンプロイアビリティ
現在の会社で求められる役割と成果を達成していれば、会社が存続する限り会社に所属することができる。時代変化に応じて会社に必要とされる価値を生み出し続ける能力が必要となる。
2.好条件での転職を可能にするためのエンプロイアビリティ
優れた専門能力を持ち、他の会社でも高い成果をだせるだけの社会に通用する普遍的な能力を持つ人は、好条件で転職や起業をすることができる。
3.やりたい仕事をやり続けるためのエンプロイアビリティ
自分のやりたい分野の能力を確立し、さらにその分野における人脈も形成し、長期間にわたりやりたい仕事を続ける。
これらのエンプロイアビリティを開発していくことが、これからの時代で働くセラピストには重要となってくる。
多くのセラピストは「所属する組織に雇われ続けるためのエンプロイアビリティ」のみを意識しているのではないだろうか?このことすら意識していなければ、論外であり、100%淘汰されるセラピストになる。
確かに、「所属する組織に雇われ続けるためのエンプロイアビリティ」は重要であるが、会社が存続しなくなった時や会社を辞めたくなった時に、このエンプロイアビリティのみだけでは対応できない。
したがって、「好条件での転職を可能にするためのエンプロイアビリティ」と「やりたい仕事をやり続けるためのエンプロイアビリティ」を高めておく必要がある。
わかりやすく言うと、今すぐ会社を辞めても、すぐに働ける場所を確保できるセラピストはこれらのエンプロイアビリティが高いということである。
会社の看板だけで働いていると、自分の看板を作らなくなる。
自分の看板を掲げ、そこに受注が入る仕組みを作ることが、これからのセラピストには求められている。