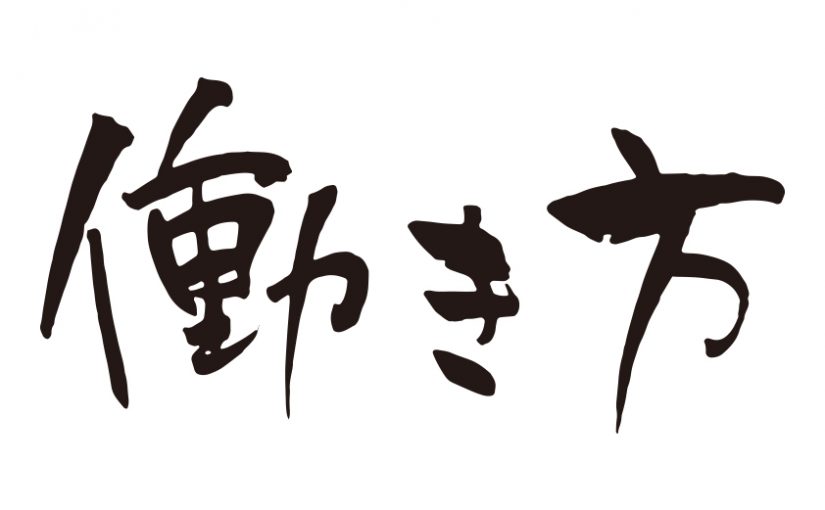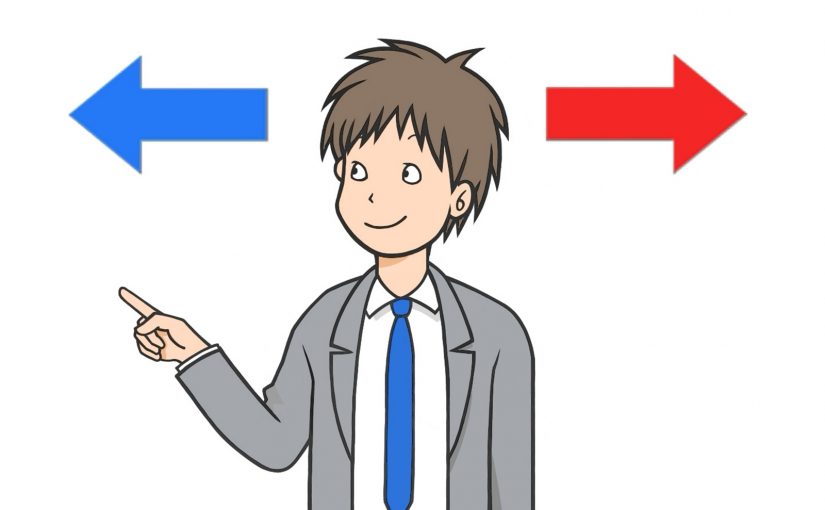人は何のために働くのか?
医療・介護従事者は専門職である前に、「人」である。
「人」がなぜ働くか?という原理原則を理解することは、人材や組織のマネジメントを行う上で極めて重要である。
今回は「人」が働く理由を考える上で重要な概念である「キャリア・アンカー」を紹介したい。
これはアメリカの心理学者エドガー・シャインによって提唱 された概念である。
キャリア・アンカー
職業、職種、勤務先などを選択する際に判断基準となるものであらゆる人が持っている。
アンカーとは日本語で「碇」を意味し、船を固定させるものである。
言い換えると、自分の人生の中で「優先度が高いもの」「譲れないもの」を示す。
どのような仕事に就こうとも「キャリア・アンカー」という自己概念が仕事の中で顕在化してくる。
キャリアアンカーには8つのものがある。
・専門
企画、販売、人事、エンジニアリングなど特定の分野で能力を発揮することに幸せを感じる
・経営管理
組織をマネジメントし、対人関係の調整や業績の拡大に魅力を感じる
・自立
自分のやり方で自由なスタイルで仕事をすることに魅力を感じる
・安定
労働条件などの福利厚生の安定を求める
・企業家的創造性
新しいものを創り出し、困難を乗り越えることに幸せを感じる
・社会への貢献
社会という公共なものへ貢献したいという気持ちが強い
・チャレンジ
大きなリスクや障害を乗り越え、不可能と思える事柄に挑戦することが楽しい
・全体性と調和
プライベートと仕事の調和を図ることが最も重要と考える
これらの8つのいずれかのキャリア・アンカーを持つ人が組織内に存在している。
比較的多いのは「全体性と調和」のキャリア・アンカーである。
仕事とプライベート(家庭)が大切であるという現代の世相を示していると言えるだろう。
しかし、中には「企業家的創造性」や「専門」などのキャリア・アンカーを有する人もいる。
その場合、「企業家的創造性」の人には新規施設の開設や経営改善の仕事、「専門」の人には医療技術指導者や研修責任者が適性のある業務であると言える。
キャリア・アンカーの評価なくして組織マネジメントは難しい。
理学療法士だからこのような価値観を持ちなさい
作業療法士だからこんな風に働きなさい
看護師はこうあるべきだ
というアドバイスは、「キャリア・アンカー」を前提にしておらず、非常に乱暴なものである。
皆さんは部下や同僚のキャリア・アンカーを把握しているだろうか?