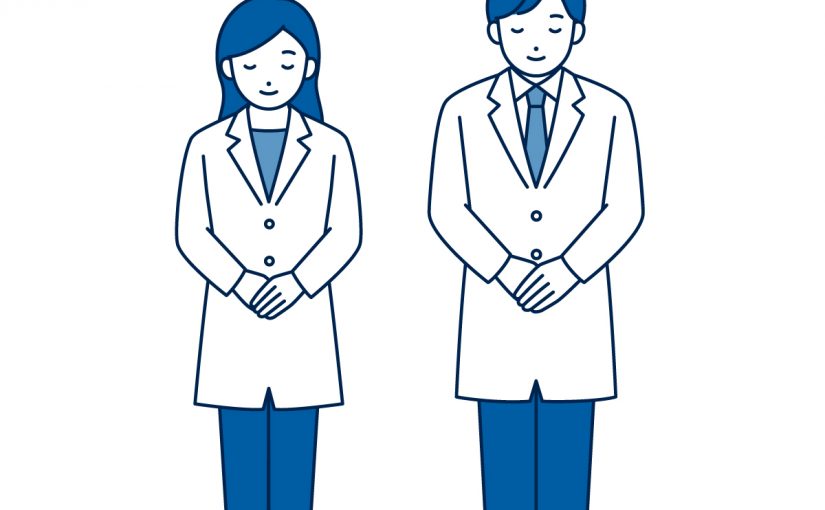現代の日本において、医療・介護分野の若手専門職――セラピスト、看護師、学生らと対話を重ねる中で、多くの者が「臨床活動」や「患者へのサービス提供」を最終目的と捉えている現実に直面する。
言い換えれば、「臨床という作業を遂行すること」自体が職業選択の動機であり、キャリア形成のゴールとなっている。
この傾向は、キャリア理論における「成長・探索・確立」のプロセスの停滞、あるいは職務中心型キャリア(Job-Centered Career)の過度な定着を示唆するものである。
本来、専門職におけるキャリアとは、自己概念の実現過程(Super, 1957)であり、環境との相互作用の中で進化するものであるべきである。
結果として、医療・介護現場では課題解決型人材よりも作業順応型人材が増加する傾向がある。
もちろん、作業を正確にこなす力は組織運営にとって不可欠であり、一定のマンパワーは社会的にも価値がある。
しかしながら、作業の延長線上からはイノベーションは生まれない。
作業はあくまで作業であり、変革を生む源にはなり得ない。
日本は、世界でも有数の経済大国でありながら、少子化・超高齢化・財政難という構造的課題を抱えている。
その一方で、衣食住に不自由しない社会保障制度の中で育った若年層は、自己実現への強い欲求や社会変革への執着心に乏しい。
これは、飢えや苦難を経験しない平和な環境の中で形成されたマインドの飽和状態である。
目標なき日常は、キャリア選択を「作業の選定」に矮小化させる。
医療・介護従事者の数は急増しており、看護師、セラピスト、薬剤師、柔道整復師、鍼灸師などの供給は今後過剰となる見通しである。
需給バランスの崩壊により、人件費は圧縮される。
にもかかわらず、多くの従事者は根拠なき安心感に包まれている。
「今の給与水準が続く」と信じる者が多いが、そこに戦略的なキャリア構築意識はない。
今、医療介護職に最も求められているのは、自分自身の仕事の意味や社会における役割を明確に持つことである。
キャリアアンカー理論(Schein, 1978)では、「奉仕・献身型」や「純粋挑戦型」といった価値観が示されており、これは、自分の中核的な価値観と社会的な貢献意識をつなぐことで、職業人生における方向性を見出すものである。
自分の役割や使命を明確にすれば、目標は自然に定まり、行動も一貫性を持つ。
結果として、日々の選択に迷いが少なくなり、ブレないキャリアを築くことが可能となる。
筆者
高木綾一
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
三学会合同呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
国家資格キャリアコンサルタント
株式会社Work Shift代表取締役
関西医療大学 保健医療学部 客員准教授
医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。
医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。
著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。
経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。