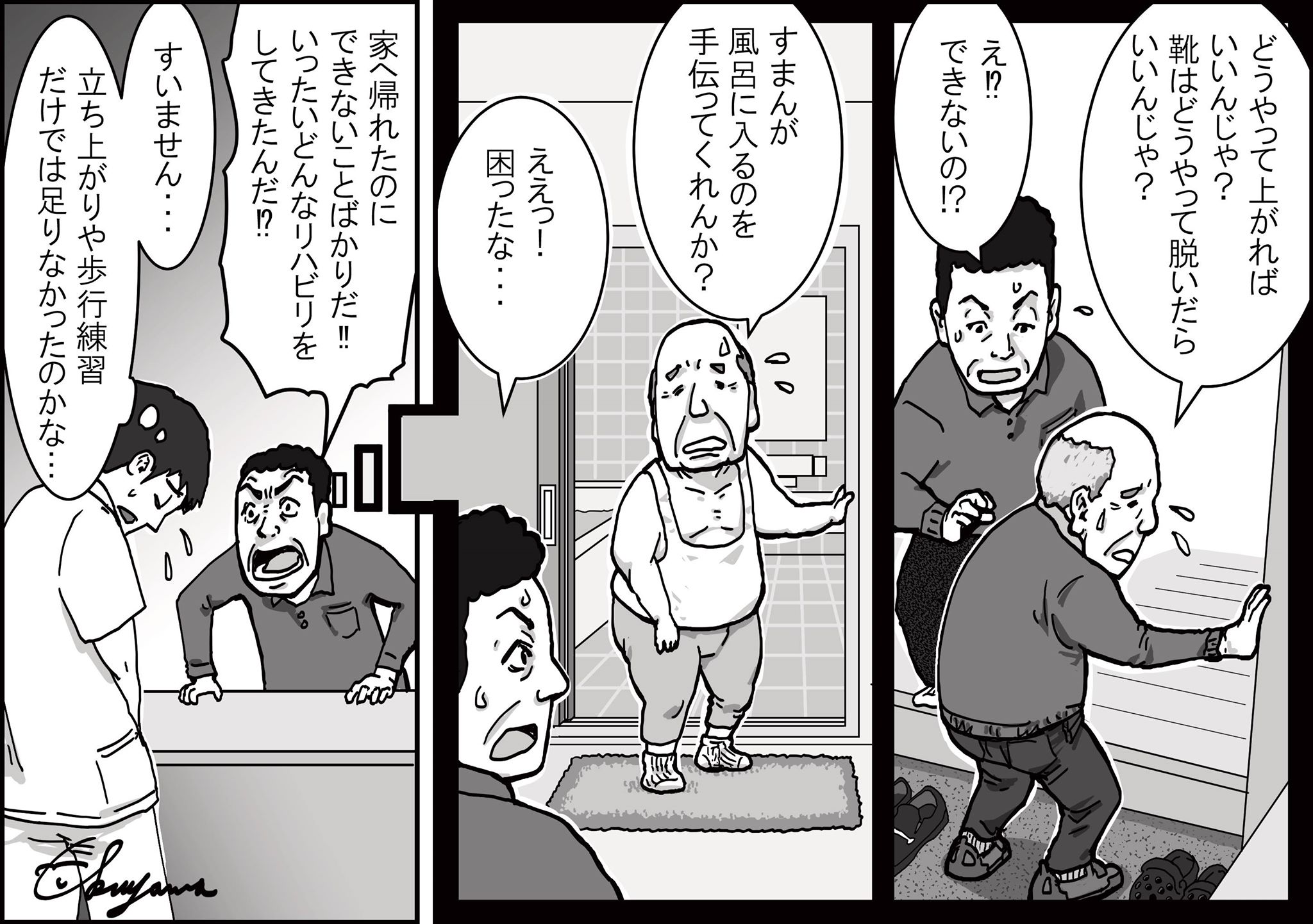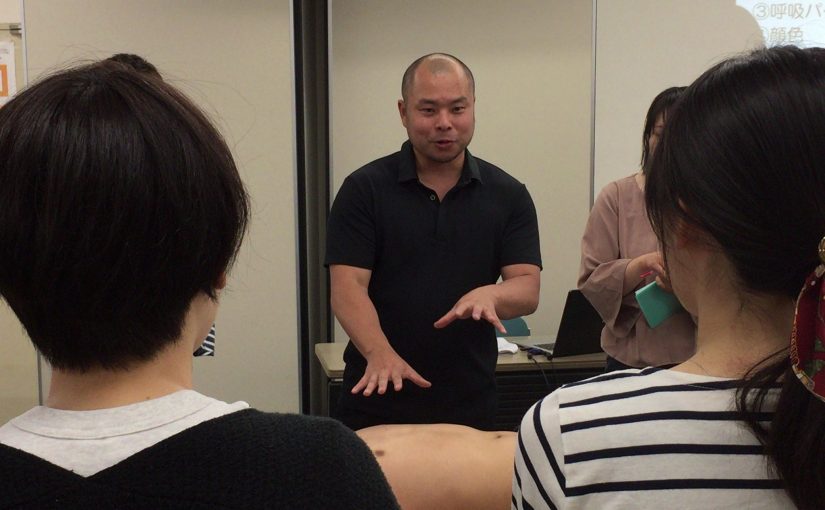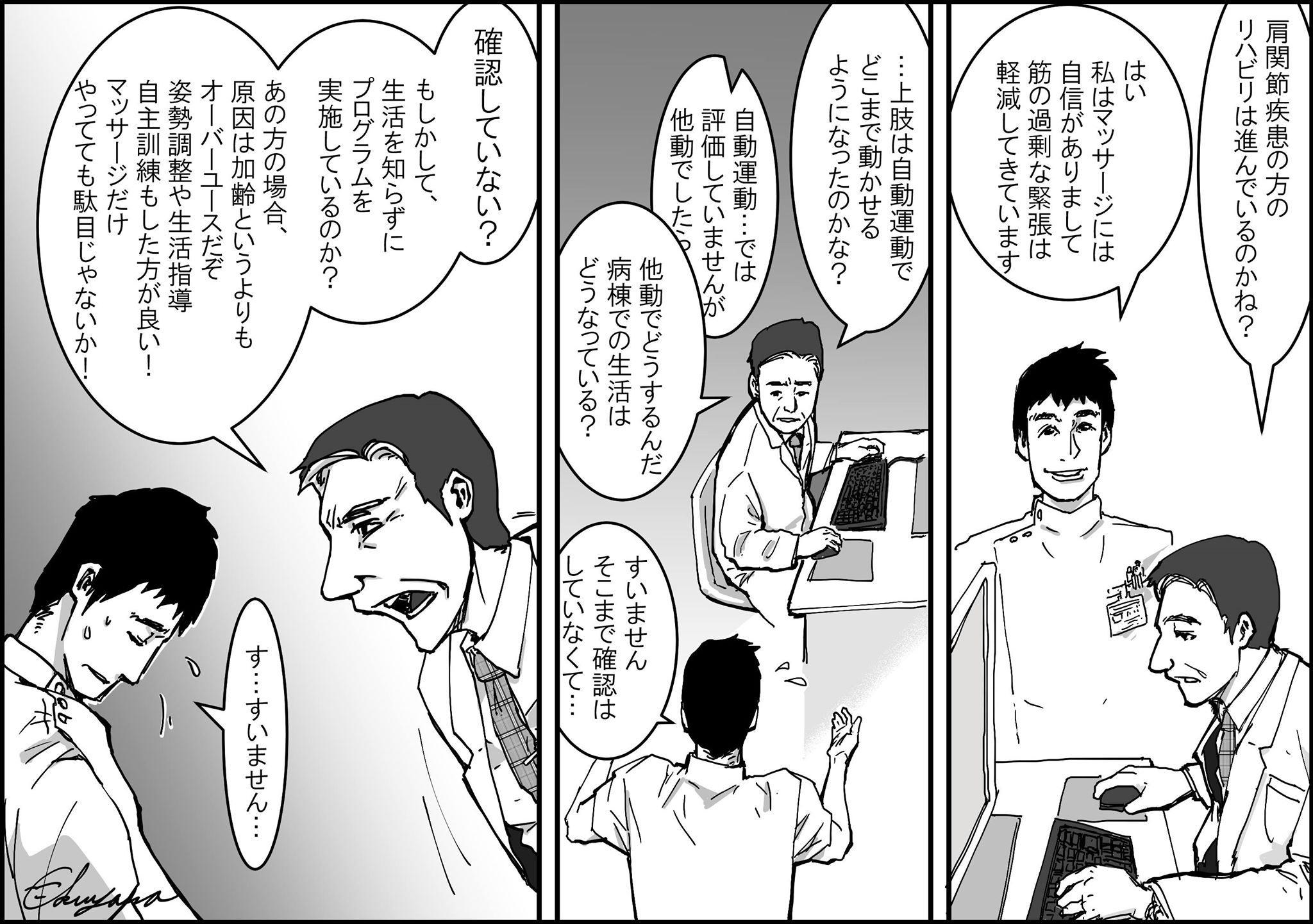仕事内容に魅力がなくなった
仕事へのモチベーションが下がった
人事異動があり、職場が変わった
結婚をして子供が生まれた
新しいプロジェクトの関与を命じられた
体調を崩し病気になった
など・・・人生には様々な節目がある。
こういった節目では、「今後の生き方」や「仕事に対する気持ち」について考えるようになる。
キャリアデザインにおいて、「節目」は非常に大切なイベントであり、大きく人生や働き方を変える契機となる。
節目で自身のキャリアを決めるのは、会社、上司、友人ではなく、人生の主人公である「あなた」でなければならない。
すなわち、自己決定こそが自身の人生を切り開く第一歩目となる。
だた、その自己決定には様々なものが影響する。
会社、上司、友人、恩師、組織、所属するネットワーク、家族、両親、妻、子供・・・。
こういった人たちからの意見や思いを大切にした自己決定である必要がある。
つまり、自己決定の裏には相互依存が存在するということである。 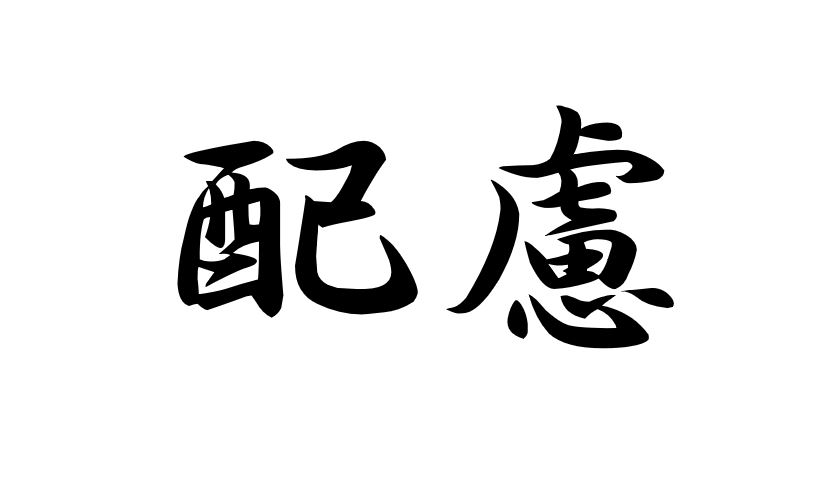 「自身の生き方を貫く」ことが、キャリアデザインであるという風潮や意見があるが、自己決定と相互依存を意識することが真のキャリアデザインである。
「自身の生き方を貫く」ことが、キャリアデザインであるという風潮や意見があるが、自己決定と相互依存を意識することが真のキャリアデザインである。
自己決定が多くの人を幸せにしない可能性や社会に悪影響を与える可能性がある。
他者に対する配慮を取りながらの自己決定をしていく姿こそ、キャリアデザインでは重要である。
起業したい 転職したい 大学院に進学したい 退職したい などの決定をする時は、その決定により影響を受ける人に事前に説明し、理解をしてもらう努力が必要である。
自己決定の裏に相互依存がある。 これがキャリアデザインの本質である。
株式会社WorkShift 代表取締役
あずま整形外科リハビリテーションクリニック
茂澤メディカルクリニック
たでいけ至福の園
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)(脳卒中)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学 客員准教授