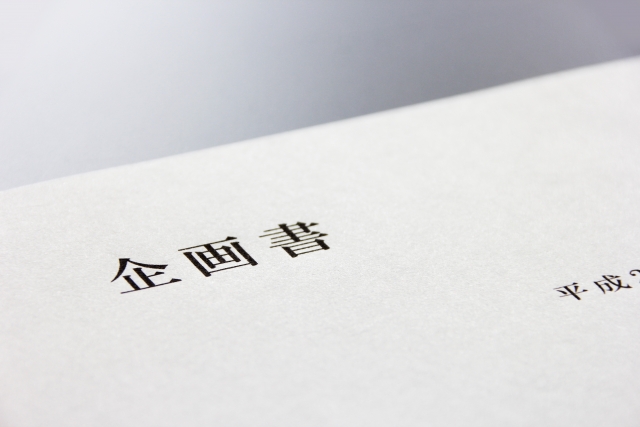リハビリテーションとは、全人間的復権である。
その人がその人らしく生きていくことを支えていく概念がリハビリテーションであり、その実現を支援するサービスがリハビリテーションサービスである。
日本は世界に類を見ない先進国であり、物質的な繁栄が著明である。
40年~50年程前の日本は物質的にもまだ、恵まれておらず、国民は国の経済的繁栄こそが幸せであると考え、懸命に働き、今の日本を作った。
先人たちの尋常ではない努力で、日本は小さい島国ながらも世界第三位の経済大国となり、国民の生活レベルも極め高い国となった。
国民の衣食住がこれだけ充実している国は実は世界では少数派である。
このような先進国では経済的な発展や物質的な繁栄が当たり前のように感じ、人が幸せを感じる尺度は変化する。
このような社会を成熟社会と呼ぶ。
成熟社会では
人間関係を良好に保ちたい
心が通う仲間が欲しい
自分自身の存在を認めてもらいたい
自分のやりたいことをやってみたい
という人間にとって高次元な欲求が高まってくる。
現在の日本は超高齢化社会となっており、高齢者の医療福祉政策が急ピッチで進んでいる。
医療・看護・介護・リハビリテーションと様々な分野で対策が打ち立てられている。
特に、リハビリテーションは全人間的復権の概念であることから、あらゆる分野で必要とされるものである。
リハビリテーションが一般的な社会インフラになる前の日本では、リハビリテーションとは機能障害やADLの回復を目指すものであった。
当然、機能障害やADLの回復は全人間的復権に必要なものであるため、それらは依然として重要である。
それに加え、成熟社会では、承認欲求や自己実現などの支援も求められる。
時代が変われば、求められる全人間的復権の内容も変わる。
今の時代は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は機能障害やADLの回復を促せる知識や技術に加え、より高次元の患者、利用者の欲求や想いを支える技能が求められる時代になっている。
こういった背景とともに生まれてきた概念である地域包括ケアや地域リハビリテーションは、より質の高い理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の能力を求めている。