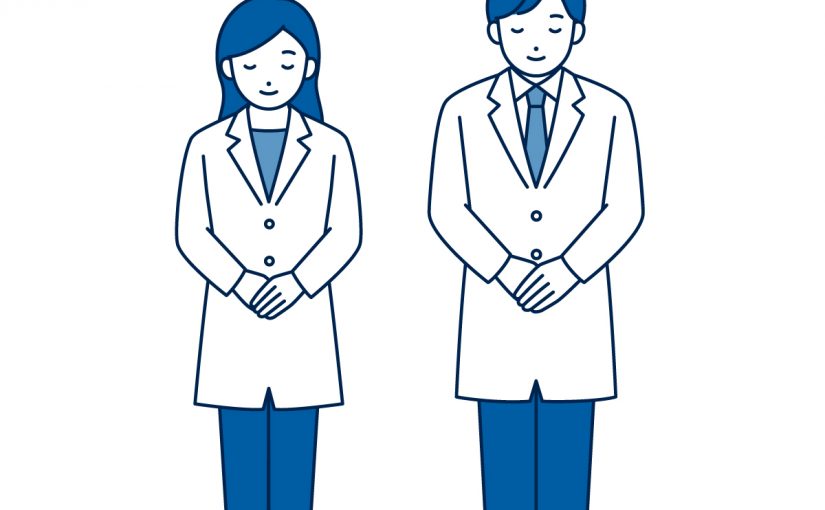医療・介護業界は現在、大きな転換期を迎えている。
地域包括ケアシステムの構築、少子高齢化への対応、公的財源の制約、そして介護保険事業への参入促進といった社会的背景を受け、異業種による医療・介護分野への参入が全国的に拡大している。
特に、居住系施設、訪問看護、訪問介護、デイサービスといった在宅支援系サービスにおいては、医療法人ではなく一般企業が経営母体となるケースが増加しており、2025年以降の高齢者市場の成長を見据えた民間企業の進出が顕著である。
このような異業種参入は、単なる業界拡大に留まらず、社会課題解決に向けたビジネスモデルの革新(イノベーション)を生み出す可能性を秘めている。
一方で、医療・介護業界特有の制度や職能理解が不十分なまま安易に参入した場合、コンプライアンス違反、医療・介護事故、経営の早期崩壊など、深刻なリスクを伴う可能性があることを忘れてはならない。
医療・介護事業は、公的保険制度のもとで厳格に運用される特性を有し、医師、看護師、介護士、理学療法士といった高度な専門職を組織内に抱える必要がある。
したがって、この分野における事業経営には、単なるマネジメントスキルのみならず、医療福祉制度に対する深い理解と、高度専門職の価値観や行動特性を適切に把握した上での組織運営力が求められる。
なかでも、参入企業が陥りがちな最大の失敗要因として、「採用段階における企業理念と専門職の価値観のすり合わせ不足」が挙げられる。
施設開設のスピードを優先し、看護師や介護職、リハビリ専門職などの採用を急ぎすぎた結果、企業理念と合致しない人材が組織内に流入し、職場内の対立、チームの機能不全、さらには法令違反へとつながる事例が散見される。
医療・介護事業の中核は「人」であり、とりわけ専門職との理念共有と信頼関係の構築が経営の成否を分ける決定的な要素である。
したがって、異業種がこの領域に参入し成功を収めるためには、専門職との継続的な対話と価値観の共有を怠らず、制度理解と人材育成に真摯に取り組む姿勢が不可欠である。
理念なき採用、理念なき運営の先にあるのは、必ずしも成長ではなく崩壊である。
異業種であっても、理念と専門性の融合を軸に据えた事業運営を徹底する者のみが、医療・介護業界において持続可能な成長を実現し得るのである。
筆者
高木綾一
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
三学会合同呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
国家資格キャリアコンサルタント
株式会社Work Shift代表取締役
関西医療大学 保健医療学部 客員准教授
医療・介護分野の経営戦略や人材育成に精通し、年間100回以上の講演を実施。
医療機関や介護事業所の経営支援を通じて、組織の成長と発展をサポートする。
著書には 「リハビリ職種のキャリア・デザイン」 や 「リハビリ職種のマネジメント」 があり、リハビリ職種のキャリア形成やマネジメントの実践的な知識を提供している。
経営相談・セミナー依頼はお気軽にお問い合わせください。