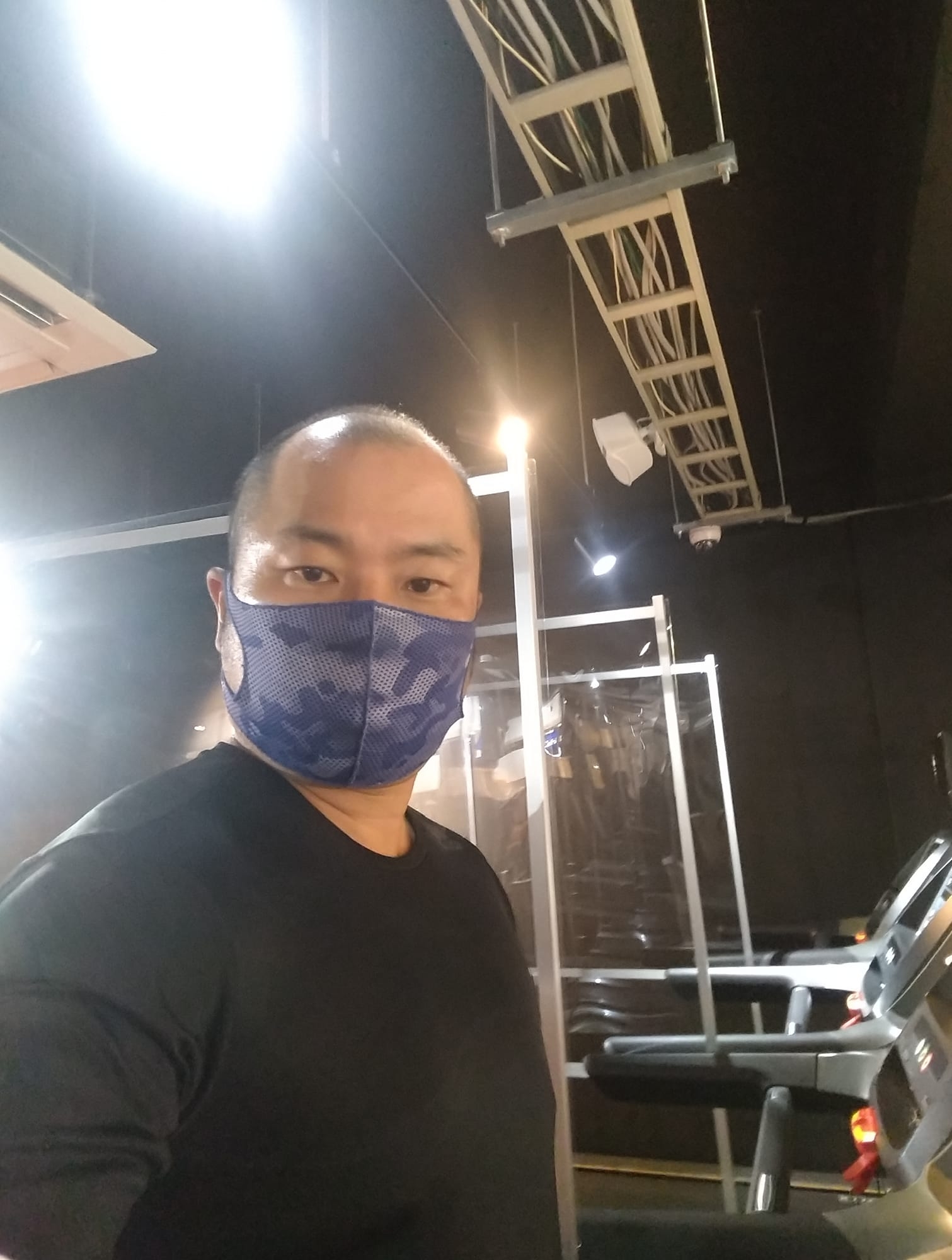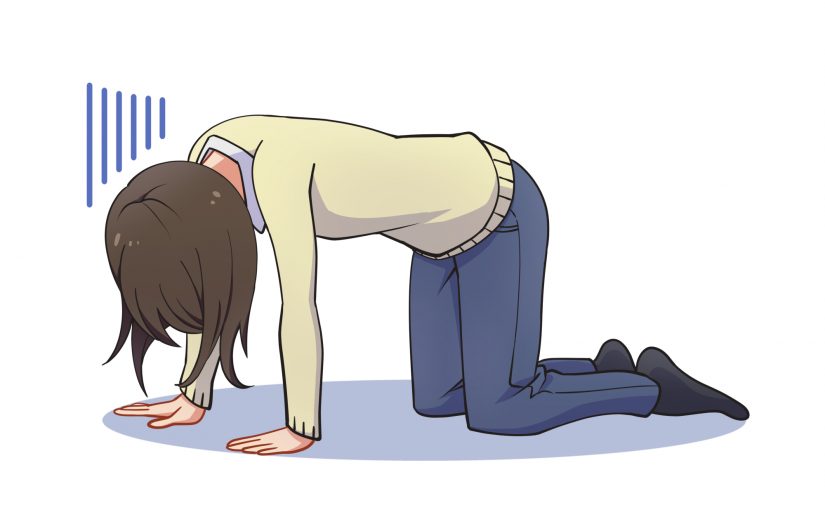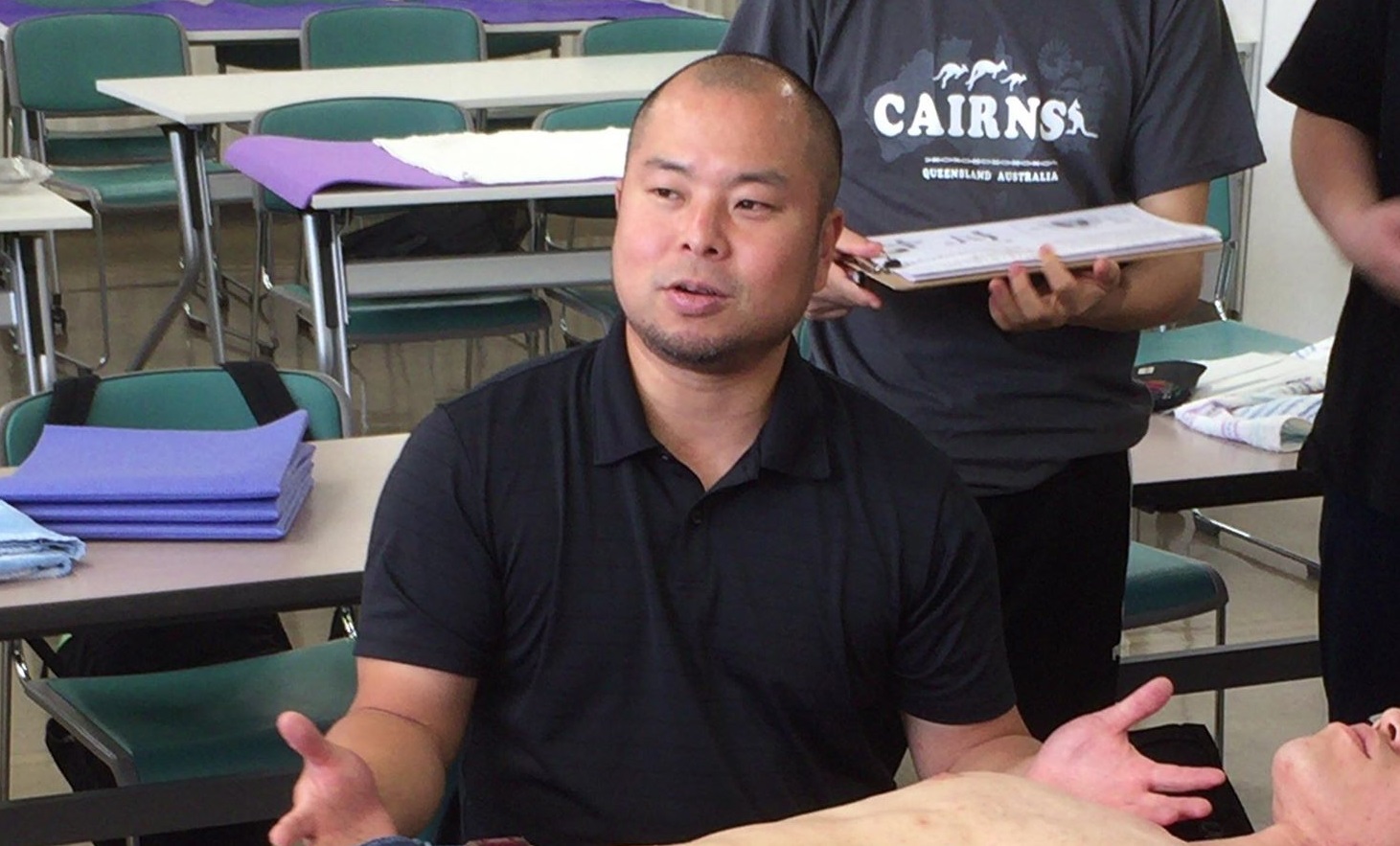2020年2月より始まった日本にほける新型コロナウイルスの蔓延は日本社会に大きな悪影響を与えている。
医療や介護の現場においても負の影響が連日報道されている。
報道されている内容はほとんど新型コロナウイルス感染患者に対する医療や介護サービスの対応への負担や病床ひっ迫などである。
しかし、現実的には新型コロナウイルスによる医療機関や介護事業所への負の影響は様々な形で表れている。
ここでは新型コロナウイルスがもたらした負の影響をいくつか紹介したい。
1)入院中の患者の様子がわからないため、家族が在宅復帰後のイメージを掴みずらい
多くの医療機関では患者が外部の人と接触することが禁じられ、面会謝絶の状態が長期間に渡り続いている。
そのため、家族が患者の状態を知ることができない。
これにより、
どれぐらいのADLの状態なのか?
どれぐらい意思疎通ができるのか?
患者の希望はどのようなものなのか?
などが把握できないまま、在宅復帰の準備が進められ、家族が困惑すると言う事例が多く認められる。
自宅に帰った時に病院スタッフから聞いていた患者の状態と異なることが多すぎて数日で在宅療養生活を諦めた事例も散見する。
2)外出自粛を過度に行ったため、内科疾患の悪化や廃用症候群が進んだ患者が増えた
高齢者の外出自粛は感染拡大の予防効果があるとは思われるが、患者の内科系疾患が増悪した事例が多く報告されている。
・デイサービスの利用をやめたことにより、認知症や歩行困難が悪化した
・病院への定期受診を延期したため、薬がなくなってしまい糖尿病が悪化した
・楽しみにしていた友達との買い物を行わなくなったため、うつ症状が進んだ
これらの事例は氷山の一角であり、外出自粛は健康面、経済面など多岐にわたる分野に大きな負の影響を与えた。
3)患者や家族から心無い言葉を言われスタッフが傷ついた
新型コロナウイルスに対する関心が高まると、高齢者や患者から医療従事者に対して差別的な発言が生じるようになった。
・訪問リハビリのスタッフに対して「他の家からウイルスをもってこないでくださいよ」と言われた
・コロナ患者を診ている医療従事者としてその人に「できるだけ近寄らないください」と言われた。
・SNSに「あの理学療法士、作業療法士はコロナにかかっているらしい」と書き込まれた
4)ワクチンを打っていない人に対する差別的な発言
新型コロナウイルスワクチンは法定接種ではなく、任意接種である。それにもかかわらず、ワクチンを打っていない人に対して差別的な言葉を投げかける人がいる。
・医療従事者なのにワクチンを打っていないのは非常識な人間だ
・ワクチンを打たないならうちの家に来ないでほしい
多くの人がワクチンを打っているため集団心理が働き、ワクチンを打っていない人を排他的に扱うことにより生じる現象である。
5)外出自粛のため外来や通所系サービスの利用者が減ることで経営者の心無い言動が増えた
新型コロナウイルスにより外来系医療機関、通所系介護事業所は利用者減少の影響を受けて経営的に厳しい状況になった。経営者は厳しい状況になると経営を守ることが第一となるため、その人の人間性が現れやすい。そのため、経営者より心無い言動が見られた。
・話し合いなどなしに突然のシフト調整・雇用調整が行われ、給料が一方的に減らされた
・パフォーマンスの低い職員を対象として肩たたきが行われた
・日頃、経営者はマーケティングに力を入れていないくせに、利用者が減ったの現場のサービスの質が悪いからだとわめかれた
・経費削減として本人の意思とは無関係に契約外の様々な仕事をさせようとする
新型コロナウイルスに対する政府の対応には賛否両論はある。
しかし、それとは別に新型コロナウイルスに対して人々が冷静に対応できたかどうかには疑問がある。
新型コロナウイルスが間接的に生み出す社会への悪影響を緩和する知恵を国民は生み出さなければならない。
また、差別やパワハラは新型コロナウイルスが生み出したものではなく、人間が生み出したものである。
差別やパワハラ防止への取り組みも一層必要であることが改めて浮き彫りになった。
株式会社WorkShift 代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
リハビリテーション部門コンサルタント
医療・介護コンサルタント
理学療法士
認定理学療法士(管理・運営)
呼吸療法認定士
修士(学術/MA)(経営管理学/MBA)
関西医療大学保健医療学部 客員准教授