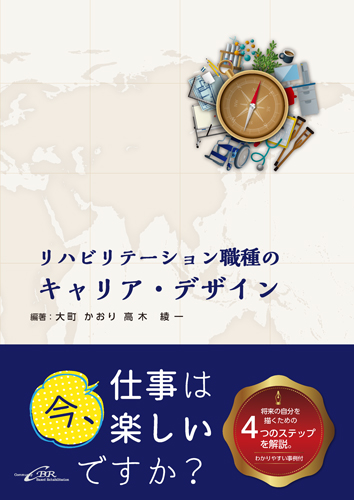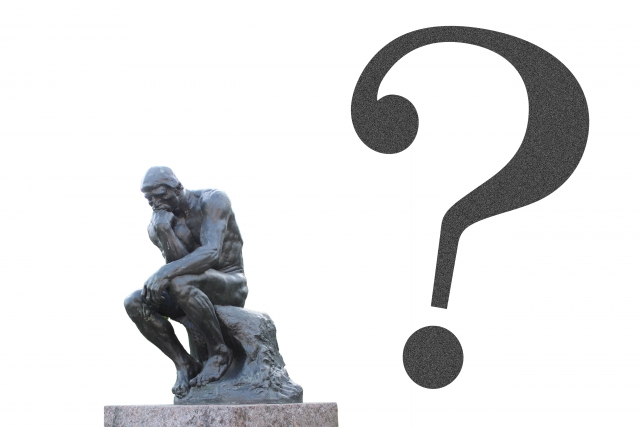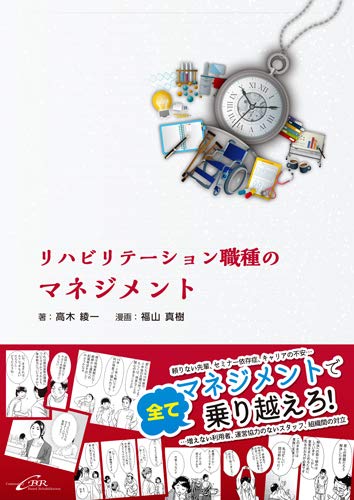こんにちわ。
株式会社Work Shift代表取締役の高木綾一です。
日頃、このブログサイトでは少々過激なことも発信しておりますが、今日は趣を変えて、弊社の5周年記念についてご報告申し上げます。
2014年12月1日に弊社は創業いたしました。
コンサルティング事業、キャリア促進事業、教育事業を中心に事業を開始いたしました。
創業後、様々な人と出会い、ご縁を頂き、多くのご案件を頂きました。
コンサルティングのクライアントは40社を越えております。
また、この5年間700回以上の教育セミナーも開催いたしました。
さらに、高木綾一のセミナー講師も5年間で600回を越えることができました。
私自身本当に運が良いと思います。
素晴らしいクライアントやビジネスパートナーと出会う事ができ、ここまで来ることができました。
皆様に支えられた5年間でございました。
これからも、自分の実力をおごらず、しかし、卑屈にもならず事業に邁進いたします。
私もそろそろ年齢も40代中盤です。
体調に十分留意しながら、事業を進めて参ります。
今後も既存事業の成長と新規事業の創出に努めます。
関係者の皆様方、本当に5年間ありがとうござました。
そして、これからも素晴らしい経験を共有させてください。
株式会社Work Shift
代表取締役 高木綾一