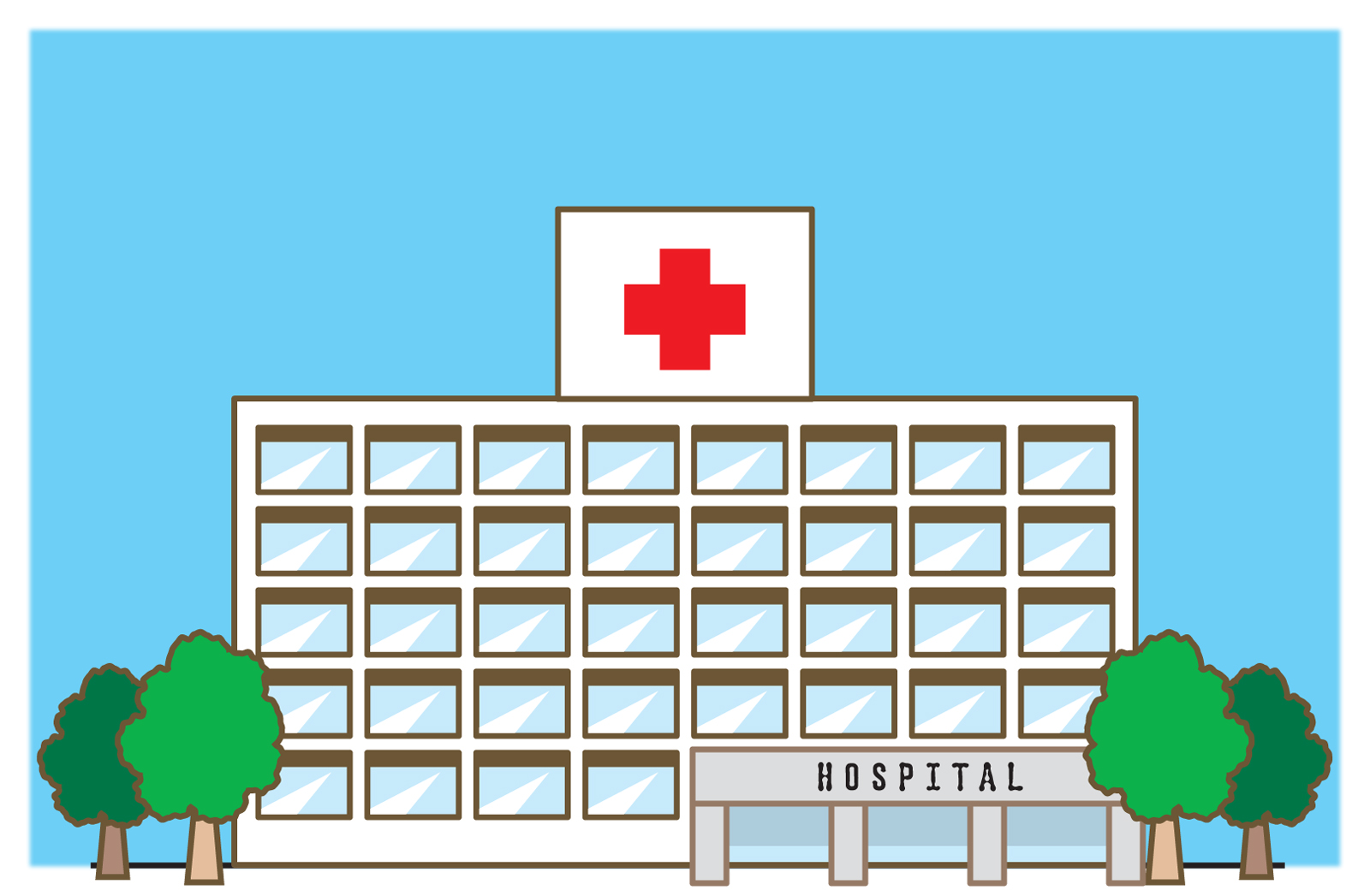日本の労働者は、厳しい局面を迎えている。
ワークライフバランスを政府は進めているものの、下流老人、長時間労働、貧困ビジネス、過労死、サービス残業など労働者の環境は厳しい状況が続いている。
日本は和を大切にする国であるため、会社は労働者を守り、労働者は会社を守るという相互依存の関係が昔より続いていた。
しかし、長期にわたる不況や社会保障費による財政圧迫により、企業は労働者を守ることより、収益を上げることを優先させる傾向が強くなった。
2000年代に入ってから、この傾向は著明となり多くの企業が労働者の好待遇を止め、労働生産性の向上を図るという政策へ舵を切った。
経済情勢が悪くなると、企業は経営状態を維持、向上させるために短期間の利益確保、内部留保の確保に傾倒する。
そのため、従業員や現場への労働負荷が増える割には、賃金が上がりにくいという状況が生まれる。
つまり、日本の経済情勢が根本的に好転しない限り、今の労働者の状況は簡単には変化しない。
よって、労働者が与えられた仕事を沢山こなしたとしても、報われにくい社会になっていると言える。
しかし、一方で多くの労働者は、企業に所属し、労働時間を提供することで賃金をもらっている。
労働者は「賃金をもらうこと」が第一の目的であるから、企業に「労働時間」を提供して働いている。
しかし、賃金を得るための方法は「労働時間の提供」だけなのか?
賃金を得る方法は労働時間の提供以外にも多々存在する。
しかし、多くの人は労働時間の提供しか行っていない。
まさに、現代に働く労働者の問題点はここにある。
賃金を得るもう一つの方法は、「労働価値」を提供することである。
すなわち、労働を通じて提供した価値の多寡により、賃金を得るということである。
このような考え方を持っている医療・介護職は非常に少ない。
9時から17時まで働いて、帰る。という働き方のスタイルでは到底、「労働価値」という考え方には及ばない。
この「労働価値」のメリットは、賃金が上昇する可能性を高くするだけでなく、自分自身の得意分野や好奇心の強い分野で仕事を行うことができることである。
「労働価値」で賃金を得る方法を獲得すれば、 労働環境が熾烈な企業で働く必要性がなくなる。
精神的にも会社に依存せず、自由になることができる。
また、賃金を支払ってくれる対象も、所属している企業から社会にある企業に変化する。
医療・介護職は、労働価値を提供するという概念に乏しい職業である。
なぜならば、医療保険・介護保険という公定価格に守られて、必要最低限の作業をしていれば賃金がもらえる環境が整っているからである。
しかし、そんな職場は間違いなく企業の論理に支配される。
「労働時間」の提供から、「労働価値」の提供へのWork Shiftが求められているが、そのことに気付いている人は少数派である。
働き方に対する個人の価値観が試されている時代に突入している。