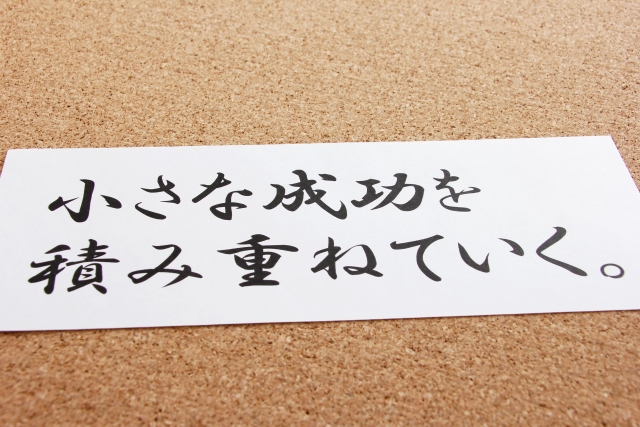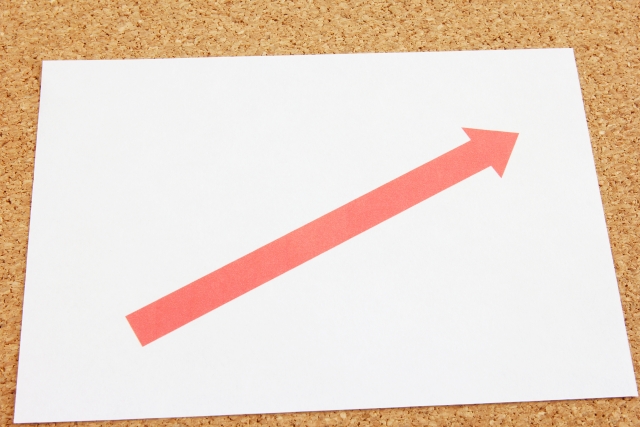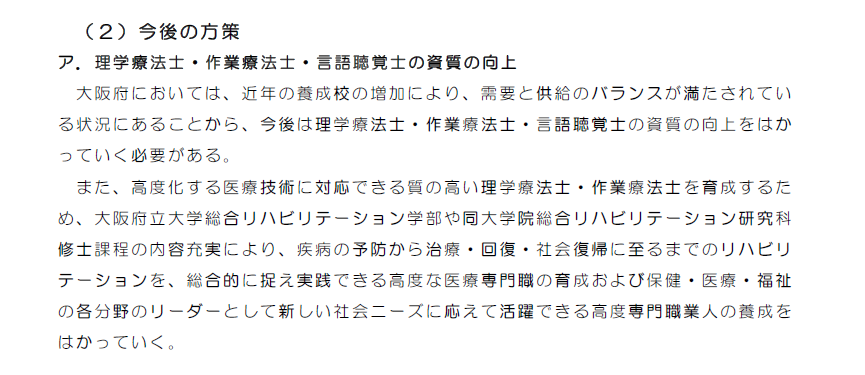多くのセラピストがダブルワーク、トリプルワークをしている。
本業だけは、生活が苦しかったり、自己研鑽の費用の捻出が苦しかったりする。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の平均年収は400万円以下であり、今後もそれを超えることはないだろう。
平均年収400万円では、将来の生活に不安がつきまとう。
よって、多くのセラピストは、休日に時給の高い非常勤を行うことが多い。
しかし、もう一段階上の次元での働き方をお勧めする。
その非常勤はあなたにとってどのような投資であるのか?という視点を持つことである。
非常勤で働いている時間は、人生にとって非常に重要な時間を切り売りしている時間でもある。
時間は有限であり、時間をいかに有効活用できるかで将来の収入や充実感が変化すると言っても過言ではない。
そんな貴重な時間を、単なる時給稼ぎのために使用することは避けるべきである。
これからの時代は、本業と副業の区別がない時代であり、すべての経験を本業と捉え、そのキャリアを人生や仕事で活かしていく姿勢が求められる。
例えば、回復期リハビリテーション病棟に勤務をしているセラピストが、訪問リハビリテーションにて非常勤勤務したとする。
訪問リハビリテーションでは、医療と介護の連携が難しかったり、高いコミュニケーション能力が求められたり、看護師との連携が必要になったりする。
これらの経験は、確実に回復期リハビリテーション病棟での業務に活きるとともに、将来への投資になる。
個別場面で経験したことを、統合し、仕事をする上での価値観として統合していくことがこれからの時代のキャリアデザインでは必要である。
本業と副業はあくまでの収入の大きさだけで判断をした分け方である。
キャリアや経験という意味では、本業と副業という分け方は不適切である。
経験していることがすべて本業である。