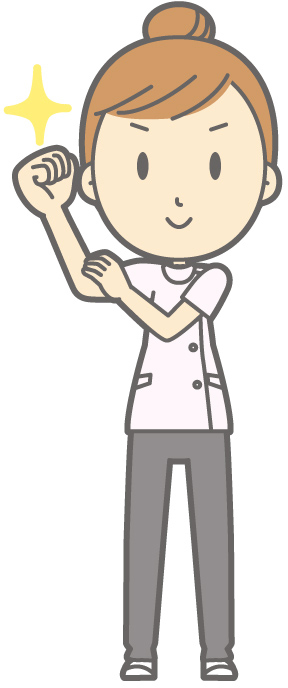臨床において最も重要な能力は「想像力」である。
なぜ、こんな現象が起きているのだろうか?
このような事をしたら、どうなるのだろうか?
この現象の原因はここではないだろうか?
常に仮説を立てて、その仮説が正しいかどうかの検証を繰り返す能力が臨床では求められる。
そして、「想像力」の源泉は、「基礎的な能力」である。
さらに、基礎的な能力は 「知識」×「経験」 により開発される。
言い換えれば、いくら経験があっても知識がなければ基礎的な能力は開発されない。
教科書や参考書に記載されている知識というのは、全くの素人を短時間で一定レベルの専門家にする代物である。
知識というのは、知っているか、知っていないかという両極端な性質を持つ。
したがって、知識がなければ、いくら想像したところで仮説は生まれてこない。
その知識を臨床の中で試行錯誤しながら用いることで、様々な仮説検証を展開できる。
よって、いくら経験があっても、知識がなければ仮説検証ができず、「理学療法もどき」「作業療法もどき」「言語聴覚療法もどき」しか展開できないことになる。
今の時代、マニュアル教育が軽視されている。
マニュアルを知っていても、実践では使えないと平気で言う管理職さえもいる。
しかし、マニュアルに書かれていることさえも理解できずにどうやって臨床を展開できるだろうか?
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士にとって、解剖学、病理学、運動学、生理学などのテキストは重要なマニュアルである。
マニュアルさえも理解できずに、難しい手技や理論を他者から教授されても全く持って理解できない。
むしろ、多くの患者はマニュアルに書かれていることだけで多くのことが解決できる。
エビデンスに基づく医療が叫ばれて久しいが、エビデンスとは最新の理論や論文に記載されていることだけではない。
すでに証明されて、教科書やマニュアルに載っていることを使いこなすこともエビデンスに基づく医療である。
マニュアルを軽視しては、いけない。