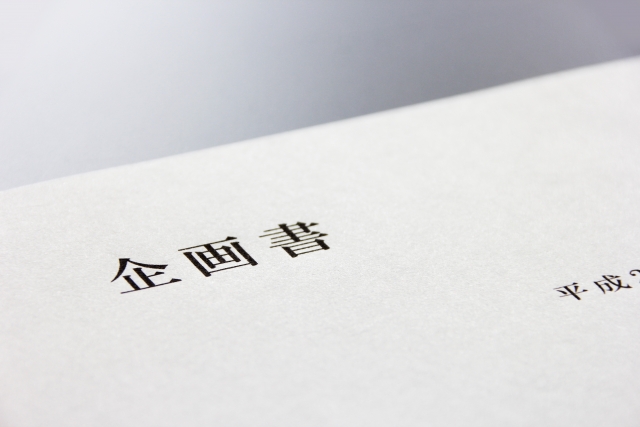2015年度介護報酬改定では、リハビリテーション分野において「心身機能」・「活動」・「参加」の重要性が明示され、通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションでは「活動」と「参加」に資する取り組みを評価する介護報酬項目が整備された。
活動・参加の概念は、リハビリテーション本来の意義を問いただすものであり、これからの高齢化社会においては益々重要となる。
しかし、筆者はこの一年間感じてきた違和感がある。
心身機能の評価や介入が未熟なセラピストに限り、「活動」「参加」が重要だと異常に訴える事例が散見することである。
自身の理学療法・作業療法・言語聴覚療法が未熟なことで、患者や利用者の基本動作能力・応用的動作能力・言語聴覚機能が回復しないことに気づいていないセラピストは残念ながら存在する。
そういったセラピストが、十分に患者や利用者の心身機能のポテンシャルを引き出してない中で、「活動」と「参加」に傾注することは、患者や利用者にとって迷惑千万な話ではないか?
セラピストと患者・利用者の間には「情報の非対称性」が存在する。
情報の非対称性とは
保有する情報に差がある時に生まれる不均等な情報構造
の事を言う
つまり、患者や利用者はセラピストより心身機能・活動・参加に関する情報を有していないため、セラピストの言いなりになる傾向がある。
セラピストが、「あなたの心身機能はもうプラトーなので、自宅では歩行器を使って歩きましょう」と説明すると、「心身機能がプラトー」であると判断する情報を患者や利用者は有していないため、セラピストの説明に従う可能性が高い。
しかし、心身機能の評価や介入に長けたセラピストがその患者や利用者を診れば、「十分に自立歩行を目指せる」と評価する可能性もある。
「活動」・「参加」はリハビリテーション上の目標であり、人が自分らしく生きていくために必要な概念である。しかし、心身機能の向上の追求なしに、「活動」「参加」という表面的な概念だけを妄信的に追いかけていくことは、リハビリテーションの概念にも反する。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、他職種と比較して、医学的側面から心身機能を評価できるアドバンテージを有しており、そのアドバンテージを活かして、「活動」・「参加」を客観的に冷静に評価・介入することが最大の強みである。
心身機能の評価・介入を軽視した「活動」・「参加」への妄信的な取り組みは、視野の狭い「活動」・「参加」偏重主義者であり、決して、患者や利用者のQOLの向上には寄与しないだろう。
心身機能・活動・参加
この概念の全ての要素を限りなく追求する事で本来のリハビリテーションが達成できる。
当然、心身機能だけを追求し、活動・参加を無視することはあってはならない。
リハビリテーションサービスのインフラが整ってきている時代だからこそ
心身機能が評価できて
活動も評価できて
さらに、参加も評価できる
が当たり前にできるセラピストが真に活躍する時代が近づいているのではないだろうか?